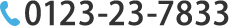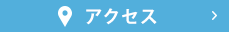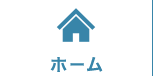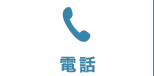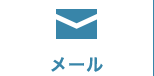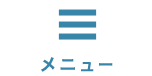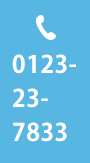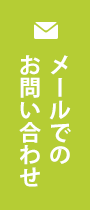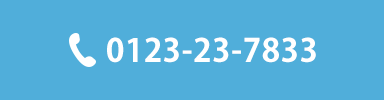膝に”水が溜まる”とは何か~関節水腫の基礎知識~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「膝に水が溜まる」という表現は、医学的には関節水腫(かんせつすいしゅ)といい、膝関節包の中に通常より多くの関節液が溜まって膝が腫れたり圧がかかって痛みを感じたりする状態です。膝関節を包む滑膜(かつまく)という組織が関与していて、滑膜が炎症を起こしたり、物理的な刺激を受けたりして、関節液の産生が過剰になったり、逆に吸収・排出が追い付かなくなったりすることが原因です。
関節液そのものは、関節を動かす時の潤滑、衝撃吸収、軟骨への栄養補給といった役割があり、通常は少量(1~3ml前後)であれば問題になりません。ですが何らかの異常があって量が増えると、「水が溜まっている」と感じるようになります。
膝に水が溜まる要因~生活習慣から器質的な疾患まで~
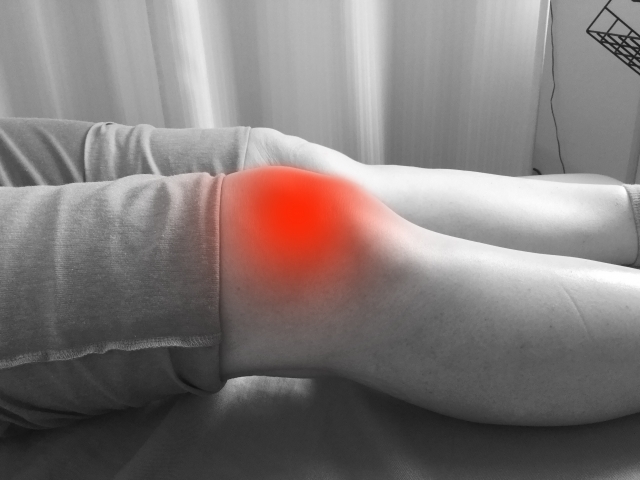
「なぜ水が溜まるのか」にはいくつかの要因があります。大きく分けて日常生活・外的な要因と、身体内部の器質的な疾患があります。
・体重過多・肥満
膝関節の荷重が大きくなり、軟骨や半月板などにストレスがかかる→摩耗や微小損傷、炎症を引き起こすことがあります。
・膝への過度な使用・負荷
階段の昇降、長時間立つ、しゃがみ、正座など膝を曲げ伸ばす動作が多い、スポーツでの強い衝撃・捻れ動作など。これらが繰り返されると摩耗や半月板・靭帯の損傷を招きやすい。
・加齢・筋力低下
歳を取るにつれて軟骨の修復力・弾力性が落ち、滑膜や関節構造を支える筋肉(特に大腿四頭筋など)が弱くなると、膝関節に負担がより集中するようになります。
・姿勢・アライメントの異常(O脚・X脚など)
歩行時や立っている時に負荷が均等にかからず、特定の部分に摩耗や圧が集中することで滑膜への刺激が起きやすい。
ここが非常に重要です。水が溜まる背後には様々な「器質的な疾患」が関与していることが多いです。
・変形性膝関節症
特徴:軟骨の摩耗、関節列隙狭小化、骨棘の形成など。加齢・過度の負荷・肥満が関与。
水が溜まる理由:軟骨や骨の摩耗で滑膜が刺激され、炎症を起こし関節液の過剰分泌・吸収障害が起きる。中~進行期には関節水腫を伴うことがしばしば。
・半月板損傷
特徴:スポーツ外傷、ねじれ、加齢による変性(老化変性)などで半月板が裂けたり断裂したりする。
水が溜まる理由:半月板の断片が関節内を刺激し、滑膜炎を起こす。炎症により関節液が過剰分泌され水が溜まる。
・靭帯損傷(前十字靭帯など)
特徴:膝の安定性が失われ、関節軟骨や滑膜に異常な動き・ストレスがかかる。外傷による炎症も強い。
水が溜まる理由:靭帯損傷に伴う出血や炎症が関節液の量の増加・吸収低下を引き起こす。外傷後の関節水腫が典型的。
・関節リウマチ・炎症性疾患
特徴:免疫異常により自分自身の関節を攻撃する疾患。関節全体に炎症を広げる。
水が溜まる理由:滑膜が慢性的に炎症を起こし、関節液の生成が亢進するなど。水が溜まることが症状の一つ。
・痛風・偽痛風(結晶性関節炎)
特徴:尿酸結晶やピロリん酸カルシウム結晶などが関節内に沈着し、急激な炎症を起こす。
水が溜まる理由:炎症により滑膜刺激・関節液産生亢進。急性発作時は膝の腫れ・水の溜まりが顕著。
・関節内遊離体(関節ネズミ)
特徴:軟骨や半月板などのかけらが関節内を滑るように浮遊する状態。動く位置によって痛み・引っかかりを生じる。
水が溜まる理由:遊離体が滑膜を物理的に刺激し炎症を起こす→関節液が増加。
・外傷・骨折
特徴:骨折、打撲、転倒などで関節内に損傷・出血を伴うもの。靭帯・軟骨の損傷も含む。
水が溜まる理由:出血+炎症。特に血液が混ざることもあり、腫れ・水たまり・可動域制限を伴う。
・感染症性関節炎
特徴:細菌などによる関節内の感染。発熱など全身症状を伴うことも。非常に急性・重篤になることあり。
症状として現れること・見分け方

膝に水が溜まると、以下のような症状が出ることが多いです。
・見た目での腫れ・膨らみ(膝蓋骨の周囲が丸く見える、皮膚が張っている感じ)
・動かす時の痛み(曲げ伸ばし・階段の昇り降り・しゃがむ・立ち上がる)が増す。静かにしている時は軽いが動くと痛むことが多い。
・熱感・赤み・触ると温かさを感じることも。炎症が強い場合。
・可動域制限:膝が完全に伸びなかったり曲げにくかったりする。膝が重く感じる、曲げ伸ばしに引っかかりや違和感。
・朝や休んでいた後、動き始めが”こわばる”感じがある。
また、関節液の色・性状(透明度・濁り・血の混入など)を検査することで、原因疾患をある程度予測できることもあります。
統計データ~日本の現状~

膝に水が溜まるという症状の背景には、変形性膝関節症などの高頻度疾患があるため、以下のデータが参考になります。
1.「変形性関節症の国内有病率」
ROADスタディ等により、40歳以上の日本人でレントゲン所見(X線)によりKLグレード2以上の変形性膝関節症と診断される者の割合は、男性で約42.6%、女性で約62.4%。これを年齢別人口構成にあてはめて推定した国内の患者数は、約2,530万人。(https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/57/11/57_571102/_pdf)
2.「自覚症状ありvs潜在的な患者数」
日本では、変形性膝関節症で自覚症状を伴う患者数が約1,000万人、X線などでML所見を含む潜在患者数が約3,000万人と推定されています。(https://www.jinko-kansetsu.com/pain/knee/oa.html)
3.「国内の有症患者数と要治療者数」
別の報告では、総人口約1億2,500万人のうち、変形性膝関節症の患者数は約2,500万人にのぼり、その中で特に治療を要する者が700万人。性差としては女性が多い。(https://www.kieikai.ne.jp/news/detail.php?seq=383)
整骨院でできること
千歳市の青葉鍼灸整骨院として「膝に水が溜まる」患者さんに対してできる対応は、根本原因の見極めと症状緩和、その後の再発予防です。
1.問診・視診・触診
いつから腫れたか、痛みの性質(動かすと痛むか、安静時も痛むか)、熱感の有無、過去の外傷歴・手術歴、膝の負荷がかかる生活動作などを詳しく聞きます。
2.検査・画像診断への橋渡し
整骨院の範囲でできる検査(例えば動き、可動域、筋力・柔軟性などの評価)を行うと共に、症状が強かったり疑いが深い器質的疾患(例:半月板損傷・靭帯損傷・関節リウマチ・感染症など)がある場合は整形外科でのレントゲン・MRI・関節液検査などを紹介することが重要。
3.保存的な治療アプローチ
・安静・アイシング:急性期の腫れ・痛みを抑えるため
・物理療法:温熱・電気・超音波などで血流を改善し、炎症を抑える
・負荷軽減・サポート:サポーターなどの装着、歩き方の指導、動作指導など
・筋力強化・柔軟性改善:下半身の関節をバランスよく使えるためのエクササイズ、運動。これによって膝関節を安定させ、関節への異常な負荷を減らす。
4.医療との連携
保存療法で改善が見られない・器質的疾患が疑われる・感染症の疑いなどがある場合は整形外科での診断・治療を検討する(注射・手術など)。
5.再発予防
生活習慣の見直し(肥満対策、膝に負荷のかかる動作の回数を減らす、姿勢・歩行の改善など)、定期的なストレッチ・筋トレなど。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
なぜ早めの対処が大切か

膝に水が溜まるのを放置すると、以下のような問題が起こる可能性があります。
・関節の可動域制限が進み、日常動作(歩行・階段の昇降・座ったり立ったり)が困難に。
・痛みの慢性化→夜間痛・安静時痛の出現
・軟骨・半月板などの損傷が進む→変形が進行する
・全体的な歩行機能低下・生活の質の低下
ですので、症状を感じたら早めに整骨院で相談、必要なら整形外科と連携することが望ましいです。
最後に
「膝に水が溜まる」症状は、ただの腫れ・むくみではなく、膝関節の内部で何らかの異常・炎症が起きているサインです。器質的な疾患(変形性膝関節症、半月板・靭帯損傷・関節リウマチ・痛風など)が背景にあることも多く、正しい診断・適切な対処が必要です。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みや腫れの緩和だけでなく、原因にアプローチし、再発を防ぐためのケアを提供しています。気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。