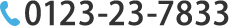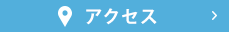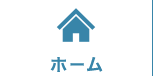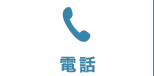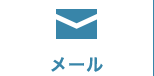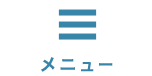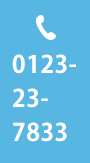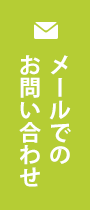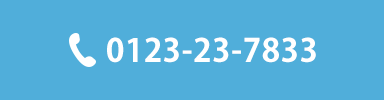膝の内側が痛む方へーー整骨院からのアドバイスと対策
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
なぜ「膝の内側」が痛むのか?
膝の痛みは、部位によって原因や対応が異なることが多く、その中でも膝の内側に痛みを感じるケースは意外と頻度が高く、生活やスポーツに支障をきたす方も多くおられます。
「歩くと膝の内側がズキッとする」「階段降りると膝の内側が痛む」「運動後、膝を内側に押すような痛みが出る」などの症状は、軟部組織・骨・靭帯・関節包・軟骨構造・筋肉バランスなど、複数要因が絡んでいる可能性があります。
整骨院としては、痛みを和らげるだけでなく、再発しにくい膝の使い方・姿勢・筋バランスを整えることが目標です。今回の記事では、膝の内側痛の背景、原因、セルフケア、予防法、整骨院でできるアプローチを中心にご紹介します。また、膝痛に関する統計データも交えて、お伝えしていきます。
膝痛・内側痛に関する統計データ(日本・世界規模での傾向)

以下、膝痛全体や変形性膝関節症、痛み部位分布に関する統計を挙げます。
1.慢性膝痛の有病率(日本・中高年層)
日本の中高年(40~79歳)を対象とした疫学研究では、慢性膝痛を訴える人の割合は、10.7%と報告されています。このデータは、膝痛が比較的広範囲に存在する健康課題であることを示しています。(PMC)
2.日本における膝関節症と症候性膝痛の傾向
日本の大規模コホート研究”ROAD調査”などによれば、X線的な膝関節の変形(変形性関節症:OA)を持つ人の割合は高く、膝痛を伴う人、つまり症候性変形性膝関節症(痛みを伴う膝OA)の割合は、一定割合存在することが指摘されています。また、女性、年齢、肥満などがリスク因子としてしばしば挙げられています。
3.膝痛発症率・男女差・全体割合
米国を含む複数国の研究では、成人の膝痛訴える割合(有症状性膝痛)は約25%程度といわれています。(AAFP)
さらに、X線的な変形や痛みの発生リスクを追った縦断研究では、年齢や性別・BMI・生活様式が影響を与えると報告されています。
これらの統計を背景に、「膝痛(特に内側痛)」が決して稀なものではなく、多くの人にとって身近な問題であることを理解して頂けると思います。
膝の内側痛が起こるメカニズム・関係因子

膝の内側が痛む場合、注目すべき主な構造・要因を以下のように整理できます。
1.内側側副靭帯(MCL)のストレス
膝の内側を支える主要な靭帯であるMCLは、膝が外側から押されるような力を受けた時に緊張します。スポーツでの接触や急な方向転換、膝関節の不安定性があれば、この靭帯にストレスがかかりやすくなります。
2.内側半月板・半月板損傷
半月板は膝のクッション・安定化構造として働きます。内側半月板に損傷・変性があると、膝の内側に疼痛や引っかかり感・違和感が出ることがあります。特に膝を曲げたり捻じったりする動作で症状が強くなることが多いです。
3.軟骨摩耗・変形性膝関節症(内側型膝OA)
膝関節の内側には荷重がかかりやすく、変形性関節症(OA)の進行もこの部位で目立つことがあります。内側関節面の軟骨すり減り、関節列隙(関節の隙間)が狭くなる変化が進むと、特に荷重時に内側部に痛みが出やすくなります。実際、X線変形所見を持つ人と痛みを伴う人は相関性が指摘されています。
4.アライメント(膝の傾き・軸・ずれ)・歩行運動連鎖
O脚傾向、膝内旋・内転方向のずれ、股関節/足関節からの連鎖異常などがあると、膝の内側にかかる荷重・ストレスが増えやすくなります。荷重ラインが本来より内側に入り込み、内側軟部組織に負荷が集中するパターンです。
5.筋力バランス・支持組織の弱さ
内側支持に関わる筋肉(内側広筋・内転筋群・大腿四頭筋全体・ハムストリングスや腓腹筋など)や靭帯・腱の協調が悪いと、動作中に膝の安定性が低下し、その結果、内側部への過負荷が起きやすくなります。
6.過負荷・反復ストレス
歩行・階段昇降・ランニング・重量物の持ち運びなど、日常動作の反復ストレスが、もともと弱い内側部組織に蓄積され、痛みを引き起こすことがあります。特に変形性変化が進行傾向にある方では、症状が発症・憎悪しやすいです。
また、痛み部位が「内側か、広く散らばってか」などによって臨床像や対応の方向性が変わるという研究もあります。たとえば、慢性膝痛患者を対象とした調査では、痛みの位置(内側・外側・前方・後方など)により機能性や疼痛・運動制限・生活の質への影響が異なるという報告もあります。
さらに、内側荷重を示す力学指標(KAM:膝内反モーメント)と痛み強度との関連を分析した研究でも、KAM指数が痛みと相関する可能性が示唆されています。
これらを総合すると、膝の内側痛は「構造変化✖荷重バランス✖筋肉/靭帯支持力✖動作連鎖」の複合影響で起きやすく、また一因だけを治療しても十分な改善が得られにくいことが多いです。
整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、以下のようなステップで膝内側痛にアプローチしていきます。
1.評価・アセスメント
・痛み部位の明確化(圧痛・可動域異常・不安定性)
・膝のアライメント・軸ズレ評価
・股関節・足関節・骨盤の連鎖評価
・筋力バランスチェック(内側広筋・大腿四頭筋・内転筋・ハムストリングスなど)
・日常・動作パターン分析(歩行・階段昇降・しゃがみ動作など)
2.筋膜リリース・軟部組織調整
膝周囲、太もも・ふくらはぎ・腸脛靭帯・膝包・内側靭帯周辺など過緊張・癒着が考えられる部位を筋膜リリースや手技で調整します。
3.関節モビライゼーション(可動域誘導)
膝関節・脛骨・大腿骨間の滑走性改善、内側関節間隙への荷重誘導など、関節可動域の改善を図ります。
4.アライメント調整・支持性強化
O脚傾向・膝内旋・外旋ずれを戻して股関節が使えて殿筋が働きやすい位置での安定性を体の感覚として認知してもらえるように刺激を入れます。
5.物理療法・補助療法
痛みや炎症期には、超音波治療・マイクロ波・ホットパック・微弱電流治療などを併用することもあります。
6.定期メンテナンス・フォローアップ
痛みが落ち着いた後も、定期的なチェックとメンテナンス(柔軟性維持・筋力調整)を行い、再発防止を図ります。
7.他科連携の判断
もし内側痛が強く、改善が見られない場合や「引っかかる感じ」「腫れ・膝ロッキング・膝の引き伸ばし不能」などの症状があれば、整形外科で半月板損傷・靭帯損傷・変形性変化の画像検査を検討すべきです。
まとめ
・膝の内側に痛みを感じる方は、靭帯・半月板・軟骨変性・アライメント異常・筋バランス不良など複数因子が関与している可能性があります。
・統計データからみても、膝痛(特に加齢者・中高年層での膝関節症)は比較的高頻度な健康課題であり、その中で内側痛を訴える方も一定数存在します。
・整骨院では、筋膜・軟部組織調整、関節可動域改善、アライメント調整など組み合わせて改善を目指します。
・痛みが強い・長く続く・膝が引っかかる・動くが制限されるといった場合は、早めに専門医との連携も視野に入れましょう。
もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。