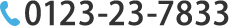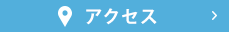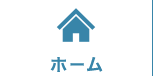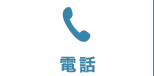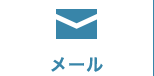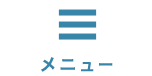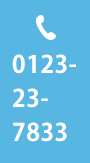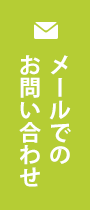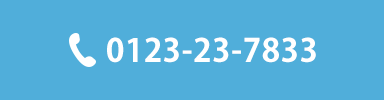千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
はじめに
授業中、黙って座っている時に「首が重く感じる」「肩甲骨あたりがだるくなる」「肩が張って集中できない」と感じる学生さんは、思っているよりも多いものです。
長時間同じ姿勢、ノートやスマホの使用、視線の向きなど、授業スタイルと密接にかかわっていることが多く、早めの対処が必要です。今回は、なぜ授業中にこうしただるさが出るのか、セルフチェックや整骨院でできるケア、日常で気をつけるポイントまでを解説します。
「授業中に首がだるくなる」の実態と原因

授業中は、黒板・スクリーン・教科書・ノートなどを見ながら長時間首を少し前に傾けたり、下を向いたりすることが多くなります。
具体的には
・顔や机の距離の不一致→無意識に首を前に出す
・教科書を下方向に置きすぎ→視線が下がって首に負担
・手書きノート作成で肩を丸める姿勢
・スマホやタブレットで画面を操作する時間
・座席の姿勢が悪い(深く座る、肘をつくなど)
これらが筋肉・関節・神経にストレスをかけ、「だるさ」「凝り感」「張り」を引き起こしやすくします。
首・肩甲骨付近の筋(僧帽筋・肩甲挙筋・菱形筋など)は、長時間の緊張や固まりですべりが悪くなることがあります。これが動きの制限やだるさ感につながります。
また、肩甲骨まわりの動きが弱いと、肩関節や首の負担が増大します。肩甲骨の後傾・内転運動が十分に出ていないと、肩と首の筋に先行して負荷がかかりやすくなります。(j-stage)
頭は重さがある部位ですので、前傾するだけで首への負担が急増します。学生では教科書やスマホ利用などによりこの傾向が強くなりがちです。実際、大学生を対象とした調査では、一般集団で首痛の有病率が23.1%であるのに対し、大学生では48~78%という高い割合が報告されています。
肩・肩甲骨の可動性が低いと、首の筋肉が代償して引っ張られやすくなるため、だるさにつながることがあります。肩痛・肩関節症の疫学データでは、肩痛の1ヵ月有病率は18.5~31%、1年有病率は4.7~46.7%と報告されており、肩周囲の不調は比較的頻度が高いとされています。(physiotutors)
・小中高校生・大学生を含む学生層でも、首痛・肩こりの訴えは少なくありません。例えば高校生を対象とした調査では、首・肩こりの有病率が23.7%と報告されています。
・また学部学生全体の筋骨格痛調査では、回答者のうち71.2%が”頸部痛”を最も頻度高く経験した症状と回答したとの報告もあります。(frontiers)
これらから、学生期における首・肩のだるさ・こりは無視できないテーマです。
セルフチェック:授業中に「怪しいサイン」を見逃さないために

下記チェックをやってみてください。該当が多いほど対策が必要と考えられます。
1.首の左右回旋
授業中、ふと首を左右に振ったとき、片側が回しにくい/引っかかる感じがある
2.首の前後屈
あごを胸に近づけたり、天井を見上げる時に詰まり感・張り感がある
3.肩すくめ・肩上げ
肩をすくめたり、耳に近づけるように力を入れると首・肩甲骨周辺がつっぱる
4.肩甲骨内転/外転(背中で肩甲骨を寄せる/開く)
腕を後ろに引いて肩甲骨を寄せる時に、背中が突っ張る
5.腕を前上方へ挙げる
肘を伸ばして腕を上げた時、肩甲骨・首に引っかかり感がある
6.長時間座っていて疲労感が強く出るか
授業後半になると首・肩甲骨まわりが重くなって動かしづらくなる
これらを記録しておくと、整骨院での最初の評価時に非常に役立ちます。
整骨院でできるケア・アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、授業中のだるさを軽減し、首・肩甲骨・肩回りの動きを取り戻すために、次のような施術や指導を行います。
〇視覚分析と姿勢評価
・授業時の座り方・机・ノート配置・画面高さを再現してチェック
・肩・首・背骨・骨盤のアライメントチェック
・動きやすさ、制限の出ている方向を詳細に把握
〇筋肉・筋膜アプローチ
・トリガーポイント療法:凝り固まったしこり点を指圧・緩和
・筋膜リリース:首から肩・肩甲骨周りの滑走性を改善
・ストレッチ:肩甲挙筋、僧帽筋、菱形筋、斜角筋、胸鎖乳突筋など
〇関節可動域改善
・頸部関節可動性改善
・肩甲骨・肩関節・胸椎連動可動性改善
〇補助療法・物理療法
・温熱療法・低周波・超音波などによる筋緊張緩和
・テーピングや支持具で姿勢を補助
〇運動療法・セルフケア指導
・姿勢改善エクササイズ:頭部後退運動(チンイン)、肩甲骨引き寄せ運動
・肩甲骨周囲運動:肩甲骨上下・内転動作を使う運動
・首の可動域訓練:ゆっくりと首を前後・左右に動かす
・簡易ストレッチ:授業合間に出来る首・肩のストレッチ
・休憩タイミング・姿勢切り替え
日常・授業中で意識したいセルフ対策
不調改善を早めるために日常的に出来る事を取り入れましょう。
1.座り方と机の高さ・視線調整
教科書・ノート・画面は目線に近い高さに。首を無理に傾けない配置を心がける。
2.こまめなルーティン休憩
50分授業なら、10分休憩で肩・首を伸ばす・立ち上がる動作を入れる。
3.スマホ・タブレット利用の制限
授業外のスマホ操作時間を意識的に長く利用しない。
4.軽いストレッチを兼ねた休憩動作
背伸び・肩回し・頭をゆっくり回すなど、間に挟む変化を作る。
5.バッグ・荷物の持ち方に注意
重いバッグを片肩にかけない・使い方を交互にする。
6.適度な運動習慣
部活・軽い運動、背筋・肩甲骨周囲筋を使う運動を入れる。
7.睡眠・枕の見直し
高さ・硬さがあっていない枕は首の負担になります。仰向けで首に無理のないものを選ぶ。
まとめ
授業中に首がだるくなるという悩みは、学生にとって決して珍しいものではありません。長時間同じ姿勢、視線・机の配置、スマホ・ノート操作などが重なって、首・肩甲骨・肩周囲にだるさや凝りを起こしやすくなります。整骨院では、姿勢の評価・筋膜・関節アプローチ・運動療法・セルフケア指導を組み合わせて、だるさを軽くし、授業中も快適に過ごせるようサポートできます。
もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。