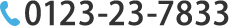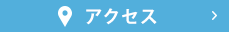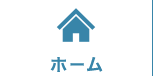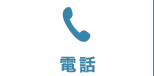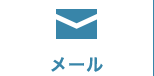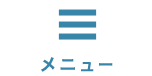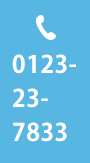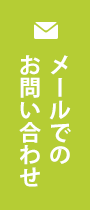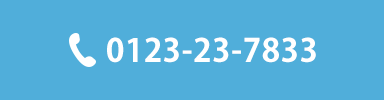スポーツで足首を痛めたら?
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
スポーツをやっていると、ジャンプの着地でグキッ、方向転換でひねった,,,そんな経験をしたことがある人は多いでしょう。足首のケガ(特に捻挫・靭帯損傷)はスポーツ選手・愛好家にとって、起こりやすく、放置すると慢性化するケースもあります。
この記事では、足首ケガの頻度・統計、原因・メカニズム、整骨院でできる処置・リハビリ、予防法などをまとめ、スポーツに打ち込むあなたをサポートできる内容をお届けします。
足首ケガはどれほど多い?ー統計でみる実態
まずは、「足首ケガ」がスポーツ界でどれくらい起きているのかを、信頼できるデータで確認しましょう。
1.スポーツ傷害全体に占める割合
足関節捻挫・損傷は、「足関節を含む外傷」がスポーツ傷害全体の大きな割合を占めるという報告があります。例えば、日本のスポーツ傷害統計データ集では、捻挫・打撲・靭帯・腱損傷を含む「足関節捻挫」がスポーツ外傷全体の11%に相当するという記載があります。(リンク)
2.アスリートにおける捻挫・足首損傷の発生頻度
国際的文献でも、スポーツ傷害のうち16~40%を足首捻挫が占めるとの報告があります。
また、高校スポーツにおいても足首捻挫はよく見られ、全傷害の15%程度を占めるケースも報告されています。(リンク)
3.再発率・慢性化する割合
足首捻挫は再発しやすく、「慢性足関節不安定性(CAI)」に移行するリスクも高いとされています。例えば、バスケットボール選手では捻挫後、再発例が60%に達するとの報告もあります。
また、逆足関節捻挫の再受傷率が73.5%に上るという調査もあります。(リンク)
これらのデータから見えてくるのは、足首ケガはスポーツでは常に起こりうる、リスクの高い領域であり、初回ケガ後のケア・予防が極めて重要だという事です。
足首ケガのメカニズム・原因

足首ケガと一口に言っても、損傷する構造(靭帯・関節包・軟骨・骨・腱など)や損傷のタイプはさまざまです。ここでは、多く見られる捻挫・靭帯損傷を中心に、原因やリスク因子を整理します。
〇捻挫の典型パターン
・内反捻挫(外側靭帯損傷)
足首を底屈+内反(足の裏が内側に傾く)すると、外側の前距腓靭帯(ATFL)・踵腓靭帯(CFL)などに負荷がかかり損傷しやすくなります。
・外反捻挫(内側靭帯損傷)
まれですが、足首を外側に強く反らせると三角靭帯(内側靭帯群)を痛めることがあります。
・高位捻挫・脛腓靭帯損傷
足首の回旋+引き離し力で、脛腓間靭帯を損傷するケースもあります。
・関節軟骨・骨棘・軟骨損傷
捻挫時には靭帯だけでなく、軟骨や骨の面にもダメージが及ぶことがあります(軟骨剥離・骨挫傷など)。
〇リスク因子・誘因
1.過去の捻挫歴
捻挫したことがある足は、再度捻挫するリスクが上がります。靭帯・受容器組織が緩むことが背景にあります。
2.足関節可動性制限
背屈可動域が制限されている人は捻挫を起こしやすいとの報告があります。
3.筋力・筋バランス不良
足首周囲筋(前脛骨筋、腓骨筋、後脛骨筋など)が弱い、アンバランスな場合、捻りに対する制御が甘くなることがあります。
4.支持系の不整合(靴・インソール・地面)
適切でない靴・インソール・不安定な地面などは捻挫の誘因になりやすい。
5.疲労・集中力低下
後半になると動作が甘くなり、足首を不安定な状態で使ってしまうことがあります。
6.競技特性
ジャンプ・着地・急な方向変換などを多く含む競技(バスケットボール、バレーボール、サッカー、ハンドボールなど)は足首ケガ頻度が高いとされています。
整骨院ではどう対応するか

足首ケガを適切に処置・リハビリできれば、早期復帰・再発予防・慢性化防止につながります。整骨院でできるアプローチを、段階別にご紹介します。
1.急性期(直後~48~72時間)
・RICE原則:安静・アイシング・圧迫・挙上
・固定・支持:テーピング、包帯固定、サポーターなど
・除痛/炎症抑制:物理療法(超音波・低周波・マイクロ波など)
・腫脹制御:圧迫・マッサージ(リンパ促進方向)
※この段階では、過度な運動やストレッチは避け、まず安定化を優先します。
2.回復期(腫れ・痛みが落ち着いてきた段階)
・可動域回復:ゆるやかな関節可動域運動(背屈・底屈・回内・回外など)
・軟部組織のケア:筋・筋膜リリース、ストレッチなど
・支持構造強化:筋力トレーニング(等尺性・軽抵抗運動→動的運動へ)
・バランストレーニング:片足立ち・不安定面でのバランス運動
3.機能回復期(競技復帰を見据える段階)
・プライオメトリクス:ジャンプ・着地訓練
・方向転換トレーニング:ダッシュ・カット動作の反復
・競技特性に近い運動:実践動作シミュレーション
・テーピング/サポーター併用:負荷が高い時の保護
4.予防・定期フォロー
・可動性維持ストレッチ:足関節背屈・底屈・内外反方向
・筋力維持トレーニング:腓骨筋群、前脛骨筋、後脛骨筋など
・バランス訓練・プロプリオセプション
・動作改善指導:着地動作・重心移動・足運びなど
・装具・靴の見直し:インソール・サポーターレベル
まとめ
スポーツ領域での足首ケガは、捻挫・靭帯損傷が中心で、スポーツ傷害の中でも頻繁に起こります。統計的にも「スポーツ傷害のうち16~40%を足首捻挫が占める」などの報告があり、再発・慢性化のリスクも高いとされています。
整骨院では、受傷直後から段階的にアプローチを行い、可動域回復・筋力修復・バランス訓練・競技復帰支援まで対応できます。重要なのは、「ただ痛みを取る」だけでなく、「再び負傷しづらい身体作り」を見据えたケアです。
もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。