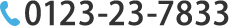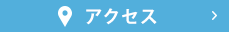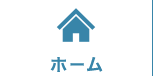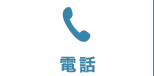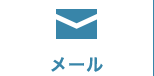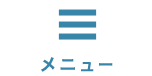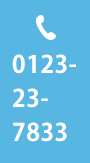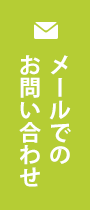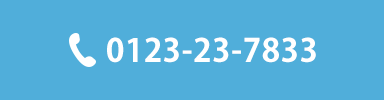はじめに
足を地面につくたびに「くるぶしが痛い」「歩くたびにズキッと響く」「痛みで足あげができず、つい引きずってしまう」──そんな症状でお悩みではないでしょうか。くるぶし周辺の痛みというのは、放っておくと日常の歩行・立ち仕事・家事に支障を来たすだけでなく、いつの間にか「痛みが慢性化」して、動きにくさを残してしまうケースも少なくありません。
ここでは「くるぶしの痛み」の背景、起こるメカニズム、統計を見ることでその多さ・身近さを感じてもらい、さらにどう対処・予防していくかを、青葉鍼灸整骨院の視点からお伝えします。
なぜ「くるぶし(足関節)」が痛くなるのか

くるぶしを含む足関節は、歩く・走る・立つ・方向を変える・体重をかける、という日常の動作で常に負荷がかかる部位です。そのため、次のような原因が考えられます。
1. 靭帯のねんざ・損傷
足をひねった、段差でグキッといった経験はありませんか?この「ひねる動作」によって、足関節の靭帯(特に外側の靭帯)が損傷を受けることがあります。いわゆる「足関節捻挫(ねんざ)」です。捻挫をきちんと治療せずに放置すると、繰り返し痛みを出したり“くるぶしがぐらつく”ようになることもあります。
実際、海外の調査では、急性の足関節捻挫の発生率が「一般人口で年間2~7件/1000人年」程度という報告もあります。 PMC+1
また日本でも「初回捻挫の年齢が若いほど、その後慢性の不安定症になる可能性が高い」というデータがあります。 Biomedres
2. 慢性の足関節不安定症(CAI)
捻挫を繰り返したり、捻挫後に十分なリハビリを行わなかった場合、「足関節がぐらつきやすくなる(不安定になる)」状態=慢性足関節不安定症(Chronic Ankle Instability=CAI)に移行することがあります。日本の大学生アスリートを対象にした調査では、CAIの有病率がおよそ 8.2% という報告もあります。 日本臨床スポーツ医学会
不安定な関節は、着地や方向転換のたびに余分なストレスがかかり、「くるぶしが痛む」「蹴るとき力が入らない」「歩くとき違和感がある」など症状を残しやすいです。
3. 変形性足関節症など、関節の変化
年齢を重ねたり、かつての捻挫・骨折・不安定をきちんと治療しなかったりすると、足関節内の軟骨/骨・靭帯・関節包の変化から、変形性足関節症(Ankle Osteoarthritis)になることもあります。例えば日本の50歳以上の地域住民調査では、「足関節のレントゲン上変形性足関節症の有病率が13.9%」という報告があります。 PubMed
このようになると、痛み・動きの制限・歩行時の違和感が長く残ることがあります。
4. 足を引きずって歩く原因になる、歩行時の“代償動作”
くるぶしが痛いと「痛む方の足に体重をかけたくない」「かばって歩く」「片足でつく時間を短くする」など歩き方を変えてしまうことがあります。これが長く続くと、股関節・膝・腰など、他の関節にも余計な負荷をかけてしまい、身体全体のバランスが崩れてしまう可能性があります。
日本・世界で見た「くるぶし・足関節痛(捻挫含む)」の“身近さ・多さ”

痛みを放っておいて「自分だけかな?」と思われるかもしれませんが、実はかなり多くの方が足関節・くるぶしの痛み/捻挫リスクを抱えています。以下、統計を3つご紹介します。
- 日本の大学・部活動系アスリートを対象にした調査で、全傷害の中で「下肢(脚部)障害」が73.5%を占め、その中でも「足関節捻挫」が最も多かったという報告があります。 PMC+1
- 足・足首痛(foot & ankle pain)について、日本の看護師を対象としたアンケートでは、「過去1か月間に足・足首の痛みあり」の割合が SNQ で23%、MFPDI という尺度では51%という結果が出ています。さらに、「日常生活・仕事に支障が出た痛み」はそれぞれ4%・17%というデータです。 PMC
- 世界的に見ても、一般人口で急性の足関節捻挫の発生率は「2~7件/1000人年」という報告があり、実際には捻挫を医療機関に受診せずに済ませるケースも多く、真の件数はもっと多いと考えられています。 PMC+1
以上から、くるぶし・足関節の痛み・捻挫・不安定性というのは“珍しいこと”ではなく、「多くの人が経験しうる・経験している可能性がある」ものだと理解していただけると思います。
症状として出やすいサインと「引きずって歩く」状態の危険性
ご自身または周りの方の歩き方を振り返ってみて、以下のサインがあれば“くるぶし・足関節に何らかの負担・異変”が起きている可能性があります。
- 足を地面につくとくるぶし周辺(内側/外側)に痛みや違和感がある
- 痛い方の足をかばって、足を引きずるように歩いてしまう
- 歩き出し・立ち上がり時・方向転換時に「ズキッ」と痛みが出る
- かかとをついて歩けない、足先で体重を支える感じがする
- 腫れ・熱感・青あざ・捻った覚えがある(過去に)
- 捻挫をしたことがあるのに「もう大丈夫」と放置してしまった
「引きずって歩く」というのは、痛みを避けるために無意識に歩行を変えてしまった結果です。しかしこれが続くと、次のような “二次的なリスク” が生じます。
- 他関節への負担増:足関節をかばうことで膝・股関節・腰に過剰なストレスがかかる
- 筋力低下・バランス低下:痛み・かばいによって足裏・ふくらはぎ・周囲筋が十分に使われず、筋力・バランスが落ちる
- 慢性化・不安定化:捻挫を繰り返したり、きちんと機能回復をしないと「ぐらつき」「違和感」が残り、長期の悩みになる
- 歩く量・活動量の減少:痛みがあると「歩きたくない」「足が重い」「動くのが億劫」になり、生活の質が下がる
そのため、痛みを感じたら「様子を見よう」だけで終わらせず、早めに専門的なケアを検討することが重要です。
くるぶし痛・足関節トラブルへの対処の流れ

では、くるぶしの痛み・歩きづらさ・引きずるような歩行を改善するために、どんな流れで対処すればよいか、青葉鍼灸整骨院としてお勧めするプロセスをご紹介します。
① 原因の把握・検査・評価
まずは「何が原因で痛くなっているか」を整理します。以下のような観点を確認・評価します。
- 痛みが出たきっかけ(捻った、くじいた、段差で、転倒など)
- 痛みの出る場所・状況(どこのくるぶし/歩行・立ち上がり・階段)
- 過去の捻挫・骨折・手術歴
- 歩き方・荷重・左右差・立ち姿勢・靴の状態
- 腫れ・熱感・運動制限・関節のぐらつき感の有無
- 生活活動の制限(仕事・家事・趣味・歩く量など)
この段階で「捻挫だけじゃなく、変形性足関節症・靭帯損傷・慢性不安定症・アーチの低下・足底からの影響」など、複合的な原因があるかどうかを考えます。
② 損傷の回復促進・痛みの軽減
痛みが出ている段階では、まずは“痛みを鎮める”ことが大切です。整骨・鍼灸・物理療法(超音波・電気・温熱/冷却)などを用いて、以下を進めます。
- 炎症・腫れ・熱感がある場合:冷却・安静・荷重制限
- 痛みがやや落ち着いてきたら:温熱・鍼灸で血流促進・回復促進
- 周囲の筋肉・靭帯・関節包・腱のケア
- 歩行時・荷重時の痛み軽減機器(テーピング・インソール・サポーター)
この段階で「痛みや歩行の引きずり」が軽減してくると、その後の機能回復がスムーズになります。
③ 機能回復・バランス・筋力強化
痛みが落ち着いたら、次は「足関節+周囲(ふくらはぎ・前脛骨筋・腓骨筋・内側筋)」「バランス・支持脚・歩行の安定性」を整えていきます。たとえば:
- 足関節の可動域(背屈・底屈・内反・外反)を確認・改善
- 足部のアーチ・足底筋・足指・ふくらはぎ筋の強化
- 片脚立ち・バランスボード・不安定面上でのトレーニング
- 方向転換・ステップ・ジャンプ動作への復帰(スポーツをされる方)
- 歩行・立ち仕事・家事作業への戻り(痛み・引きずりなく)
このステージをしっかり行うことで、「次にまた痛めない・引きずらない」脚に変えていくことができます。
④ 予防・日常生活改善
痛みやつらさを繰り返さないためには、日常生活・履物・動作の見直しも重要です。
- 靴選び:かかと・足裏・アーチを支える靴、クッション性・安定性をチェック
- 段差・滑りやすい路面など足元環境に注意
- 立ち仕事・歩き仕事の方は“休憩時のふくらはぎ伸ばし”“足裏体重の均等化”を意識
- 運動前のウォームアップ・ストレッチ・バランストレーニングを習慣化
- 過去に捻挫をした方は、特に「再発予防(不安定にならない)」「左右バランス」を意識
なぜ「引きずって歩く」状態が長くなるのか?&早期対応のメリット
「足を引きずる=動きを変えて無意識にかばう」状態が続くと、次第に“痛みが日常”になってしまうことがあります。なぜそれが起こるのでしょうか。
- 痛みを避ける歩き方:痛む側に荷重をかけたくないため、体重を反対側にかけたり、足を引くようになったり。これがクセになる。
- 筋・靭帯・バランスの変化:かばいながら歩くことで、筋肉が十分に使われず筋力低下・支持力低下。靭帯・関節包の刺激が変わる。
- 慢性化・不安定化:一度捻った関節・痛んだ関節をきちんとケアしないと「関節がぐらつきやすい」「違和感が残る」状態に移行しやすい。
- 他の部位に波及する影響:足を引きずることで、膝・腰・股関節に余分な負荷がかかり、そちらに痛みが出てしまうケースも。
- 活動量の低下・生活の質低下:痛み・歩きづらさがあると“歩かない”“動かない”ようになり、さらに筋力低下・体重増加・循環の低下など負のスパイラルに。
だからこそ、「痛みを我慢して引きずりながら使い続ける」よりも、 “早めに適切にケアして”「正常に足をついて・歩ける脚に戻す」ことが、長期的な負担・再発リスク・他の関節への影響を軽くするために重要です。
青葉鍼灸整骨院でのケアの特長・お勧めポイント
(千歳市の当院ブログをご覧の読者向けに、当院でできることをご紹介します)
- 丁寧な問診・動作・歩行評価
痛みの出たきっかけ・過去歴・歩き方・立ち姿勢・左右差をしっかり確認。どのように「引きずって歩いてしまう」動作になっているかを把握します。 - 整骨(筋・靭帯・関節包)ケア
痛みのある段階では、鍼灸で血流を促進・痛みを和らげ、整骨で靭帯・筋肉・足関節のサポートを行います。テーピングやサポーターも併用可能です。 - 機能回復トレーニング・バランス指導
痛みが落ち着いてきたら、足関節・ふくらはぎ・足底・足指の筋力強化やバランス訓練を行い、「引きずらない=スムーズに歩ける脚」に変えていきます。 - 歩き方・靴・日常動作のアドバイス
歩行のクセ・立ち仕事の負荷・靴の形・段差対策など、日常生活レベルで無理なく改善できるポイントをお伝えします。 - 再発予防プログラム
捻挫を繰り返してしまう方や「いつもくるぶしが気になる」という方には、専門的な不安定症予防のプログラムもご提案可能です(リハビリ/バランストレーニング/インソール紹介など)。
痛みを改善して「引きずらない」脚に戻るためのチェック&セルフケアポイント

ご自身でも今日からできるケア・チェックポイントをご紹介します。特に「くるぶしが気になる」「引きずってしまう気がする」という方は、ぜひ目を通してみてください。
- 歩き出しや立ち上がり時に「くるぶしにズキッ」と出るか? → 出るなら荷重・歩き方に問題があるかも。
- 立って、片脚でバランスをとってみる(10秒以上)→ふらつき・ぐらつきある? → ある場合、足関節・足部筋・バランス能力の低下の可能性あり。
- 靴のかかと・内側・外側の摩耗をチェック → かかと外側だけ減っていたり、靴が偏っているなら歩き方に偏りが出ているかも。
- 階段・段差を昇る/降りる時にくるぶしが痛いか? → こうした動作は足関節に負荷がかかりやすいため、痛み出るなら要注意。
- ふくらはぎや足裏(足底)を定期的にストレッチ・マッサージする → 筋肉・足底筋の疲労をためずに、足関節への負担を和らげましょう。
- 捻挫したことがあるなら、 “捻ったからもう大丈夫” と放置せず、専門家に相談を → 再発リスク・不安定化の芽を早めにつぶすことが大切です。
- 長時間の立ち仕事・歩き仕事のあと、腫れ・重だるさ・くるぶしの違和感が続くか? → こうしたサインを放置すると、慢性化しやすくなります。
これらを日常的に気をつけていただくだけでも、「引きずって歩く」状態に至るリスクをかなり軽減できます。
最後に:大事なのは「早めの一歩」
くるぶしの痛み・引きずるような歩行というのは、「まだ軽いから大丈夫」「そのうち治るだろう」と思われがちですが、実は長引くほど脚の機能・他の関節・生活の質に影響を及ぼす可能性があります。先に紹介した統計でも、足関節付近の痛み・捻挫・不安定症が想像以上に多くの人に関わっているというデータが出ています。
「歩きづらいな」「くるぶしが気になるな」と思ったら、ぜひ早めに相談をしていただきたいです。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、歩き方のクセ・痛みの原因・機能回復・再発予防までトータルにサポートしています。
一緒に「引きずらずに歩ける」「安定して立てる」「日常生活・仕事・趣味を支える脚」を目指していきましょう。
参考リンク(統計データ)
- 「足・足首(foot & ankle)痛の有病率と関連因子 ― 日本の看護師を対象」 (日本語・本文あり)
→ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5886880/ PMC - 「大学生アスリートにおける慢性足関節不安定症(CAI)の有病率」 (日本スポーツ医学誌)
→ https://www.rinspo.jp/journal/2020/files/30-3/724-731.pdf 日本臨床スポーツ医学会 - 「足関節捻挫・急性足関節障害の疫学レビュー」 (英語)
→ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6602402/ PMC