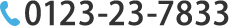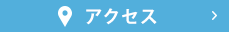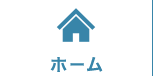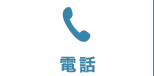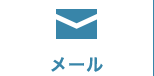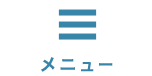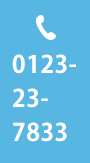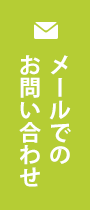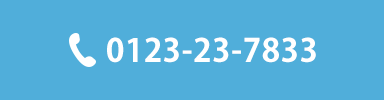はじめに
交通事故に遭われたあと、「むち打ち」「腰痛」「肩・首の痛み」などが良く話題になりますが、意外にも「股関節(もも/お尻/付け根あたり)の痛み」「脚を開きにくい」「あぐらがかけない」「車の乗り降りがつらい」といった症状を訴える方も少なくありません。
とくに衝突や追突、側面からの衝撃などで骨・軟部組織・関節に負荷がかかると、股関節周辺にダメージが残りやすく、動きが制限されることで日常生活にも支障が出ることがあります。
今回は、交通事故後の股関節の痛み・可動域制限(開きにくさ)が起こるメカニズム・放っておくと慢性化するリスク、そして青葉鍼灸整骨院としてご提案するアプローチをお伝えします。
なぜ交通事故で「股関節」が影響を受けるのか

まず、「なぜ股関節に痛み・動きの制限が起こるのか」を整理します。
- 交通事故による衝撃は、予想以上に身体の各部に負荷がかかります。特に脚・骨盤・股関節あたりは、車のダッシュボードや側面衝撃でぶつかったり、底面や床板に脚が押されることで損傷を受けたりすることがあります。 交通事故病院サーチ+2いしがみ整形外科クリニック+2
- 股関節は、太もも(大腿骨)と骨盤(寛骨)をつなぐ大きな関節で、歩く・立ち上がる・座る・脚を開く・あぐらをかくなど様々な動作に不可欠です。そのため、少しのズレ・筋肉の損傷・靭帯・軟骨の影響でも「動きにくさ」「痛み」が出やすい部位です。
- また、事故直後に症状が出ないことも珍しくありません。アドレナリン等で痛みに気づかなかったり、痛みが出るまで時間がかかったりするため、「脚が開きにくい」「股関節が動かしづらい」と感じたら、事故後すぐに専門家に相談することが重要です。 南九州市|アーク鍼灸整骨院+1
- さらに、股関節近くの筋肉・腱・靭帯・神経が損傷/拘縮を起こすと、可動域(脚を開く・引く・回す範囲)が制限され、動作に伴って痛み・違和感が残ることがあります。たとえば、あぐらをかこうとして「脚が外に開かない」「もも・お尻が突っ張る」という声も聞きます。 足立慶友整形外科+1
以上のように、交通事故の衝撃が直接または間接的に股関節周辺に影響をもたらし、結果として「脚を開きにくい」「股関節が痛む」という症状につながる可能性があるのです。
症状が残るとどうなるか/早期対応の重要性
脚を開きにくい・股関節が動かしづらいという状態を放っておくと、次のようなリスクがあります。
- 可動域制限が固定化:関節や筋肉・腱の硬さが進み、「開く・引く・回す」動作がさらに制限される。
- 筋力低下・アンバランス:動かしづらいためにその部位を使わなくなり、筋力が落ちることでさらに動きにくくなる。
- 二次的負担:股関節が十分に動かないと、その分腰・膝・足首など他の関節に負担がかかり、連鎖的に痛みが出る可能性があります。
- 慢性痛化・後遺症化:事故によるケガは、適切な治療・リハビリを行わないと痛み・機能制限が長引く傾向があります。たとえば、「慢性疼痛治療ガイドライン」には、事故・労災による痛みが長期化してしまう可能性が指摘されています。 厚生労働省+1
- 後遺障害の認定対象になるケースも:例として、事故で股関節脱臼を起こした場合、神経症状が残れば後遺障害等級(12級または14級)が認められる可能性があります。 交通事故病院サーチ
このように「脚を開きにくい」「股関節がしっかり動かない」というのは、単なる“違和感”のレベルにとどまらず、将来の歩行・日常動作・QOL(生活の質)に影響を及ぼす可能性があります。従って、事故後に股関節あたりに違和感・痛み・動きづらさを感じたら、できるだけ早く対処することが望まれます。
交通事故の現状に関する主な統計データ

事故をめぐる環境・統計を知ることは、ご自身の対応・治療選択を考える上での背景理解になります。以下に、参考となる3つの公的統計リンクを掲載します。
- 全国の交通事故統計情報のオープンデータ(警察庁)
→ 事故発生数・死傷者数・年次推移などが公開されています。 警察庁 - 「令和3年中の道路交通事故の状況」からの抜粋:令和3年中、発生件数30万5,196件、死者数2,636人、負傷者数36万2,131人。 内閣府ホームページ
- 「道路の交通に関する統計/交通事故死者数について」:令和6年(2024年)の全国死者数は2,663人で、前年から横ばいまたは微減。 ITARDA
上記のように、交通事故そのものがまだ日常的に起きており、「負傷・機能制限」「後遺症」のリスクも決して低いものではありません。股関節の痛み・可動域制限も、その中の一つの重要な症状として捉える必要があります。
青葉鍼灸整骨院のアプローチ:股関節の痛み・開きにくさに対して

千歳・北北海道エリアで事故後の股関節の痛み・可動域制限にお悩みの方に対し、青葉鍼灸整骨院では次のような流れ・対策をご案内しています。
1) 初期検査・問診
事故状況(追突・衝突・脚の圧迫など)/症状発生時期/動かしにくい方向(外に開く・内に閉じる・脚を振る)/日常で困っている動作(あぐら・車の乗降・階段・横方向の動き)などを丁寧に伺います。
レントゲン・MRI等の医療機関受診状況・診断有無も確認し、必要に応じて整形外科との連携も図ります。
2) 関節可動域評価・筋・靭帯・軟部組織チェック
股関節の開き具合(外転)・脚を引く・回す可動域を計測し、筋肉の緊張・腱の硬さ・靭帯の引きつり感・筋力低下などを確認します。
動作時の痛み・ズキッとする症状・動き出しの鈍さなども重要なサインです。
3) 整骨施術・徒手療法
- 股関節周囲のトリガーポイント/筋硬結/血流低下箇所に対し、筋・腱・靭帯・関節包へのアプローチを行います。
- 整骨・徒手療法:関節可動域改善を目的に、モビライゼーションやストレッチ、筋膜リリース的な操作を行い、脚を開く・引く動作を支えます。
- 筋力バランス療法:脚の外転・内転筋、臀部・大腿部筋群の筋力低下を補うため、段階的にトレーニング・体操指導を行います。
4) 可動域回復プログラム・日常動作指導
脚を開く・あぐらをかく・車の乗降・階段の昇降など、日常生活で負担を感じる動作にフォーカスし、可動域を少しずつ広げるための運動・ストレッチ・セルフケアを指導します。例えば、股関節を外に開く動作/内に閉じる動作のストレッチ、筋力維持のための臀部・大腿部エクササイズなど。
また、事故後の体の使い方が偏ると、体重移動・脚のバランスが崩れやすいため、「歩き方」「立ち姿勢」「座り方」などのアドバイスも行います。
5) 経過観察・機能改善の確認
一定期間ごとに可動域・痛みの変化をチェックし、「脚をどれくらい開けるようになったか/あぐらがかけるようになったか/痛みなく車に乗り降りできるか」など、日常動作の改善を一緒に確認していきます。経過によっては整形外科への紹介・専門検査を提案することもあります。
治療を受けるべきサイン・早めのご相談をおすすめする理由

股関節に関して、次のようなサインがある方は早めの相談をおすすめします。
- 「脚を開こうとしたとき、お尻・ももあたりに“突っ張り”“引きつり”を感じる」
- 「あぐらをかくと以前より脚が開かない/左右差がある」
- 「階段を下りるとき、脚を横に出すと“痛む”または“違和感”がある」
- 「車の乗り降りで片側の脚がスムーズに動かない/股関節が“ぎこちない”」
- 「事故後数週間経っても股関節まわりに痛み・動かしづらさが残っている」
これらがある場合、事故直後に“様子を見れば治るだろう”と放っておくと、先に述べたように筋拘縮・関節可動域制限・筋力低下・二次的な負担などのリスクが高まります。特に関節周囲の動きが停滞すると、回復が遅れたり、改善が難しくなったりするため、早期対応が鍵となります。
さらに、事故後の治療・リハビリを適切に受けているかどうかは、将来的な痛み・機能回復・後遺症の有無に大きく関わってきます。事故だから“仕方ない”とあきらめず、きちんと専門機関で評価・処置を受けることをぜひおすすめします。
おわりに
交通事故後に「股関節が痛む」「脚が開きにくい」「普段できていた動作(あぐら・乗車・車の降り方)が不自由になった」と感じたら、それは“ただの痛み”ではなく、身体が深くダメージを受けて“動かしづらさ”としてサインを出している可能性があります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、交通事故後の股関節まわりの痛み・可動域制限・機能低下に対して、丁寧にカウンセリング・検査・整骨・運動療法を組み合わせた対応を行っています。事故の痛み・違和感を放置せず、今後の歩行・日常動作・QOLを守るためにも、ぜひ早めにご相談ください。
本稿でご紹介した統計データ(上記リンク)を背景に、「交通事故はまだ身近で起こっており、本人のケアが重要である」という視点をぜひ持っていただければ幸いです。股関節まわりの違和感・痛みが、あなたの暮らしを少しずつ制限してしまう前に、一緒に回復を目指していきましょう。
参考リンク
- 交通事故統計情報のオープンデータ(警察庁)→ https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/opendata/index_opendata.html 警察庁
- 令和3年中の道路交通事故の状況→ https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html 内閣府ホームページ
- 令和6年(2024年)全国市区町村別交通事故死者数→ https://www.itarda.or.jp/contents/10875/info_W01.pdf ITARDA