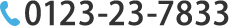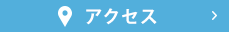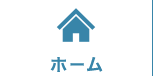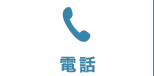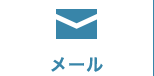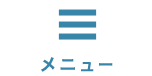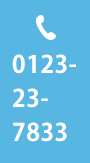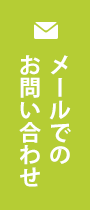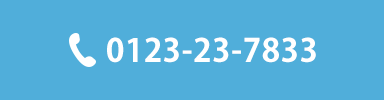球拾いで腰が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

部活で球拾いしていたら腰が痛くなった学生へ
~千歳市の青葉鍼灸整骨院からのアドバイス~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
部活の練習中、何気なく行っている「球拾い」。しゃがんで立って、走って拾って、またしゃがんで,,,この繰り返しの動作、実は腰にかなりの負担がかかっていることをご存知でしょうか?
「腰が痛いけど、練習を休むのは気が引ける」「試合が近いから、何とか我慢してやってしまう」そんな学生の声を、当院(千歳市の青葉鍼灸整骨院)でもよく耳にします。ですが、腰の痛みを我慢して続けると、思っている以上に長引いてしまうことが多いのです。
球拾いで腰が痛くなる原因とは?

球拾いの動作を分解すると、「中腰」「前かがみ」「ひねり」「立ち上がり」の連続です。これらの動きが繰り返されると、腰の筋肉・関節・骨盤まわりのバランスに負担が集中します。
特に原因になりやすいのは以下の3点です。
①中腰姿勢の維持
中腰は腰の筋肉(脊柱起立筋)を常に収縮させた状態です。特に、ハムストリングス(太ももの裏側の筋肉)が硬くなると、腰を曲げる動きが制限され、腰部に余計な緊張が走るようになります。
②前かがみでの拾う動作
腰を丸めると、背骨の「腰椎」が前方に押し出される形になります。この状態で何度もボールを拾うと、椎間板に強い圧力がかかり、腰椎椎間板ヘルニアのような状態を引き起こすことも。
③体をひねる動作
片手でボールを拾いながら体をひねると、腰椎の回旋ストレスが発生します。特に野球・テニス・バレーなどでは、拾ってすぐに投げ出す動作が入るため、腰椎・骨盤まわりの筋バランスが崩れやすいのです。
学生の腰痛は意外に多い!

文部科学省と日本体育協会の調査によると、中高生の約30%が「腰の痛み」を経験していると報告されています。(リンク)
また、整形外科学会の調査では、腰痛の原因の約7割が「筋肉や姿勢の問題」によるものとされており、骨や神経の病変によるものは少数です。(リンク)
さらに、スポーツ庁のデータでは、高校生アスリートのうち約25%が腰痛で練習を制限した経験があると発表されています。(リンク)
つまり、「若いから大丈夫」ということは決してありません。部活動で日常的に腰を酷使する学生ほど、早めのケアと予防が重要です。
整骨院での治療とアプローチ

当院(千歳市の青葉鍼灸整骨院)では、学生の腰痛に対して次のようなステップでアプローチします。
①原因の分析
まず、どの動作で痛みが出るのかを確認します。しゃがむ時、立ち上がる時、捻じる時など、動作の中でどこに負担が集中しているかを見極めます。これにより、「筋肉性の腰痛」か「関節由来」かを明確に出来ます。
②筋肉と関節のバランス調整
腰だけでなく、骨盤・股関節・太もも裏(ハムストリングス)・背中の柔軟性を整えることがポイントです。特に学生は成長期で筋肉の伸びが骨の成長に追い付かず、硬くなりやすい傾向があります。そのため、筋肉の緊張を緩め、骨盤の動きをスムーズにすることで、腰の負担を軽減します。
③再発予防トレーニング
治療と同じくらい大切なのが再発防止です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「体幹の安定」「股関節の可動域向上」「姿勢改善」を目的とした簡単なエクササイズを指導しています。
たとえば、
・お尻の筋肉(大殿筋)を活性化させるブリッジ運動
・ハムストリングスと腰の連動を整えるストレッチ
・骨盤を立てて支える腹横筋のトレーニング
など、これらを継続することで、腰への負担が軽くなり、部活中の動きもスムーズになります。
自宅でできるセルフケア

もし痛みが軽い段階であれば、次の方法を試してみましょう。
・入浴でしっかり温める:血流が良くなり、筋肉のこわばりが和らぎます。
・痛みが強い時は冷やす:炎症がある場合は、最初の48時間は冷やす方が有効です。
・ストレッチは無理せず少しずつ:前屈で痛みが強い時は、太ももの裏を軽く伸ばすだけでもOK。
ただし、「動くと痛みが強くなる」「朝起きると痛くて伸びない」などの場合は、自己判断せず整骨院へご相談ください。
放置するとどうなる?

最初は「軽い筋肉痛」でも、繰り返すことで次のような状態に進行することがあります。
・腰の慢性的な張り(筋筋膜性腰痛)
・椎間板ヘルニア
・分離症(特に成長期男子に多い)
一度この段階になると、数週間~数か月の安静やリハビリが必要になることも。早めに治療を始めることが、最短の回復への近道です。
最後に:痛みは「努力の証」ではなく、「体のSOS」
球拾いで腰が痛くなるのは、頑張っている証でもあります。しかしその「頑張り」が続けられるように、体のメンテナンスを習慣にすることが大切です。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、学生一人一人の体の状態や練習量に合わせた施術とセルフケア指導を行っています。「少し違和感がある」「最近腰が重い」と感じたら、早めにご相談ください。未来のパフォーマンスを守るためにも、今のケアが大切です。


掃除機をかけて腰痛 千歳青葉鍼灸整骨院

掃除機をかけていると腰が痛くなる方へー千歳市の青葉鍼灸整骨院
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「掃除機をかけていると腰が痛くなる」「終わった後腰が重だるい」と感じたことはありませんか?
実はこの”掃除中の腰痛”は、家事を行う多くの方が抱えている悩みの1つです。今回は、その原因と対策を、整骨院の視点からわかりやすくお伝えします。
掃除機をかける動作で腰が痛くなる理由

掃除機をかけるという行為は、一見軽い動作に思えますが、実は腰に大きな負担がかかります。以下の3つのポイントが腰痛を引き起こす原因になっています。
掃除機のノズルを前に伸ばすと、自然と上半身が前に倒れます。この「軽い前かがみ」姿勢が数分続くだけで、腰の筋肉(脊柱起立筋)に常に緊張が入り、血流が悪くなります。その結果、筋肉が硬くなり、痛みや張りを感じやすくなるのです。
掃除機を左右に動かす時、腰を中心にひねるように動かす人が多いです。しかし、本来は腰よりも「脚や骨盤」を使って動かすべきところ。腰を軸にひねる動きが続くと、椎間板や筋膜に負担が集中してしまいます。
腰を支えるための腹筋やお尻の筋肉(大殿筋)が上手く使えていないと、腰まわりの筋肉だけで体を支えることになります。その結果、腰が”孤軍奮闘”してしまい、痛みを感じやすくなります。
日常生活で発生する腰痛の実態(統計データ)

腰痛は、家事・育児・仕事を問わず、日本人にとって非常に身近な症状です。実際に、いくつかのデータからもその多さが分かります。
1.厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、自覚症状のうち男性で最も多いのが「腰痛」、女性では「肩こり」に次いで「腰痛」が2位です。(リンク)
2.労働災害の統計では、「4日以上の休業を伴う職業性疾病」のうち、約6割が腰痛によるものです。(リンク)
3.腰痛による生産性の低下も深刻で、腰痛を持つ人は持たない人に比べ、労働生産性が約12.9%低下するという試算もあります。(リンク)
これらの統計は、「腰痛が特別な人だけの問題ではなく、誰にでも起こりうる」ことを示しています。特に、家事や掃除のような”毎日の動作”で出る腰痛こそ、早めのケアが大切です。
掃除中の腰痛を防ぐ3つのポイント
では、実際に掃除機をかける時、どうすれば腰への負担を減らせるのでしょうか。整骨院でお伝えしている、効果的な3つのポイントをご紹介します。
掃除機を左右に動かす時、腰を捻るのではなく、脚を一歩ずつ動かして全身で移動するようにします。腰の回旋(ねじり)を減らすことで、筋肉や椎間板へのストレスを大幅に減らせます。また、掃除中は片足に体重が偏らないように注意しましょう。
掃除機のノズルをできるだけ長く伸ばし、上半身を起こしたまま動かすことがポイントです。膝を軽く曲げ、背筋を真っすぐに保つことで、腰の筋肉の過緊張を防げます。特に身長が高い方は、ノズルを短くし過ぎないことが大切です。
掃除を始める前に、腰や太もも裏(ハムストリングス)を軽く伸ばしておくと、血流が良くなり痛み予防になります。終わった後も腰をゆっくり反らす「腰伸ばしストレッチ」を取り入れましょう。整骨院で指導している簡単なストレッチは、1日1分でも効果的です。
千歳市の青葉鍼灸整骨院での腰痛ケアの流れ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「掃除や日常動作で痛む腰痛」に対して、次のような流れで施術を行っています。
1.姿勢・動作の確認
実際に掃除機をかける姿勢を再現してもらい、どこに負担がかかっているのかをチェックします。体の使い方のクセを把握することで、根本的な原因を見つけます。
2.筋肉・関節の調整
腰だけでなく、腹部・お尻・太ももなど、腰を支える筋肉を整えることで、体全体のバランスを改善します。筋膜リリースなど、痛みの出にくい施術を行います。
3.動作指導とセルフケア
掃除機をかける姿勢、物を持ち上げる時のコツ、家事の合間に出来るストレッチなどを丁寧にアドバイスします。ご自宅でも実践できる”再発予防のための習慣”をお伝えします。
千歳市内でも、冬場の除雪や氷割り、暖房による体の冷えで腰を痛める方が多く見られます。「腰が重い」「立ち上がる時に痛い」「掃除後に腰が張る」といった症状がある方は、放置せず、早めのケアをお勧めします。
まとめ:腰痛は”家事の姿勢”から変えられます
掃除機をかけて腰が痛くなるのは、「腰だけで作業をしている」ことが主な原因です。足やお腹、お尻の筋肉をバランスよく使えるようにすることで、腰の負担は大きく減らせます。
腰痛は放っておいても自然に良くなることは少なく、繰り返すことで慢性化してしまうこともあります。家事を頑張るあなたの体を守るためにも、日常の中での姿勢改善と定期的なケアを心掛けてみて下さい。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「掃除中・家事中の腰痛」に特化した施術と生活指導を行っています。「腰が痛くて掃除が辛い」「終わった後に腰が重くなる」という方は、是非一度ご相談ください。


蓋の開け方に注意! 千歳青葉鍼灸整骨院

指ばかり使ってペットボトルの蓋を開けていませんか?
ーー肘・手首を痛める前に知っておきたい整骨院からのアドバイスーー
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
ペットボトルの蓋や、調味料の瓶、ジャムの蓋など。「ちょっと開けるだけ」と思っていても、気づいたらなかなか開かない・手首が痛い・肘が張る・指がだるいと感じたことはありませんか?
特に女性は、力を入れづらい状態で指先ばかりで捻る動作を行う傾向があり、これが手首や肘の慢性的な痛みにつながることがあります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「手首を回すとピキッと痛む」「肘が重くて家事が辛い」という方が少なくありません。
今回は、そんな「ふたを開ける時に手首・肘が痛くなる原因」と「整骨院での施術・セルフケア」について詳しくお話しします。
なぜ”ふたを開けるだけ”で痛くなるのか?

指・手首・肘が連動して捻じる動作をしている
ペットボトルや瓶の蓋を開ける動作では、
1.握る(グリップ力)
2.回す(ねじるトルク)
3.支える(肘・肩の安定)
という複数の動きが同時に起こります。
一見小さな動作ですが、研究では、密閉された瓶の蓋を開ける際、手首と前腕には非常に大きな力がかかることが報告されています。(リンク)
つまり、「ふたを開けるだけ」でも、実際には手首・肘・指に高い負荷が加わっているのです。
指ばかりで開ける癖が”肘・手首の障害”に
特に女性は、力の入れ方が「指中心」になりやすい傾向があります。手のひらではなく指先で蓋をつかみ、手首を捻って開けようとすることで、前腕の筋肉・腱・関節包に強いストレスが集中します。
この使い方が続くと、
・手首の腱鞘炎
・肘の外側上顆炎(テニス肘)
・前腕の筋膜炎・神経痛
などの慢性障害に発展することがあります。米国の研究では、繰り返し動作による手首・肘の障害は女性に多いと報告されています。(リンク)
また、瓶の蓋を開ける実験では「女性の多くが手首の許容トルクを超えて力を使っている」とのデータもあります。(リンク)
つまり、”日常のちょっとした動作”が、手首・肘にとっては実は過酷な負担になっているのです。
こんな症状が出ていませんか?

・ふたを開ける時手首がピキッとする
・開けた後手首・肘がだるい
・指をひねる動作でズキッと痛む
・肘の外側が張って重い
・最近、力が入りにくい・疲れやすい
・手首を動かすたびに「抜けそう」「違和感」がある
これらは、手首や肘の筋肉・腱が限界を迎えているサインかもしれません。放置すると慢性化して、ペットボトルの蓋を開けるだけで強い痛みが出るようになる方もいます。
整骨院での施術アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、手首や肘の痛みを「局所だけでなく、動作全体」から見直していきます。
①問診・動作チェック
・どんな動作で痛みが出るか
・どの指・どの方向に負担がかかっているか
・肩・体幹の連動性があるか
を丁寧に確認します。
②筋・関節・腱の調整
・前腕から手首にかけての筋肉を手技で緩め、血流を改善
・手首や肘関節の可動域を広げ、負担を分散
・炎症部位の安定をサポートするためのテーピング・サポーター指導
③再発予防の動作指導
・指先だけでなく「肩・体幹を使う」開け方を指導
・家事・仕事・パソコンなどの手首への負担軽減法を提案
・日常でできる簡単なストレッチ・トレーニングをお伝えします
千歳市の青葉鍼灸整骨院での治療は「痛みを取るだけ」ではなく、「負担のかからない使い方」を身につけることがゴールです。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
自宅でできる手首・肘ケア
以下のセルフケアををとり入れるだけでも、手首や肘の疲れを軽減できます。
手首ストレッチ
手のひらを下にして腕を前に伸ばし、反対の手で指先を手前に引く。次に手のひらを上にして同じように引く。それぞれ20~30秒キープを2セット。
前腕マッサージ
机の角などに前腕を乗せ、肘の近くから手首まで優しくさすり、硬い部分をゆるめます。
握り方の工夫
・指だけでなく、手のひら全体で包むように持つ
・手首を真っすぐ保ち、肘を軽く曲げる
・肩の力を抜いて、体全体で回すイメージで行う
また、すべり止めマットや蓋オープナーを使うのも立派な予防策です。
整骨院からのメッセージ
「たかがふたを開けるだけ,,,」と思う方も多いですが、実際にはその小さな動作の積み重ねが手首・肘に大きな影響を与えます。慢性的な腱鞘炎や肘の炎症を抱えている方の中には、「最初はペットボトルの蓋を開ける時だけ痛かった」というケースも少なくありません。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋・関節の調整と使い方の改善の両面から、手首・肘のトラブルを根本からサポートします。もし手首や肘に違和感を感じたら、無理せず早めにご相談ください。あなたの”日常の使い方”から改善することで、痛みのない生活を取り戻すことができます。


営業職のストレス 千歳青葉鍼灸整骨院

営業職のあなたへー人間関係のストレスが体に与える影響と整骨院でできるケア
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
営業の仕事は、成果だけでなく「人との関係づくり」が求められる職種です。お客様とのやり取り、社内での調整、上司からのプレッシャーなど、日々の業務の中で、人間関係によるストレスを感じる方は少なくありません。
そんな心身の不調を感じていませんか?今回は、営業職に多い”人間関係ストレス”が体に与える影響と、整骨院でのケア方法について詳しくお伝えします。
営業職は「人間関係ストレス」を抱えやすい職種
厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査」によると、仕事で強いストレスを感じる人のうち、54.4%が「職場の人間関係」を主な原因と回答しています。(リンク)
営業職は、社外・社内の両方でコミュニケーションが欠かせません。常に”相手の反応”を気にして動く必要があるため、精神的な疲労が溜まりやすいのです。
さらに、数字のノルマや成果へのプレッシャーも加わることで、体が常に緊張状態になり、自律神経が乱れやすくなるのが特徴です。
ストレスが体に与える影響とは?

ストレスを感じると、自律神経のうち「交感神経」が優位になります。交感神経は”戦う・頑張る”ときに働く神経で、体を緊張状態に保つ役割があります。
この状態が続くと、次のような体の不調が現れます。
・肩こり・首の凝りが慢性化する
・背中が張って呼吸が浅くなる
・頭痛や眼精疲労が出る
・胃が重く、食欲が落ちる
・朝起きても疲れが抜けない
営業職では「常に気を張っている」「断られることが多い」「移動が多く休めない」といった要素が重なり、心の緊張が体の不調につながりやすいのです。
ストレスによる「体の凝り」の正体

千歳市の青葉鍼灸整骨院に来院される営業職の方の多くが訴えるのは、「肩から首にかけての張り」「腰の重だるさ」「背中の疲労感」です。
これらは、単なる筋肉疲労ではなく、ストレスによって交感神経が過剰に働き、筋肉が硬直している状態です。
例えば、緊張すると自然に肩が上がりますよね。この状態が長く続くと、筋肉が硬くなり、血流が悪化。疲労物質が溜まって、痛みやだるさが生じます。
データで見るストレスと体の関係

実際に、ストレスが身体症状と深く関係していることは複数の研究で明らかになっています。
1.独立行政法人 労働者健康安全機構の調査
心理的ストレスを抱える労働者の約7割が肩こり・頭痛・腰痛などの身体症状を同時に訴えている。(リンク)
2.日本産業衛生学会の研究
人間関係ストレスが高い群では、自律神経の乱れ・睡眠障害・胃腸不調の発生率が有意に高いと報告。(リンク)
営業という職業は、これらの条件が重なりやすいため、「心のストレス→自律神経の乱れ→体の不調」という悪循環が起こりやすいのです。
整骨院でできるストレス由来のカラダケア

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、単に”痛みを取る”だけでなく、ストレスでこわばった体をゆるめ、自律神経のバランスを整えることを目的としています。
①筋肉の緊張をゆるめて血流改善
首・肩・背中の筋肉を中心に、優しくほぐすことにより、副交感神経(リラックスの神経)が働きやすくなり、心身が落ち着きます。
②背骨・骨盤の調整で自律神経を整える
自律神経は背骨を通って全身に分布しています。姿勢の歪みを整えることで、神経の流れがスムーズになり、「なんとなく体が軽くなった」と感じる方が多いです。
③呼吸改善アプローチ
ストレスによって浅くなった呼吸を深めるために、肋骨や横隔膜周りを緩める施術を行います。深い呼吸はリラックスに直結します。
営業職におすすめのセルフケア
日々のストレスを少しでも軽減するために、整骨院の施術と併せて次のケアを取り入れてみましょう。
1.1時間に1回、肩甲骨を動かす
デスクワークや車移動中は肩が固まりやすいので、肩を後ろに回す・胸を張るなどの軽い動作を。
2.深呼吸を意識する
「吸う」よりも「ゆっくり吐く」ことを意識すると、副交感神経が働きやすくなります。
3.湯船に浸かる習慣を
40度前後のお風呂に10分入るだけでも、体の緊張を和らげ、睡眠の質が上がります。
4.休日は”人に合わせない時間”を作る
営業職は常に人に合わせているため、自分のペースで過ごす時間が心の回復につながります。
整骨院は「心と体を整える場所」

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みを取るだけでなく、体の緊張を緩めることで、ストレスによる不調を和らげる場所でもあります。
営業職の方は、「頑張りすぎ」「我慢しすぎ」になりやすく、知らないうちに体が限界を超えているケースも少なくありません。施術を通して血流や呼吸を整えることで、自然と心も落ち着き、仕事への集中力や前向きな気持ちを取り戻すことができます。
まとめ
営業職の人間関係ストレスは、体にも大きな影響を与えます。肩こりや頭痛、腰の重だるさは、単なる疲れではなく、心と体が「緊張し続けている」サインかもしれません。
「最近、疲れが抜けにくい」「心身のバランスが崩れている気がする」そんな時は、ぜひ千歳市の青葉鍼灸整骨院にご相談ください。心と体の両面から、あなたの”営業力”を支えるケアを行います。


歩くと股関節が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

長く歩くと股関節が痛くなる人へー整骨院からのアドバイス
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「長く歩くと股関節が痛くなる」「歩き続けているとお尻の横や前側が重くなる」ーーそんな経験はありませんか?
歩くことは健康にいい反面、股関節には想像以上の負担がかかっています。特に最近では、通勤・立ち仕事・買い物などで1日当たりの歩行距離が増え、股関節の痛みを訴える方が増加傾向にあります。今回は、なぜ長く歩くと股関節に痛みが出るのか、その原因と整骨院での対処法、自宅でできるケア方法を詳しく解説します。
なぜ長く歩くと股関節が痛くなるのか?

股関節は「体重を支える」「足を前に出す」「体を安定させる」という3つの重要な働きを同時に行っています。そのため、歩行時には体重の約3倍の負荷が股関節にかかるといわれています。(リンク)
長時間の歩行は、この負荷が何千回と繰り返されるため、股関節周辺の筋肉や靭帯、関節包に疲労が溜まり、痛みや違和感につながります。
さらに、次のような要因が加わると痛みが出やすくなります。
骨盤の傾き、反り腰、猫背などがあると、歩く時に股関節の動きが偏り、一方の足に過度な負担がかかります。特に女性では骨盤が広く、筋力バランスの影響を受けやすい傾向にあります。
股関節を支える筋肉(臀部・腸腰筋・太もも前後の筋肉)が硬くなったり、弱くなったりすると、関節の動きがスムーズに行えなくなります。その結果、股関節に「ねじれ」や「圧縮力」が加わり、痛みの原因になります。
「歩くと痛い」という人の中には、変形性股関節症の初期段階である場合もあります。成人の約10%に股関節痛を抱えているという報告もあります。(リンク)
放置して歩行制限が強まると、将来的に人工関節が必要になるケースもあるため、早めのケアが重要です。
歩く時に出やすい股関節痛の特徴

長く歩くと痛みが出る人には、以下のような共通点があります。
・歩き始めて10分ほどで股関節の前や外側に痛み・重だるさを感じる
・坂道や階段で特に痛みが強くなる
・歩いているとだんだん歩幅が狭くなる
・座った後に立ち上がると、股関節が突っ張る・引っかかる感覚がある
・片足立ちになると不安定で、股関節が抜けそうな感覚がある
こうした症状がある場合、単なる「歩きすぎ」ではなく、体の使い方や関節のバランスに問題があることが多いです。
整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、股関節の痛みを単に”筋肉痛”と捉えるのではなく、全身のバランスや動き方を重視して施術を行います。
①問診・動作分析
どの動作で痛むのか、どのくらい歩くと痛みが出るのかを丁寧に聞きとります。さらに、骨盤や腰の傾き、足の長さ、歩行時の重心移動などをチェックして、股関節への負担ポイントを特定します。
②筋肉・関節の調整
・硬くなった股関節まわり(お尻・太もも前後、腸腰筋など)を手技で緩め、血流を改善
・股関節の可動域を広げ、関節への圧迫を軽減する
・歩行時のバランスを整えるため、体幹・臀部の筋肉を安定化させる施術を実施
③再発予防のアドバイス
歩く前後のストレッチや、正しい姿勢・歩行動作の指導も欠かせません。「どんな靴を履くか」「坂道の歩き方」「休憩の取り方」など、日常生活で実践しやすい方法をお伝えします。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
自宅でできるセルフケア

股関節痛を予防・軽減するためには、日常のケアがとても大切です。整骨院では次のような方法をおすすめしています。
・仰向けになり、片膝を胸に引き寄せて10秒キープ
・椅子に座り、片足を反対の膝に乗せて軽く前に倒れる(お尻の筋肉を伸ばす)
・立った状態で足を後ろに引き、お腹を前に出すようにして腸腰筋を伸ばす
入浴や温熱パッドで股関節を温めることで、筋肉や関節の柔軟性を高め、痛みを和らげます。
歩幅を少し広めにとり、踵からつま先に重心を移すイメージで歩くと、股関節への衝撃を分散できます。
統計でみる股関節痛の現状
1.成人の約10%が股関節痛を経験(リンク)
2.50歳以上の約9.7%が慢性的な股関節痛を訴える(リンク)
3.股関節痛を持つ人は、健常者よりも股関節の伸展動作が有意に少ない(リンク)
これらの統計からもわかるように、「歩くと股関節が痛む」症状は決して珍しくありません。多くの方が気づかないうちに、股関節へ過剰な負担をかけているのです。
まとめ
長時間歩いて股関節が痛くなるのは、体からのSOSサインです。痛みを我慢し続けると、関節や筋肉に負担が蓄積し、日常生活の動作にまで影響が出てしまいます。
大切なのは、「痛くなってから対処する」ではなく、「痛くならない体を作る」という考え方。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、関節・筋肉・姿勢・動作を総合的に整えながら、再発しにくい体づくりをサポートします。
「最近歩くと股関節が重くなる」「疲れが取れにくい」と感じている方は、是非一度ご相談ください。早めのケアで、再び気持ち良く歩ける体を取り戻しましょう。


ストレスでの体の影響千歳青葉鍼灸整骨院

人間関係のストレスで体が辛いー整骨院が教える「心と体の関係」
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
仕事をしていると、避けて通れないのが「人間関係」です。上司や同僚、部下との関係、取引先とのやり取りーー。相手に気を遣うことが多いと、知らないうちに体にも負担がかかっていませんか?
「最近、肩こりがひどい」「頭痛や腰痛が続く」「朝から体がだるい」
そんな症状の背景に、人間関係によるストレスが潜んでいることは少なくありません。今回は、整骨院の立場から「ストレスが体に与える影響」と「整骨院でできるケア」について解説します。
職場ストレスの約半数が”人間関係”

まず、データを見てみましょう。
厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事で強いストレスを感じる人のうち、54.4%が「職場の人間関係」を主な原因として挙げています。(リンク)
つまり、2人に1人が「人間関係ストレス」を抱えているということです。このストレスは、単なる気分の問題ではなく、自律神経のバランスを崩し、体の不調を引き起こす要因になります。
ストレスが体に影響するメカニズム

人間関係のストレスを感じると、脳は「危険」と判断し、自律神経のうち交感神経(緊張・興奮の神経)が優位になります。
交感神経が優位になると、体は”戦うモード”に入り、次のような反応を起こします。
・筋肉がこわばる
・血管が収縮し、血流が悪くなる
・呼吸が浅くなる
・胃腸の働きが低下する
・睡眠の質が悪くなる
本来、リラックス時には副交感神経(休息の神経)が働き、体を回復させます。しかし、ストレスが続くとこのバランスが崩れ、体が常に緊張した状態に。結果として、肩こり・頭痛・腰痛・めまい・不眠などの症状が出やすくなります。
心の疲れが「肩こり」「腰痛」に出る理由
千歳市の青葉鍼灸整骨院に来られる方の中にも、「マッサージをしてもすぐに戻ってしまう」「原因がわからないのに体が重い」という方が多くいます。
このようなケースでは、筋肉のこわばりの根底に”心のストレス”があることがよくあります。
ストレスで交感神経が過剰に働くと、体は常に緊張状態になります。特に影響を受けやすいのが「首・肩・背中・腰」です。筋肉がギュっと縮まり、血流が悪化し、疲労物質が溜まりやすくなります。
結果として、以下のような症状が出てきます。
・肩こりがひどくなる
・首の付け根が重く、頭痛がする
・腰が重く、長時間座るのが辛い
・朝起きたときに体がこわばっている
これらの症状は、単なる姿勢や運動不足ではなく、自律神経の乱れが原因のことも多いのです。
ストレスが招く身体症状の実態

独立行政法人 労働者健康安全機構の研究によると、心理的ストレスを抱える労働者の約7割が、肩こり・頭痛・腰痛などの身体症状を同時に訴えていると報告されています。(リンク)
さらに、日本産業衛生学会の報告では、人間関係によるストレスが強いほど、自律神経の乱れ、睡眠障害、胃腸の不調などが起こりやすいとされています。(リンク)
このように、ストレスは「心」だけでなく「体」にも明確な反応を起こすのです。
整骨院でできるストレス由来のカラダケア

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、単に痛い部分をほぐすだけでなく、自律神経のバランスを整え、ストレスでこわばった体をゆるめることを目的としたケアを行います。
①筋肉・筋膜の緊張を解く
ストレスでこわばりやすい首・肩・背中を中心に、優しい手技で筋肉を緩めます。血流を促すことで、副交感神経が優位になり、自然にリラックスできる状態を作ります。
②呼吸と姿勢の調整
ストレスによって浅くなった呼吸を整えるために、胸郭(肋骨周り)や横隔膜の動きを改善します。姿勢が整うと、呼吸が深くなり、緊張がほどけていきます。
③自律神経へのアプローチ
背骨や骨盤周りを調整し、自律神経の通り道を整えることで、体の内側から回復力を高めます。整骨院での施術は「体を通じて心を緩める」サポートにもなります。
日常でできるストレス緩和法

整骨院の施術に加えて、日常でできるケアもとても大切です。次の3つを意識してみましょう。
1.深呼吸を意識する
1日3回でもいいので、ゆっくりと息を吐く練習をしましょう。副交感神経が働き、体がリラックスします。
2.体を動かす習慣を作る
軽いストレッチや散歩は、血流を良くし、ストレスホルモンを減らします。
3.人に話す・共有する
悩みを抱え込まず、信頼できる人に話すことで心が軽くなります。
整骨院ができるサポート
ストレスによる体の不調は、放っておくと慢性化し、「どこに行っても良くならない」と感じる方も多くいます。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉・関節の調整だけでなく、「体の緊張を取って自律神経を整える」ことを目指したアプローチを行います。
人間関係でのストレスが強い時期こそ、体を整えることで心を守ることが大切です。
まとめ
人間関係のストレスは、見えない形で体に影響を与えます。肩こりや腰痛、頭痛、疲労感ーー。それは、体が「もう限界です」というサインかもしれません。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉や姿勢の調整を通して、ストレスで乱れた自律神経を落ち着かせるサポートができます。
「最近ずっと体が重い」「休んでも疲れが取れない」そんな時は、無理せずご相談ください。体を整えることが、心を整える第一歩になります。


なぜ太もも裏が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

きっかけもないのに太ももの裏が痛いあなたへーー神経痛やヘルニアの可能性も?
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「特に運動していないのに、太ももの裏が痛い」「ストレッチしてもなかなか良くならない」「腰も少し重い気がする」
このような”きっかけのない太ももの裏の痛み”に悩む方は、意外と多くいらっしゃいます。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、こうした症状を訴える患者さんの中に「坐骨神経痛」や「椎間板ヘルニア」が隠れているケースを良くみかけます。
今回の記事では、太ももの裏が痛くなる原因、ヘルニアや神経痛との関係、そして整骨院でできる対策をわかりやすく解説します。
なぜ「きっかけがないのに太ももの裏が痛いのか?

太ももの裏の筋肉(ハムストリングス)は、歩行・立ち上がり・階段動作など日常生活のあらゆる動きで使われています。この部位に痛みが出ると、多くの人は「筋肉痛」や「肉離れ」を疑いますが、明確なきっかけがない場合は筋肉以外の原因を考える必要があります。
主な原因としては、以下の3つが挙げられます。
①坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)
腰から出て、太もも~ふくらはぎ~足先まで伸びる「坐骨神経」が、どこかで圧迫・刺激されることで痛みやしびれが出る状態です。
特徴的な症状は
・太ももの裏がズーンと重だるい
・痛みがふくらはぎや足先まで広がる
・長く座っていると悪化する
・立ち上がる瞬間に痛む
坐骨神経痛は、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、腰部のトラブルによって引き起こされることが多いです。
②腰椎椎間板ヘルニアによる神経痛
「椎間板ヘルニア」とは、腰の骨と骨の間にある”クッション”のような組織(椎間板)が飛び出し、神経を圧迫して痛みや痺れを起こす状態です。
特に、第4~第5腰椎や第5腰椎~仙骨の間で起こると、坐骨神経を圧迫し、太ももの裏やふくらはぎに神経症状が現れます。
・腰の痛みと一緒に太ももの裏がしびれる
・前かがみ姿勢で痛みが強くなる
・くしゃみや咳で腰から足に電気が走る
こうした症状があれば、整骨院だけでなく整形外科での画像検査(MRI)も視野に入れましょう。(リンク)
③筋・筋膜性のトラブル(ハムストリングスの硬さ)
神経ではなく、筋肉そのものの「張り」や「こわばり」によって痛みが出るケースもあります。特にデスクワークが多い方や、長時間座りっぱなしの生活をしている方は、骨盤の後傾+ハムストリングスの過緊張が原因で、血流不足・筋膜の癒着による痛みが起きることがあります。
この場合は、ストレッチや筋膜リリースで改善するケースも多いです。ただし、神経由来か筋肉由来かを見極めることが重要です。
「神経痛」が関係しているかどうかのチェックポイント

以下のようなサインがある場合は、神経痛(坐骨神経痛やヘルニア)が関与している可能性が高いです。
・片側だけ太ももの裏が痛い
・しびれ・ビリビリ感がある
・足に力が入りにくい
・腰を曲げたり反らしたりで痛みが変わる
・お尻の奥に痛みがある
これらに当てはまる場合、筋肉ではなく神経の圧迫や炎症を疑いましょう。(リンク)
ヘルニアや神経痛による太もも裏の痛みーー統計からみる実態

太もも裏の痛みの多くは、「腰椎由来の神経症状」であることが分かっています。以下の統計データをご覧ください。
1.日本整形外科学会の調査では、腰痛患者のうち約35%が神経圧迫を伴う「坐骨神経痛」タイプであると報告。(リンク)
2.厚生労働省「国民生活基礎調査」では、腰痛は自覚症状の第1位で、特に40代以降の有訴率が高いとされています。(リンク)
3.日本腰痛学会の研究報告によると、腰椎椎間板ヘルニア患者の約70%が太もも裏~下肢にかけての放散痛を訴えています。(リンク)
これらのデータからも、太ももの裏の痛みは「筋肉の問題」と思い込みやすい一方で、実際には腰椎や神経が関係しているケースが少なくないことがわかります。
整骨院での施術・アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、まず痛みの出る動作や姿勢を確認し、筋肉・関節・神経のどこに原因があるかを丁寧に見極めます。
主な施術内容
1.筋緊張の緩和・血流改善
手技療法や電気治療を用いて、ハムストリングス・殿筋・腰部の筋肉をゆるめます。
2.ストレッチ・体幹トレーニング
坐骨神経の通り道を確保し、再発しにくい体づくりを行います。
3.日常生活のアドバイス
長時間座位の姿勢改善や、簡単なセルフストレッチ指導も行います。
自分でできるセルフケア
1.長時間座りっぱなしを避ける
1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かすようにしましょう。
2.太もも裏のストレッチ
椅子に座り、片足を伸ばしてつま先を引き上げるだけでもOK。無理のない範囲で20~30秒キープ。
3.腰を温める
冷えは血流を悪化させ、神経痛を強めることがあります。温熱パッドや入浴で腰を温めましょう。
まとめ
・明確なきっかけがない太もも裏の痛みは、神経が関係している可能性が高い
・坐骨神経痛や椎間板ヘルニアでは、太もも裏~足まで痛みやしびれが出る
・整骨院では、筋肉・骨盤・神経の状態を総合的にチェックし、根本改善を目指す
「ストレッチしても治らない」「痛みが長引く」という方は、筋肉ではなく神経のサインかもしれません。放置せず、早めにご相談ください。


仕事で肘を痛めた 千歳青葉鍼灸整骨院

「仕事で重いものを運ぶと肘が痛い」整骨院が教える原因と対策
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
日常的に重いものを持ち運ぶ仕事をしている方で、「最近、肘の外側や内側がズキッと痛む」「ものを持つたびに腕が重い」などの症状に悩んでいませんか?それは単なる”筋肉痛”ではなく、肘の腱や筋肉の使い過ぎによる炎症(いわゆる「テニス肘」「ゴルフ肘」など)かもしれません。
今回は、仕事で重い荷物を扱う方に多い肘の痛みの原因と整骨院での対処法、そして日常でできる予防法を詳しく解説します。
肘の痛みの原因は「使い過ぎ」と「使い方のクセ」
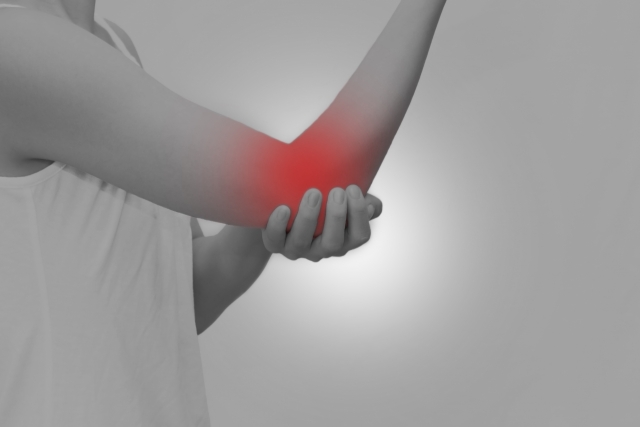
肘の関節自体は比較的丈夫な構造をしていますが、重いものを「繰り返し」「不自然な角度」で持ち上げたり、手首を捻る動作を頻繁に行うことで、前腕の筋肉が硬くなり、肘の腱付着部に炎症が起きることがあります。
この状態がいわゆる「上腕骨外側上顆炎(テニス肘)」や「内側上果炎(ゴルフ肘)」と呼ばれるものです。職業的には、以下のような人に多く見られます。
・建設・運送業など、重量物を扱う仕事
・調理師・介護職、看護師など、手を酷使する仕事
・デスクワークや工具作業で手首を捻る動作が多い人
肘の腱は、筋肉と骨をつなぐ「ロープ」のような役割をしており、そこに繰り返し負担がかかると、微細な損傷が蓄積して痛みに繋がります。
どんな症状が出るのか?
肘の外側が痛む場合は「外側上顆炎(テニス肘)」、内側が痛む場合は「内側上果炎(ゴルフ肘)」の可能性が高いです。特徴的な症状としては以下が挙げられます。
・ペットボトルの蓋をひねると痛い
・タオルを絞ると痛む
・荷物を持ち上げると肘の外側(または内側)がズキッとする
・手首を反らす・曲げる動作で痛みが強くなる
・安静時は痛くないが、仕事で使うと再び痛む
放置していると、炎症が慢性化して筋肉が常に緊張し、肩や手首の痛み、さらには握力の低下まで引き起こすこともあります。
関連する統計データ

肘の障害はスポーツだけでなく、労働現場でも多く報告されています。以下の統計からも、仕事による上肢障害の多さがわかります。
1.厚生労働省「職業性疾病の動向」
・上肢障害(肩・肘・手首など)の発生件数は、全職業性疾患の中で約30%を占める。(リンク)
2.日本整形外科学会:上腕骨外側上顆炎の有病率
・一般人口の1~3%程度が発症しており、特に40~50代の労働者層に多い。(リンク)
3.独立行政法人労働者健康安全機構:作業関連性上肢障害に関する報告
・「荷重運搬作業」「繰り返し動作」「姿勢の固定」が上肢障害の主因とされている。(リンク)
これらのデータからも、肘の痛みは「職業性負担」と密接に関係していることがわかります。
整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、肘の痛みを根本から改善するために、次のような施術を行います。
①炎症の鎮静と筋緊張の緩和
まずは患部に負担をかけないようにしながら、前腕~肘周辺の筋緊張を緩めます。手技療法(指圧やストレッチ)で血流を改善し、自然治癒力を高めることを目的とします。
②使い方のクセを修正
肘に負担がかかる背景には、「姿勢」「体の使い方」「肩や背中の動きの悪さ」が関係しています。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、肩甲骨や体幹の動きを整えて、肘だけに負担が集中しない体の使い方を指導します。
③サポート・テーピング療法
仕事を完全に休めない方には、テーピングやサポーターで肘の負担を軽減します。必要に応じて、肘関節の角度を保つテープ固定を行い、動作時の痛みを和らげます。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
自分でできる予防とセルフケア
痛みを再発させないためには、日常での意識も大切です。
1.荷物を持つときは肘を伸ばさず、体に近づける→肘への負担を分散できます。
2.作業の合間に手首・前腕のストレッチを行う→筋肉の硬さを防ぎます。
3.握力を鍛えるよりも、リラックスして使う意識を→力を抜くくせが痛みの予防につながります。
特に、肘の痛みは「使い方のクセ」が大きく影響するため、正しい姿勢と身体の連動を学ぶことが重要です。
放っておくとどうなる?
「少し痛いけど我慢できる」と放置していると、腱の炎症が慢性化し、腱が変性して治りにくくなることがあります。さらに、手首や肩の動きにも悪影響を与え、腕全体のだるさやしびれが広がることも。
早期に整骨院でのケアを始めることで、回復までの期間を短くし、再発を防ぐことが可能です。
まとめ
重い荷物を扱う仕事での肘の痛みは、単なる「疲労」ではなく、腱や筋肉の損傷が進行しているサインです。放置すると長引くことが多いのですが、適切な治療と使い方の見直しで改善は十分に可能です。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みを取るだけでなく、「どうすれば同じ痛みを繰り返さないか」までサポートします。肘の痛みを我慢せず、早めにご相談ください。仕事を続けながらでも、しっかり回復できる方法があります。


腰の重だるさの原因 千歳青葉鍼灸整骨院

片側の腰からお尻が重くなる人へー原因と整骨院での対処法
片側の腰~お尻が重い,,,それ、放置しないで!
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「なんとなく右(または左)側の腰からお尻にかけて重だるい」「痛いというよりも鈍く重い感じが続く」といった訴えは、整骨院でも非常に多く見られる症状の1つです。最初は「少し疲れているのかな?」と感じる程度でも、放っておくと坐骨神経痛や腰椎由来の痛み、骨盤の歪みなど、より深刻な問題へ発展することがあります。
今回は、片側の腰からお尻が重くなる原因と、整骨院での治療・セルフケアについて詳しく解説します。
1.なぜ片側だけ腰やお尻が重くなるのか?

片側の腰~お尻の重だるさには、主に以下のような原因が考えられます。
①骨盤・腰椎のバランスの崩れ
長時間のデスクワークや立ち仕事、片足に体重をかける立ち方などが続くと、骨盤が左右非対称に歪みやすくなります。この歪みが腰椎(腰の骨)や仙腸関節にストレスを与え、片側の腰やお尻の筋肉に過剰な負担をかけて「重い」「だるい」といった感覚を生み出します。
②中殿筋・梨状筋などの筋緊張
お尻の筋肉の中でも、中殿筋・小殿筋・梨状筋は骨盤を支える重要な筋肉です。特に梨状筋が硬くなると、そのすぐ下を走る坐骨神経を圧迫し、神経性のだるさやしびれが生じることもあります。
「重いけどビリビリする感じもある」という人は、このパターンの可能性が高いです。
③腰椎の神経圧迫(腰椎椎間板ヘルニアなど)
腰椎の椎間板が後方へ飛び出し、神経を圧迫すると、腰からお尻、太もも裏にかけて重さや痛みが出ます。特に「片側だけ」症状が出るのが特徴で、長時間座っていると悪化する傾向があります。この場合は、整骨院での徒手検査や整形外科での画像診断が有効です。
④血流やリンパの滞り
運動不足や冷え、長時間の同一姿勢によって血流が悪くなると、筋肉に疲労物質が溜まり「重だるい」感覚になります。この場合、温める・動かす・姿勢を変えることで一時的に軽減するのが特徴です。
2.放置するとどうなる?

片側の腰やお尻の重さをそのままにしておくと、以下のような悪循環に陥ります。
・筋肉のアンバランスがさらに強まり、骨盤がゆがむ
・神経の圧迫が進み、しびれ・痛みを伴うようになる
・歩き方や姿勢が偏り、反対側にも負担が出る
結果的に、腰痛・坐骨神経痛・慢性疲労といった状態に発展することもあります。早めに整骨院で原因を特定し、適切なケアを行うことが大切です。
3.整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、症状の原因を探るために姿勢・骨盤・筋肉・関節の動きを細かくチェックします。主な施術内容は以下の通りです。
〇筋肉の調整(手技療法)
中殿筋・梨状筋・腰方形筋など、硬くなった筋肉を丁寧に緩めて血流を促進します。
〇神経症状へのアプローチ
坐骨神経や腰椎周囲の神経圧迫がある場合は、手技に加えて電気療法や温熱療法を行い、炎症や緊張を和らげます。
〇姿勢・動作指導
普段の姿勢や座り方、立ち方、寝方のクセを見直すことも大切です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、日常での姿勢改善やストレッチ方法も指導します。
4.自宅でできるセルフケア

①温める
お尻や腰を温めることで、血流を改善し筋肉の緊張を緩和します。入浴やホットパックを活用するのがおすすめです。
②ストレッチ
特に効果的なのが「梨状筋ストレッチ」です。仰向けで片膝を立て、反対の膝の上に足首を乗せ、そのまま足を胸の方に引き寄せます。左右20~30秒ずつ行いましょう。
③軽いウォーキング
動かないことで筋肉がさらに硬くなるため、痛みが強くない場合は軽いウォーキングも効果的です。
5.再発予防のポイント

1.長時間同じ姿勢を避ける
2.座る時は骨盤を立てる意識を持つ
3.定期的にストレッチを取り入れる
4.片側に重心をかける癖をなおす
5.早めのメンテナンスを意識する
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、定期的に骨盤や筋肉の状態をチェックすることで、慢性化や再発を防げます。
6.関連する統計データ

腰やお尻の不調は、想像以上に多くの人が抱えている問題です。信頼性の高いデータをいくつか紹介します。
1.厚生労働省「国民生活基礎調査(2022)」
腰痛は日本人の自覚症状第1位。男性の約9人に1人、女性の約7人に1人が腰痛を感じています。(リンク)
2.日本整形外科学会「腰痛診療ガイドライン」
腰痛患者のうち、明確な原因が特定できるのは全体の約15%で、残りの85%は筋肉や骨盤由来の機能的問題と報告。(リンク)
3.日本理学療法士協会「運動器の健康に関する実態調査」
腰・臀部の不快感を訴える人の約60%が「片側に症状が出る」と回答。(リンク)
まとめ
片側の腰からお尻の重さは、単なる疲れや凝りではなく、骨盤の歪み・筋肉の緊張・神経の圧迫など、体のバランスの崩れから起きていることが多いです。放っておくと痛みに発展したり、反対側にも負担が広がるため、早めのケアが重要です。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの体の使い方や姿勢を元に根本原因を見つけ出し、改善へ導くお手伝いをしています。「なんとなく片側が重い」「違和感が取れない」そんな時こそ、早めにご相談ください。


バスケで腰痛 千歳市の青葉鍼灸整骨院

バスケの練習後に腰が痛い学生へーー「分離症」に注意!
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
バスケットボールの練習後、「腰が重い」「反ると痛い」「朝起きたときに腰がズキッとする」ーーこんな症状がある学生は多いのではないでしょうか。
バスケはジャンプ・ダッシュ・ストップ・体の捻りなど、腰に強い負担がかかるスポーツです。特に成長期の学生によって、腰の痛みを放置するのは危険です。
その痛み、もしかすると「腰椎分離症(ようついぶんりしょう)」が関係しているかもしれません。今回は、バスケで腰を痛める原因や、分離症の特徴・整骨院でのケア方法を詳しく解説します。
バスケで腰を痛める理由

バスケでは、ジャンプや切り返しの動作を何度も繰り返します。この時、腰椎(腰の骨)は「反る・ひねる・衝撃を受ける」という負担が加わりやすく、筋肉・関節・骨にストレスが集中します。
特に以下の動作で腰を痛めることが多いです。
・ジャンプシュートやリバウンドでの着地時の衝撃
・腰を反らせるシュートフォームやブロック動作
・ディフェンス時の中腰姿勢や素早い方向転換
・片足での動作・体幹の弱さによる姿勢の崩れ
学生アスリートは筋肉の発達に対して成長が追い付かない時期があるため、腰に負担が集中しやすい特徴があります。
成長期に多い「腰椎分離症」とは?
腰椎分離症とは、腰の骨(椎弓)が疲労によってヒビ(ストレス骨折)が入る状態を指します。特に中学生~高校生のスポーツ選手に多く、繰り返しのジャンプや反る動作で発生します。
・腰を反ると痛みが強くなる
・お尻や太ももにだるさが出る
・じっと立っていると痛い
・練習を休むと痛みが軽くなるが、再開すると再発する
初期段階では筋肉痛と区別がつきにくく、「少し休めば治る」と思ってしまうケースが多いですが、疲労骨折が進行すると「分離」したまま骨が癒合しなくなることもあります。
分離症は学生スポーツで特に多い

日本整形外科学会の調査によると、中高生のスポーツ障害の中で腰痛は第2位に位置しています。(リンク)
さらに、腰椎分離症は男子中高生の約5~6%に発症しており、その多くが野球・バスケットボール・サッカーなどジャンプや反る動きの多い競技に集中しています。(リンク)
また、文部科学省の調査でも、部活動におけるスポーツ障害の中で「腰の痛み」は全体の約25%を占め、特に男子バスケットボール部での発生率が高いとされています。(リンク)
つまり、バスケ部で腰痛を訴える学生は珍しくありません。ただし、早期発見・早期治療で完治するケースも多いので、早めの受診が大切です。
整骨院での検査とアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、まず「どの動きで痛みが出るのか」を確認し、筋肉・関節・骨盤の動きをチェックします。必要に応じて整形外科と連携し、分離症が疑われる場合はレントゲンやMRI検査を案内することもあります。
1.安静・炎症の抑制
初期は炎症が強いため、無理にストレッチやトレーニングを行わず、安静を優先します。電気治療や超音波治療で炎症を鎮め、痛みの軽減を図ります。
2.筋バランスの調整
痛みが落ち着いた段階で、腰部・腹部・臀部の筋肉を中心にバランスを整えます。特に「腸腰筋」や「大殿筋」「腹横筋」など体幹を安定させる筋肉が重要です。
3.姿勢と動作の改善
ジャンプやシュート時に腰を反らせすぎる癖、体幹の弱さ、片足での不安定さなどを改善します。骨盤や股関節の可動域を整えることで、腰への負担を減らします。
4.復帰プログラム
痛みが落ち着いたら、段階的に練習復帰を行います。体幹トレーニングや柔軟性アップのメニューを取り入れ、再発防止を徹底します。
分離症の早期発見ポイント

「ただの疲れ」だと思って放置すると、分離が進行して治りにくくなることがあります。以下のような症状がある場合は、早めに整骨院や整形外科を受診してください。
・練習後の腰の痛みが1週間以上続く
・腰を反るとズキッと痛い
・前かがみよりも反る動作で痛い
・お尻や太ももにしびれが出る
分離症は初期(疲労骨折段階)であれば治癒が可能です。しかし、分離が完成してしまうと骨がくっつかないままの「偽関節」状態になり、慢性的な腰痛の原因になります。
整骨院でできるケアの一例
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの軽減だけでなく、再発しない体づくりをサポートします。
・骨盤・股関節・腰部の可動域改善
・体幹の安定化トレーニング
・柔軟性向上のストレッチ指導
・正しいフォームのアドバイス
・テーピングによるサポート
また、学生の体の成長段階を考慮し、必要以上の負荷をかけないよう段階的な指導を行います。
自分でできる予防・セルフケア

1.練習前のストレッチをしっかり行う
腰・太もも前・お尻・背中をしっかり伸ばしてから動きましょう。
2.体幹を鍛える
腹筋・背筋・インナーマッスルを鍛えることで、腰への衝撃を減らせます。
3.姿勢を意識する
猫背や反り腰は腰痛の原因です。特に反り腰は分離症を悪化させるので注意。
4.無理をしない勇気を持つ
痛みが出た時は「少し休む事」も練習の一部。完治させることで、長期的に良いパフォーマンスにつながります。
まとめ
バスケットボールは全身を使う魅力的なスポーツですが、成長期の学生には腰への負担が大きい競技でもあります。練習後の腰痛を軽くみず、早めに原因を特定し、適切な治療を受けることが大切です。
・練習後の腰痛が続く場合は、「分離症」を疑う
・初期であれば治癒可能、放置すると慢性化する
・整骨院では痛みの軽減と再発予防の両面からサポート
腰痛を我慢せず、早期にケアして安心して練習に打ち込める体を取り戻しましょう。何か気になる症状や当てはまる症状などありましたら、お気軽にご相談ください。