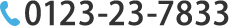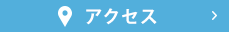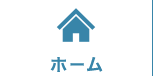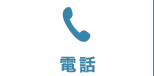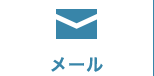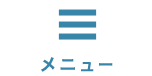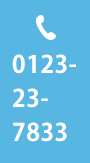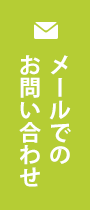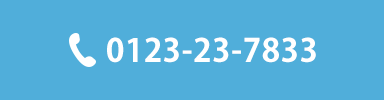物持って捻ると腰痛 千歳青葉鍼灸整骨院

重いものを持って体を捻ったら腰を痛めた,,,その原因と対処法
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
重い荷物を持ち上げた瞬間、あるいは体をひねった瞬間に「ピキッ」と腰に痛みを感じた経験はありませんか?このような動作で起こる腰の痛みは、筋肉や靭帯の損傷、関節の炎症などが関係しています。放置してしまうと慢性化や再発に繋がるため、早めのケアがとても大切です。
今回は、整骨院の視点から「なぜ腰を痛めるのか」「どう対処すべきか」詳しくお伝えします。
なぜ”ひねった”だけで腰を痛めるのか

腰を支える筋肉や関節は、前後方向の動きには強いのですが、「ひねり」や「回旋」の動きには弱い構造をしています。重いものを持つことで、腰椎(腰の骨)や椎間板、靭帯には大きな圧力がかかります。その状態で体を捻ると、関節や筋膜にねじれが生じ、急なストレスが加わります。
特に、以下のような状況ではリスクが高まります。
・片側に体重をかけながら荷物を持ち上げた
・膝を使わず腰だけで物を持ち上げた
・床にある重い荷物を体を捻って持ち上げた
・中腰の姿勢で長時間作業した
これらの動作では、「回旋+荷重」が同時にかかり、筋や靭帯の微細な損傷、椎間関節や椎間板の炎症を引き起こしやすくなります。
症状の特徴と注意すべきサイン
重いものを持って腰を痛めた時は、次のような症状がみられます。
・腰を捻る・起き上がると痛みが走る
・腰の片側がズキッと痛い、または張って動きづらい
・動き始めが特に痛く、安静にしていると楽になる
・翌日になっても痛みや違和感がとれない
・まっすぐ立つことや歩行がしづらい
このような症状が出た場合は、無理をせず安静を保ち、早めに専門家へ相談することが大切です。強い炎症があるうちは、マッサージやストレッチを自己判断で行うと悪化することもあります。
放置するとどうなる?
腰を捻って痛めた場合、「数日で良くなるだろう」と放置してしまう方も多いですが、注意が必要です。初期の炎症が治まっても、腰の深部筋肉が硬くなり、関節の動きが制限されることで再発しやすい”慢性腰痛”に移行するケースがあります。
実際、労働者の約54%が1年以内に腰痛を経験し、そのうち36%が3カ月以上続く慢性腰痛に悩んでいると報告されています。(リンク)
腰痛は日本の自覚症状ランキングでも男女ともに上位であり、最も多い症状の1つです。(リンク)
さらに、職業性の腰痛は労働災害の中でも発生件数が最も多く、2019年だけでも約5,000件が報告されています。(リンク)
つまり、腰痛は「誰にでも起こる身近なトラブル」であり、早めにケアを行うことが慢性化を防ぐ最善策です。
整骨院での主な治療・対応

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、重いものを持って腰を痛めた方に対し、次のような流れで施術を行っています。
①問診・検査
痛みが出た動作、発症時の状況、体の使い方などを丁寧に確認します。腰だけではなく、骨盤や股関節、背中の動きまでチェックして原因を特定します。
②炎症の鎮静
痛みが強い初期は、温熱や電気治療を用いて炎症を抑えます。無理に動かすよりも、痛みを落ち着かせることが優先です。
③筋・関節の調整
痛みが落ち着いてきたら、硬くなった筋肉や関節を手技で緩めていきます。腰方形筋・大殿筋・腹斜筋など、捻じり動作に関わる部位を中心に施術し、動きをスムーズに戻します。
④再発予防のための運動指導
腰を痛めた方の多くは、普段の姿勢や身体の使い方に癖があります。荷物を持つときの正しい姿勢、骨盤を安定させる体幹トレーニング、ストレッチなどをお伝えし、再発を防止します。
自分でできる予防・セルフケア

腰を捻って痛めないためには、日常のちょっとした意識が大切です。
1.荷物を持ち上げる時は「膝を使う」
腰だけで持ち上げず、膝を曲げて重心を下げましょう。荷物はできるだけ体の近くで抱えるようにします。
2.体を捻らない
物を運ぶときは、腰を捻るのではなく、「足ごと向きを変える」のがポイントです。
3.長時間同じ姿勢を避ける
座りっぱなし・立ちっぱなしの状態が続くと腰の筋肉が硬くなります。1時間に1回は軽く伸ばす習慣をつけましょう。
4.体幹を鍛える
腹筋や背筋などの体幹筋を鍛えることで、腰にかかる負担を分散できます。無理のない範囲で、軽いストレッチや呼吸を意識した運動を行いましょう。
整骨院での早期対応が回復を早める
腰を捻った直後の正しい対応は、その後の回復スピードに大きく影響します。痛みを我慢して動き続けていると、筋肉の緊張や関節のズレが固定化し、治りが遅くなってしまいます。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、腰を支える筋や骨盤周りを整え、痛みを早く鎮めるだけでなく、再発しにくい体の使い方を身につけるお手伝いができます。
「まだ少し痛いけど我慢できる」「仕事が忙しくてそのままにしている」ーーそんな方こそ、早めの来院がおすすめです。初期のケアが、今後の腰の健康を守ります。
まとめ
重いものを持って体を捻った時に起こる腰痛は、筋肉や靭帯、関節に急な負担がかかることで起こります。初期対応を誤ると慢性化しやすく、再発を繰り返すこともあります。
・荷物は体の近くで持ち上げる
・腰を捻らず、足ごと向きを変える
・痛みが出たら早めに整骨院でケアを受ける
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの原因を正確に見極め、施術・動作指導・予防までトータルサポートいたします。腰を痛めてしまった方も、早期の対応で健康な身体を取り戻しましょう。


運動やめて膝が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

「運動を止めてから、膝が動かしづらくなったあなたへ~整骨院で取り戻す”動きやすい膝”~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
はじめに
「以前はウォーキングやジョギング、ジム通いをしていたのに、最近どうも膝の曲げ伸ばしがスムーズじゃない」「階段を降りると膝が引っかかる感じがする」「正座や椅子から立ち上がると膝が固まったように感じる」ーーこういった変化にドキッとしたことはありませんか?
運動習慣をやめてしまったり、活動量が著しく低下したりすると、膝関節周りの筋肉・関節包・軟部組織の機能が徐々に低下し、「動かしづらさ」「可動域の制限」「違和感」を生みやすくなります。
今回の記事では、運動を止めてから膝の調子が悪くなったと感じる方に向けて、なぜそのような変化が起きるのか、どのように整骨院でケアができるかを詳しくご紹介します。
膝が動かしづらくなる仕組みー運動中止/活動低下による影響
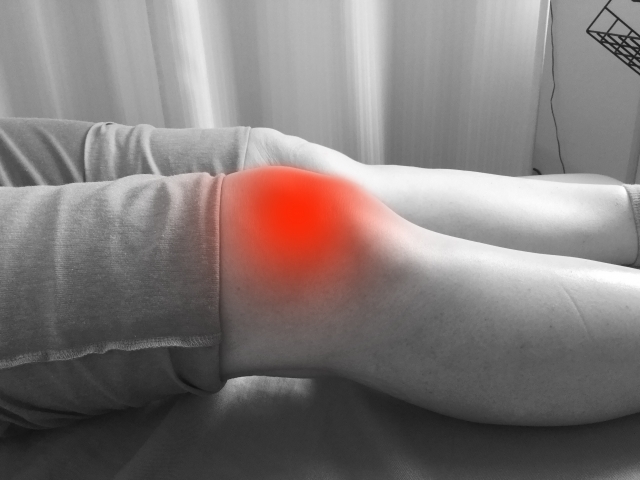
①筋力低下・筋肉の硬さ
運動を止めてしまうと、膝を支える筋肉(特に大腿四頭筋、ハムストリングス、内側広筋など)の使用頻度が低下します。この筋力低下は膝関節を安定させる力が落ちるだけでなく、筋肉が硬く、萎縮気味になってしまうことで関節の可動域も狭くなります。例えば、「運動不足は関節を支える大腿四頭筋の筋力低下を招き、膝への衝撃をダイレクトに受けやすくなり、関節可動域が狭くなって動きがぎこちなくなる」ことが指摘されています。(リンク)
②関節可動域の制限(拘縮・軟部組織の短縮)
筋肉・腱・関節包などの軟部組織は、使われなくなると徐々に短縮し、関節可動域が制限される傾向があります。いわゆる「関節が硬い」「曲げづらい」「伸ばしづらい」と感じるのはこれが一因です。例えば、「膝関節伸展可動域が年数経過で有意に減少した」研究があります。(リンク)
③関節の負担増・変形性変化の進行
膝を支える筋肉・靭帯・関節包の機能が低下すると、膝関節そのものにかかる負担が増加し、将来的に「変形性膝関節症」などのリスクも高まります。実際、40歳以上の日本人で、膝関節の変形性関節症の有病率が男性で42.0%、女性で61.5%と高く、可動域制限や痛みを伴うものが少なくないと報告されています。(リンク)
こうした3つの流れ(筋力低下→可動域制限→関節負担増)により、「運動をやめてから膝が動かしづらくなった」という現象が起きやすくなります。
整骨院でできるアプローチ

運動を止めて膝が動きづらくなった方に対して、千歳市の青葉鍼灸整骨院では、以下のような多面的なアプローチを行います。
①筋・軟部組織への手技・調整
・大腿四頭筋・ハムストリングス・内腿の筋肉および膝裏(膝窩)・外側膝まわりの筋膜や靭帯に対し、ストレッチ、筋膜リリース、トリガーポイントケアなどを行い、筋肉の硬さや萎縮傾向を改善します。
・膝関節包や靭帯が短縮・硬化している場合、軽く関節を揺らしたり、可動域を意識したゆるやかな運動誘導を行います。
・さらに、骨盤・股関節・足関節など膝と連動する部位の可動性を整えることで、膝単独ではなく”下肢全体の動き”を改善します。
②関節可動域の改善・姿勢バランス調整
・膝の曲げ伸ばし・正座・椅子からの立ち上がり・階段昇降など、日常生活で使う動きを確認し、どの局面で「動かしづらさ」が出ているのかをチェックします。
・その上で、膝をスムーズに動かしやすくするために、関節運動(他動・自動)・可動域拡大運動を段階的に組み込みます。
・また同時に、立ち姿勢・歩行・立ち上がり・座り方などの姿勢・動作習慣を整えることで、膝への余計なストレスを減らします。
③運動・活動習慣の再構築支援
・運動習慣を止めてしまった方に対して、まずは無理のない範囲で膝に負担の少ない軽めの運動(ウォーキング・スイミング・サイクリング)を提案します。
・筋力低下が進んでいる場合は、大腿四頭筋・ハムストリングス・殿筋群の筋力トレーニングを整骨院と連携して指導することがあります。
・継続的に運動を行うことで、膝を支える筋・軟部組織が活性化し、可動域改善や痛み・違和感の軽減につながります。運動習慣がない日本の実情も無視できない要素です。
④セルフケア指導・再発予防
・家でもできるストレッチ・膝まわり軽運動・立ち上がり・階段動作の改善などをアドバイスします。
・運動を止めてしまった方はまず「膝を動かす習慣を再開する」「座りっぱなし・立ちっぱなしを避ける」「階段・段差を活用する」など小さな動作を増やすことが鍵です。
・定期的に整骨院へメンテナンスに来ていただくことで、膝の動きを良好に保ち、関節の負担を減らしていきます。
まとめ
運動をやめてから「膝が動かしづらい」「膝が辛い」、、、という感覚を抱えている方は、決して年齢のせいだけではありません。それは「筋肉・軟部組織・関節可動域・運動習慣」という複数の要素が少しずつ弱くなって現れたサインです。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、膝そのものだけでなく、膝を支える筋・軟部・関節・姿勢・習慣にまで目を向けたケアが可能です。「膝を再び軽やかに動かしたい」「階段を怖がらずに降りたい」「日常の違和感を無くしたい」ーーそんな思いがある方は、是非一度ご相談ください。今再び、小さな一歩を動き出すことが、膝の動きを取り戻す第一歩です。


仕事後の背中・腰痛 千歳青葉鍼灸整骨院

仕事後に背中・腰が辛い方へ~その原因と整骨院でできる事~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
1日の仕事が終わり、帰宅するころになると「背中が重い」「腰が張って辛い」と感じる方は少なくありません。特にデスクワークや立ち仕事、重いものを扱う職種では、このような不調が慢性的に続いている人が多いのが現状です。実は、こうした「仕事後の背中・腰の辛さ」は、単なる疲労ではなく、体の使い方の偏りや姿勢の乱れ、筋肉の緊張、自律神経の乱れが複雑に関係しています。
仕事後に背中・腰が辛くなる主な原因

①長時間の同じ姿勢
デスクワークで座りっぱなし、あるいは立ち仕事で立ちっぱなしの状態が続くと、筋肉が同じ長さで固定され続けるため、血流が悪くなります。筋肉の中に疲労物質が溜まり、「だるさ」や「重さ」、「痛み」として感じやすくなります。
特に、デスクワークでは骨盤が後ろに傾き、背中が丸まりやすくなります。その結果、背筋(脊柱起立筋)や腰の深層筋(多裂筋など)に負担がかかり、夕方になるほど症状が強くなります。
②肩甲骨や骨盤の動きの低下
背中や腰の筋肉は、肩甲骨や骨盤と密接に関係しています。肩甲骨が動かないと背中の筋肉が硬くなり、骨盤の動きが悪くなると腰部のストレスが増えます。こうした「体幹の連動の悪さ」が仕事後の辛さを引き起こしているケースが非常に多いです。
③自律神経の乱れ
長時間の集中、ストレス、疲労の蓄積により、交感神経が優位な状態が続くと、筋肉が常に緊張します。また、血流が悪化して疲労回復が遅れるため、「一晩寝ても疲れが取れない」状態に。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、この自律神経のバランスを整えることも非常に重要な施術ポイントになります。
データでみる「腰痛・背中の不調」の現状

・厚生労働省の調査によると、日本人の約4人に1人が「腰痛」を抱えていると報告されています。(リンク)
・労働安全衛生総合研究所の調査では、「腰痛による労働損失」は年間約3,800億円と推定されており、仕事に大きな影響を与えています。(リンク)
・また、環境省の統計によると、在宅勤務者の約52%が「背中・腰の不調を感じる」と回答しており、姿勢環境の変化も影響しています。(リンク)
これらの数字からもわかるように、仕事と腰・背中の不調は非常に深く関わっています。
整骨院でのアプローチ

①筋肉と関節のバランス調整
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、硬くなっている筋肉を緩め、動きの悪い関節を動きやすくすることで、痛みの原因を根本から改善していきます。特に重要なのは、背中や腰の筋肉だけでなく、骨盤・股関節・肩甲骨周囲を含めて全体のバランスをみることです。
②姿勢改善と動作指導
姿勢を支える筋肉(体幹や殿筋など)の弱化も大きな原因です。日常で正しい姿勢をキープできるように、ストレッチや軽いエクササイズ指導を行うことで、再発予防を目指します。また、デスクワークの方には、椅子やPCの高さなどの環境調整アドバイスも効果的です。
③自律神経へのアプローチ
自律神経のバランスを整えるためには、リラックスを促す施術も有効です。呼吸を整えることで副交感神経が優位になり、筋緊張の緩和・睡眠の質向上につながります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、ストレス性の筋緊張に対しても、穏やかな手技で対応することが可能です。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
自宅でできるセルフケア

1.深呼吸を意識する
背中の緊張は呼吸の浅さとも関係しています。深い呼吸を3~5分行うだけでも血流が改善されます。
2.30分に一度は姿勢を変える
立ち仕事でも座り仕事でも、一定時間ごとに姿勢を変えるだけで筋緊張が大きく軽減されます。
3.軽いストレッチを習慣に
背中や腰まわりを中心に、1日5分程度のストレッチを行うことで、慢性的な張りを予防できます。
整骨院での施術をおすすめするタイミング
・朝より夕方に痛みや重さが強い
・マッサージをしてもすぐ戻る
・睡眠の質が悪く、疲れが取れない
・背中や腰の「張り」が常に残っている
これらに当てはまる場合は、単なる疲れではなく、身体のバランスが崩れているサインです。放っておくと慢性腰痛や肩こり、坐骨神経痛へと発展することもあります。
まとめ
仕事後の背中・腰の辛さは、単なる疲労ではなく「姿勢・筋肉・自律神経」のバランスが乱れている結果です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、体全体を丁寧にチェックしながら、根本的な原因にアプローチしていきます。「仕事終わりが辛い」「いつも背中が重い」と感じる方は、我慢せずに早めにご相談ください。
毎日の疲れをため込まず、快適に仕事や日常を過ごせる体づくりを整骨院と一緒に行いましょう。


天気が悪いと頭痛 千歳青葉鍼灸整骨院

天気が悪いと頭痛がするあなたへ~気圧と自律神経の関係を整骨院から
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「雨が降る前になると頭が重い」「天気が崩れると首や肩まで痛くなる」そんな症状に悩んでいませんか?実はそれ、”天気の変化による「気象病」”の可能性があります。特に頭痛は、整骨院に来られる患者さんの中でも非常に多い訴えの1つです。
天気が悪くなると頭痛が起こるのはなぜ?
天気が崩れる前には「気圧」が下がります。この気圧の変化は、耳の奥にある「内耳」にある気圧センサー(前庭神経)が感じ取ります。このセンサーが刺激を受けると、脳に信号が送られ、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが乱れるのです。
その結果、
・血管が急に拡張または収縮して頭痛を引き起こす
・筋肉が緊張して首や肩が張る
・血流が滞って重だるい感覚が出る
といった症状が現れます。つまり、「天気頭痛」は単なる気のせいではなく、身体の生理的反応なのです。
気象病と頭痛の関係:統計データからみる実態

気圧変化による頭痛や体調不良は、近年、医学的にも注目されています。以下のデータからも、その多さがわかります。
1.日本気象協会の調査では、「天気や気圧の変化で体調が悪くなる」と答えた人は全体の68.8%。特に女性では、75.8%にのぼり、頭痛・肩こり・倦怠感が主な症状です。(リンク)
2.ウェザーニュースの調査(2023年)では、「気圧変化で頭痛を感じる」と答えた人は約60%。そのうち半数以上が鎮痛剤を常用していると報告されています。(リンク)
3.厚生労働省・国民生活基礎調査によると、頭痛は日本人の自覚症状の中で第2位(女性)・第4位(男性)に位置しています。特に天候変化が誘因の1つとされています。(リンク)
このように、気圧の変化に体が敏感に反応する人は決して少なくありません。現代のストレス社会や不規則な生活が、自律神経を乱しやすくしていることも関係しています。
整骨院で行う「天気頭痛」へのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、単に頭痛を抑えるのではなく、自律神経と筋肉・姿勢のバランスを整えることを目的に施術を行います。
①首・肩・背中の筋緊張を緩める
気圧変化によって交感神経が優位になると、筋肉が緊張しやすくなります。特に「僧帽筋」や「後頭下筋群」は頭痛と密接に関係しています。これらを丁寧にほぐすことで、血流が改善し、神経への圧迫も軽減されます。
②頭の重だるさをとる頸部調整
首の骨(頸椎)の配列が崩れると、後頭部の神経が刺激され、頭痛が悪化することがあります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、ソフトな頸椎調整を行い、神経や血管の流れをスムーズにします。
③自律神経バランスを整える呼吸と姿勢指導
浅い呼吸や猫背は、自律神経の乱れを助長します。呼吸を深め、胸を開く姿勢を保つことで、副交感神経が働きやすくなり、体がリラックス状態に戻ります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、自宅でもできる簡単な呼吸法やストレッチも指導しています。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
自分でできるセルフケア方法

頭痛が出やすい時期(梅雨や台風前など)には、以下のようなセルフケアもおすすめです。
1.耳のマッサージ
耳の周りを優しく引っ張ったり、回したりすることで内耳の血流を促し、気圧センサーの過敏を和らげます。
2.首肩の温め
蒸しタオルや入浴で筋肉を温めることで、緊張が解け、自律神経が整いやすくなります。
3.睡眠と生活リズムの安定
自律神経は「体内時計」と密接に関係しています。就寝・起床の時間を一定に保ち、夜更かしやスマホの見過ぎを避けることも大切です。
整骨院からのメッセージ
天気による頭痛は、「気のせい」でも「我慢すれば治るもの」でもありません。それは身体が環境変化に過敏に反応しているサインです。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの体の状態を丁寧にチェックし、
・筋肉や関節の動き
・自律神経のバランス
・血流や姿勢のクセ
といった複合的な要因を整えていきます。
「天気が悪くなるたびに頭痛が出る」という方は、是非一度ご相談ください。季節や天候に左右されない、本来のバランスを取り戻した体を目指してサポートいたします。
まとめ
天気頭痛は、気圧による自律神経の乱れと筋肉の緊張が原因です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉と神経のバランスを整えながら、再発しにくい体づくりを目指します。早めのケアで、雨の日も晴れやかに過ごせる体を取り戻しましょう。


首が張って頭痛 千歳市青葉鍼灸整骨院

首が張って頭痛がするあなたへ
~自律神経を整えて、首・肩・頭の不調を根本から改善~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「朝から首が張って頭が重い」「デスクワークの後は首からこめかみまでズーンと痛む」そんな症状で悩んでいませんか?
首の張りと頭痛は、多くの方が経験する身近な不調です。しかし、ただ筋肉が硬いだけでなく、「自律神経の乱れ」が深く関わっていることもあります。今回は、首の張りや頭痛が起こる仕組み、自律神経との関係、そして整骨院でできる改善方法について詳しくご紹介します。
首の張りと頭痛が起こる仕組み

長時間のスマホ操作やデスクワーク、姿勢の崩れによって、首や肩の筋肉(僧帽筋・肩甲挙筋・胸鎖乳突筋など)は常に引っ張られ、緊張状態になります。この筋肉の緊張が続くと血流が悪化し、老廃物が溜まり、結果として「張り」や「鈍い痛み」として感じられるようになります。
このような状態が続くと、「緊張型頭痛」と呼ばれる頭痛を引き起こすことがあります。緊張型頭痛は、世界的にも最も多い頭痛の1つであり、一般人口の約22%が経験しているとされています。(リンク)
特に現代社会では、パソコンやスマートフォンの使用時間が長く、姿勢不良が慢性化している人が増えています。首に負担がかかる時間が長いほど、筋肉のこわばりが強くなり、頭痛・目の疲れ・集中力の低下など、さまざまな不調へとつながっていきます。
自律神経の乱れが、首と頭の不調を悪化させる
「首コリ」と「頭痛」がなかなか取れない方の中には、自律神経のバランスが乱れているケースが多く見られます。
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」という2つの神経があり、体のリズム(血流、呼吸、心拍、内臓機能など)を自動的にコントロールしています。
しかし、ストレスや不眠、過労、気候の変化、スマホやPC画面からの刺激などが続くと、交感神経が優位な状態が長引き、筋肉の緊張や血流障害が起こりやすくなります。
交感神経が優位な状態では、常に「緊張モード」。筋肉は硬くなり、呼吸も浅くなり、血流が悪化するため、首の張りや頭痛が改善しにくくなります。
また、自律神経の乱れは「何となく体が重い」「疲れが取れにくい」「寝てもスッキリしない」といった慢性的な不調も引き起こします。厚生労働省の調査によると、”20~60代の約80%”が「なんとなく不調を感じている」と回答しており、その原因の多くがストレスや生活リズムの乱れによる自律神経の影響とされています。(リンク)
首コリ・頭痛は女性にも多い

近年の調査では、女性の約76%、男性の約62%が「首・肩こり」を自覚しており、そのうち約3割が「頭痛も伴う」と回答しています。特に女性の場合、ホルモンバランスの変化によって自律神経が乱れやすく、首コリや頭痛、めまい、倦怠感を感じる傾向が強いと報告されています。(リンク)
つまり、「首の凝りと頭痛」は単なる筋肉の凝りではなく、体の内側(自律神経・ホルモン・血流など)からのSOSである可能性もあるのです。
整骨院での改善アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「筋肉」「神経」「生活習慣」の4つの観点から、首と頭の不調にアプローチしていきます。
①筋肉の緊張を緩める
首・肩・肩甲骨周囲の筋肉を丁寧に緩めることで、血流を促進し、老廃物の滞りを改善します。筋膜リリースやストレッチ、軽度の手技で筋緊張を和らげる事で、「張り」や「重だるさ」を解消します。
②姿勢バランスの調整
頸椎や胸椎、骨盤のバランスが崩れていると、常に首に負担がかかる姿勢になります。正しい重心を知ることで、再発しにくい状態を作ります。
③自律神経を整える施術
呼吸に合わせたゆるやかな手技や、頭蓋・首まわりを優しく揺らす施術によって副交感神経を優位に導きます。「リラックスして眠くなる」「呼吸が深くなった」と感じる方も多く、自律神経のバランス改善に効果的です。
④セルフケアの指導
・首・肩・胸周りのストレッチ
・デスクワーク時の姿勢の工夫
・深呼吸や軽い運動の習慣化
・寝る前のスマホ制限・入浴などリラックス習慣
これらを継続することで、施術効果を長持ちさせ、再発を防ぐことができます。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
日常でできる簡単ケア方法

1.1時間に1回は姿勢を変える
デスクワーク中は、首を回す・肩をすくめるなどの軽い運動を。
2.深呼吸を意識する
浅い呼吸は交感神経を刺激します。1日数回、ゆっくりとした腹式呼吸を。
3.お風呂にゆっくり浸かる
38~40度のぬるめのお湯に10分浸かるだけでも副交感神経が優位になります。
4.就寝前のスマホ時間を減らす
ブルーライトが自律神経を刺激し、眠りを浅くします。
こうした小さな習慣の積み重ねが、首や頭の回復力を高めてくれます。
まとめ
首の張りと頭痛は、「筋肉の凝り」だけでなく、「自律神経の乱れ」も深く関わっています。ストレス社会で頑張る現代人にとって、自律神経のバランスを保つことは健康のカギです。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉や姿勢を整えるだけでなく、体の内側からの回復をサポートすることで、痛みの根本改善を目指します。「最近、首が張って頭痛が増えた」「寝てもスッキリしない」という方は、是非一度ご相談ください。あなたの体を、”緊張”から”リラックス”へ。自律神経が整えば、首も頭も軽くなります。


小中学生のケガ増加 千歳青葉鍼灸整骨院

小中学生のスポーツケガが増えている?整骨院が伝えたい予防とケアの大切さ
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
近年、小中学生のスポーツ活動はかつてないほど盛んになっています。部活動やクラブチーム、地域のスクールなどで、週に5~6日練習しているお子さんも珍しくありません。体を動かすことは心身の発達にとって非常に大切ですが、一方で「ケガの増加」という問題が深刻化しています。
千歳市の青葉鍼灸整骨院には、「練習中に足を捻った」「膝がずっと痛い」「腰が重い」など、スポーツによる不調を訴える小中学生が多く来院しています。今回の記事では、現代の小中学生に多いスポーツ障害の実態や原因、整骨院でのケア方法、そして予防のポイントを解説します。
統計でみる小中学生のスポーツケガの現状

スポーツによるケガは昔からありますが、現代は「早期専門化」と「練習量の増加」により、その傾向がより顕著になっています。最新の研究から、以下のような興味深いデータが出ています。
1.スポーツの専門化とケガの関係
日本の小中学生を対象とした研究によると、早い時期に1つのスポーツだけに集中する子ほど、使い過ぎによる障害(オーバーユース障害)が増加していると報告されています。小学生高学年で約21%、中学生では35%が「スポーツ中の急性または慢性のケガ」を経験していました。(リンク)
2.練習頻度とケガ発生率の関係
別の研究では、「週あたりの練習日数が多い」「複数競技をしていない」子ほどケガの発生リスクが高いことが示されています。特に、休みなく週5日以上練習している子は、足首・膝・腰などのオーバーユース障害が増加しています。(リンク)
3.体育授業でもケガが増加傾向に
学校の体育授業中にもケガが増えています。調査によると、学年が上がるほどケガの発生率が高くなり、男子は球技、女子は跳び箱や縄跳びなどでのケガが多い傾向があります。(リンク)
これらのデータからも、「小中学生の体が怪我にさらされやすい環境」にあることがわかります。
成長期の体は「ケガしやすく」「治りにくい」

子どもの体は日々成長しています。骨や筋肉、関節、靭帯が未発達な段階では、強い負荷や繰り返しの動作に耐えきれず、痛みや炎症が起きやすくなります。
・足首の捻挫・膝の靭帯損傷:サッカーやバスケットボールで多発。
・オスグッド病:成長期に膝の前側が痛む代表的な障害。
・シンスプリント:走り過ぎによるすねの痛み。
・腰椎分離症:野球や体操で体を反らす動作が多い子に発症。
・野球肘・テニス肘:同じ動作を繰り返すことで肘関節が炎症を起こす。
・シーバー病:成長期に踵が痛む代表的な障害。ジャンプや走る競技で多い。
これらの症状は「最初は軽い痛み」から始まります。しかし、放置したまま練習を続けると、慢性的な痛みや関節変形につながることもあります。
どうしてケガが起きるのか?主な原因
1.オーバーユース(使い過ぎ)
毎日の練習で、筋肉や関節の修復が追い付かず疲労が蓄積。休む間もなく使い続けることで、炎症や損傷が発生します。
2.柔軟性の不足
特に思春期前後は急激に身長が伸び、筋肉や腱の柔軟性が一時的に低下します。その結果、関節への負担が増え、捻挫や肉離れを起こしやすくなります。
3.フォームの乱れ・技術不足
正しい体の使い方が身についていないまま強度を上げてしまうと、関節や筋肉の一部に負担が集中します。
4.休息と栄養の不足
体は「練習で壊し、休息で強くなる」もの。休みなく練習を続けると、回復が追い付かずケガに直結します。
整骨院でできる事

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、ケガの治療はもちろん、「ケガをしにくい体づくり」までトータルにサポートします。
①痛みの軽減と炎症ケア
電気治療・手技療法・冷却などを用いて炎症を抑え、痛みを軽減します。
②筋肉・関節バランスの調整
硬くなった筋肉や関節を丁寧に緩め、可動域を改善。姿勢や動作のクセも整えます。
③成長期に合わせた運動指導
ストレッチや体幹トレーニング、バランス練習などを取り入れ、フォームを改善。「ケガをしない体の使い方」を身につけていきます。
④再発防止とメンテナンス
痛みが取れても、再発しやすい部分を定期的にチェックし、予防を続けます。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
保護者・指導者の方へーーケガを防ぐために出来る事
・練習前後のストレッチを習慣化する
・痛みを訴えたら「我慢させない」
・睡眠・食事・休養をしっかり取らせる
・週に1回は完全休養日を設ける
・適切なシューズ・用具を選ぶ
子供たちの「痛い」は小さなサインです。無理をさせるよりも、早期に対応することで、結果的に競技への復帰も早まります。
整骨院からのメッセージ
私たち整骨院は、スポーツで頑張る子どもたちを応援しています。「痛みを取る」だけでなく、「再発しない体づくり」「正しい体の使い方」「休む勇気」を伝えることが私たちの役目です。
スポーツは本来、楽しく、健康を育てるもの。ケガを恐れず、でも無理をし過ぎないように。そのバランスを整えるためにも、体の専門家である整骨院をぜひ活用してください。もし、気になる症状や当てはまる症状などありましたら、お気軽にご相談ください。


口が開きにくい 千歳市の青葉鍼灸整骨院

口が開きにくい,,,その不調、顎関節症かもしれません
~整骨院で整える「顎と首のつながり」~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「大きく口を開けると痛い」「口を開けようとしても引っかかる」「顎のあたりでカクっと音が鳴る」ーーこうした症状がある方は、顎関節症(がくかんせつしょう)の可能性があります。
放っておくと顎だけでなく、首や肩のコリ、頭痛、姿勢の崩れにもつながることがあります。今回は、整骨院の視点から「口が開きにくい」症状の原因と改善のポイントをお伝えします。
顎関節症とは?
顎関節症とは、顎の関節(側頭骨と下顎骨の接合部)や、その周囲の筋肉・靭帯にトラブルが起きた状態を指します。代表的な症状には以下のようなものがあります。
・口が開きにくい(開口制限)
・顎を動かすと「カクっ」「ジャリっ」と音がする
・顎がだるく疲れやすい
・首や肩までこってくる
顎関節は顔の左右にひとつずつあり、首・頭・姿勢と密接に関係しています。そのため、顎の動きが悪くなると、首や肩の筋肉が代償的に働き、全身のバランスが崩れてしまうのです。
顎関節症は珍しくない

顎関節症は「まれな病気」ではありません。近年の研究では、非常に多くの人が症状を経験しています。
・成人では約31%が顎関節症を有する可能性があるという報告があります。(リンク)
・全人口のうち約3人に1人がTMD(側頭下顎部障害=顎関節症)の症状を持ち、その中の約5%前後が治療を必要とするレベルとも報告されています。(リンク)
・日本国内では、歯科受診者のうち男性の約9.9%、女性の約17.3%(平均13.6%)に症状がみられたとの研究もあります。(リンク)
これらの統計からも分かるように、顎関節の不調は誰にでも起こりうる、非常に身近なトラブルです。
なぜ口が開きにくくなるのか?原因を探る

顎関節がスムーズに動くためには、「関節の滑り」と「筋肉の協調運動」が正しく働くことが大切です。しかし、次のような原因でバランスが崩れると、口が開きにくくなります。
1.顎関節の構造異常
関節内にある「関節円板」がずれたり、炎症を起こすことで、開閉時に引っかかるようになります。
2.咀嚼筋の緊張や疲労
咬筋や側頭筋など、噛むための筋肉が硬くなりすぎると、顎がスムーズに動かなくなります。特に「歯の食いしばり」や「夜間の歯ぎしり」が続く人は注意が必要です。
3.姿勢・首との関係
顎関節は頭の骨と首の骨(頸椎)に支えられています。首の筋肉が固まると、顎の動きも制限されるため、「姿勢の崩れ」が原因になっているケースも多いです。
4.ストレスや精神的緊張
ストレスが強いと、無意識に顎の筋肉を緊張させてしまいます。その結果、関節や筋膜が固まり、開口制限を引き起こすことがあります。
整骨院でのアプローチ方法

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「顎そのもの」だけでなく「体全体の動きや姿勢」をみて改善を図ります。主な施術内容は以下の通りです。
①顎周囲筋のリリース
咬筋・側頭筋・内外翼突筋など、顎を動かす筋肉の硬さを丁寧にほぐします。強い刺激を与えず、痛みを出さない範囲で緩めることがポイントです。
②顎関節の可動調整
関節包や靭帯を軽く動かし、関節の”滑り”を取り戻すように調整します。ポキポキ鳴らすような施術はなく、滑走性を高める手技を使います。
③首・肩・胸郭の調整
顎の動きは、首や肩の筋肉と連動しています。首の前後バランスや胸郭の硬さを整えることで、顎への負担を軽減します。
④姿勢改善と再発予防エクササイズ
正しい姿勢と口の動かし方を習得していただくことで、再発を防ぎます。例えば、
・顎を突き出さず、頭の位置を整える
・歯を軽く離す「リラックスポジション」を意識する
・深呼吸や軽いストレッチで筋緊張を緩める
などを指導します。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
自宅でできるセルフケア
整骨院での施術と併せて、以下のセルフケアを取り入れると改善が早まります。
1.軽い開閉運動
痛みのない範囲でゆっくり口を開け閉めする練習を1日数回行いましょう。
2.咬筋ほぐし
頬の横(エラの少し前)を指で優しく押し、5~10秒ほどキープします。
3.歯を話す意識
安静時は上下の歯が触れないのが理想です。「唇を閉じて、歯は離す」この状態を意識してみて下さい。
4.噛みすぎ注意
硬い食べ物(スルメ、フランスパンなど)や長時間のガムは避けましょう。
整骨院での治療が有効な理由
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、顎だけでなく「首~背中~骨盤」までをひとつの動きの連鎖として捉えることができます。そのため、「顎の痛みだけを見て終わり」ではなく、全身のバランスを整える施術が可能です。
顎関節症の多くは、顎以外に原因があります。
・長年の姿勢のクセ
・首の筋緊張
・噛み癖やに非常の動作
こうした背景を整骨院で見直すことで、再発を防ぐことができます。
まとめ:顎の不調は、体のサイン
口が開きにくい、顎がカクカク鳴る、口を開けると痛いーー
これらは単なる「顎の問題」ではなく、体全体のバランスが崩れているサインです。
早めにケアすることで、症状の悪化や慢性化を防ぐことができます。「歯医者さんに行くほどでも,,,と思っている方でも、整骨院で筋肉や姿勢から整えることで、自然な開閉運動を取り戻せるケースは多くあります。
「顎の違和感、放っておかずにご相談ください。」あなたの”噛む・話す・笑うを、もう一度自然に戻すお手伝いをします。


ぎっくりから腰痛 千歳青葉鍼灸整骨院

ぎっくり腰の後、腰の違和感が取れないあなたへ
~もう治ったはずなのに残る不快感の正体とは~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
ぎっくり腰を経験した後、「動けるようになったのに、なんとなく腰に違和感が残っている」「重だるい感じが抜けない」「再発しそうで怖い」と感じていませんか?実は、ぎっくり腰(急性腰痛症)は痛みが落ち着いても、筋肉や関節の機能が完全に回復していないことが多いのです。今回は、その違和感の正体と、整骨院でできる対策について解説します。
ぎっくり腰の回復後に違和感が残る理由

ぎっくり腰は、多くの場合「腰の筋肉や靭帯に急なストレスが加わり、微細な損傷が起きた状態」です。炎症が落ち着けば痛みは引きますが、組織が完全に元通りになるには時間がかかります。
1.筋肉の防御反応が残っている
強い痛みを経験すると、脳と筋肉が「また痛くなるかもしれない」と判断し、無意識に腰まわりを固めてしまいます。
2.関節の動きが制限されている
炎症時に動きをかばっていた結果、腰椎や骨盤の動きに偏りが出ることがあります。これが残ってしまうと、痛みはなくても「腰がスッキリしない」状態になります。
3.体幹や股関節の筋バランスが崩れている
腰をかばうことで、殿筋(お尻の筋肉)や腹筋群が弱まり、再び腰に負担が集中しやすい状態に。特に、腸腰筋や多裂筋など深い筋肉の働きが落ちていると、違和感が長引く傾向にあります。
放置すると「慢性腰痛」や「再発」へ
日本整形外科学会によると、一度ぎっくり腰を経験した人の約60%が1年以内に再発を経験していると報告されています。(リンク)
また、厚生労働省の調査では、日本人の約84%が生涯で一度は腰痛を経験し、その多くが「慢性的な腰の重さ・違和感」として続く傾向にあります。(リンク)
さらに、ぎっくり腰後の筋力低下や姿勢の乱れが原因で、腰痛が長期化する人は全体の約30%にのぼるという研究もあります。(リンク)
こうした統計からも分かる通り、「痛みが取れた=完治」ではなく、違和感のある状態を放置することが再発の第一歩なのです。
整骨院での改善アプローチ

ぎっくり腰後に残る違和感を解消するには、「痛みを取る」よりも「動きを取り戻す」ことが重要です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、次のようなアプローチを行います。
①筋膜・深層筋のリリース
腰方形筋や多裂筋、腸腰筋など、腰の奥で支えを担う筋肉を丁寧に緩めます。表面の筋肉だけでなく、深層までアプローチすることで「腰の張り感」が軽くなり、可動性が戻ります。
②再発防止のための運動指導
体幹(インナーマッスル)を中心とした軽いエクササイズを行い、正しい動作を再教育します。特に「腹横筋」や「多裂筋」を再活性化することで、腰を守る”天然コルセット”の機能を回復させます。
③日常生活の動作改善
・長時間座りっぱなしを避ける
・床から物を取る時は腰から曲げず、膝を曲げて体を前に倒す
・朝のストレッチで股関節を動かす
これらを意識するだけで、再発リスクを大きく減らせます。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
整骨院に通うメリット

自宅でのケアだけでは限界があります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、
・炎症や筋緊張の程度を見極めながら、安全に施術
・再発しやすい姿勢や歩き方の分析
・その人に合った運動指導
を行うため、「もう治ったけど不安」な状態に最適なサポートができます。
まとめ:違和感のうちにケアすることが最大の予防
ぎっくり腰の痛みが落ち着いても、「違和感」や「重さ」が残るのは珍しくありません。そのまま放っておくと、再発や慢性化につながります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉・関節・姿勢のバランスを整えることで、「再び腰痛に悩まされない体づくり」をサポートしています。早めのケアが、再発予防への一番の近道です。「なんとなくおかしい,,,」と感じたら、それが身体のサイン。放置せず、お気軽にご相談ください。


歯の食いしばり 千歳市の青葉鍼灸整骨院

歯の食いしばりで首が痛いあなたへ
~顎から首へのつながりと、整骨院でできるケア~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「朝起きたら首がこわばっている」「デスクワーク中に首や肩が張る」「歯医者で”食いしばりが強い”と言われたことがある」ーーそんな方は、歯の食いしばり(ブラキシズム)が首の痛みの原因かもしれません。
歯の食いしばりは、単に”歯や顎の問題”にとどまらず、首・肩・背中まで影響を及ぼす全身の不調の引き金になることがあります。今回は、その理由と整骨院での対処法、日常でできるケアを解説します。
歯の食いしばりとは?

歯の食いしばりは、無意識のうちに上下の歯を強く嚙合わせる癖のことを指します。特に寝ている間や、集中している時(パソコン作業・スマホ操作・車の運転など)に多く起こります。
咀嚼筋(咬筋・側頭筋など)が過剰に緊張し、顎関節や首の筋肉にもストレスがかかることで、首の凝りや痛みにつながるのです。
どれくらいの人が「食いしばり」をしているのか?

実は、この食いしばりはとても身近な現象です。
・世界的調査によると、ブラキシズム(食いしばり+歯ぎしり)の有病率は約22.2%。(リンク)
・睡眠中の歯ぎしりに限ると、一般人口の約8%にみられるという報告もあります。(リンク)
・日中の食いしばりは、約15.4%の人にみられるとの調査もあります。(リンク)
つまり、5人に1人以上が「食いしばり」に関係する筋緊張を抱えているのです。整骨院で首や肩こりの相談に来られる方の中にも、無意識に歯を噛みしめている方が非常に多くみられます。
なぜ食いしばりで首が痛くなるのか?
顎(あご)と首は、筋肉・神経・骨格的に密接に関係しています。顎の筋肉に力が入り過ぎると、その緊張は首の筋肉や神経にまで波及しておきます。
①顎の筋肉と首の筋肉は”つながっている”
食いしばりのとき最も働く「咬筋」「側頭筋」は、頭蓋骨や下顎骨を介して首周辺の筋膜と連動しています。特に「胸鎖乳突筋」「斜角筋」「僧帽筋上部」といった首まわりの筋肉が引っ張られ、首のこわばりや痛みを感じる原因になります。
②頭の位置が前にずれる
食いしばりが強い人は、顎関節や側頭部の筋緊張で頭が前方へ引っ張られやすくなります。頭は約5~6㎏あり、わずかに前へでるだけで首への負担は2~3倍に。そのため、”ストレートネック”のような首の筋疲労が起きやすくなるのです。
③自律神経・ストレスの関係
食いしばりは、精神的なストレスや緊張状態とも深く関係しています。ストレスがかかると、交感神経が優位になり、体が「防御反応」として筋肉を固めようとします。この時に、顎を無意識に噛みしめてしまい、結果的に首にも力が入りっぱなしになるのです。
首の痛みを悪化させる要因
・長時間のデスクワーク
・スマホ姿勢(うつむき姿勢)
・枕の高さが合っていない
・寝ている時の歯ぎしり・食いしばり
・ストレスによる顎の過緊張
これらが重なると、首から肩にかけて慢性的な張りが残り、朝起きても疲れが取れない・肩が回らない・頭痛が出るといった症状につながることもあります。
整骨院での施術:食いしばりによる首痛へのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、ただ首をマッサージするのではなく、「顎・頭・首のつながり」を重視して施術を行います。
①咀嚼筋・顎関節の調整
まず、顎を動かす筋肉(咬筋・側頭筋・内側翼突筋など)を優しく緩めます。強く押すと逆に緊張が強まるため、ゆっくりと深部を解放するリリースが効果的です。
②首~肩の筋肉を整える
胸鎖乳突筋・僧帽筋・肩甲挙筋など、顎の影響を受けやすい筋群の緊張をとり、頸椎(首の骨)の動きを回復させます。首の可動域が戻ると、顎の動きも軽くなります。
③姿勢・頭の位置を改善
頭が前に出過ぎている方には、胸を開き、肩甲骨を安定させる施術・運動を組み合わせます。「姿勢が整う=首の負担が減る=食いしばりも減る」という好循環を作ることが目的です。
④自律神経の調整
リラックスを促す手技で、自律神経のバランスを整えます。緊張状態が緩むと、自然とあごの力みも減っていきます。
自宅でできるケア方法
整骨院の施術とあわせて、次のような習慣を意識しましょう。
1.日中は上下の歯を話す意識を持つ
「上下の歯は軽く離れているのが正常」です。
2.あごを緩めるマッサージ
頬のエラ部分(咬筋)を指で優しく円を描くようにほぐします。強く押さないように注意。
3.首のストレッチを習慣に
首を左右に傾ける・ゆっくり回すなど、30秒ずつ行いましょう。
4.睡眠環境の見直し
枕の高さを調整し、頭が前に出ない姿勢で寝ることが大切です。
5.ストレスケアを取り入れる
深呼吸、散歩、軽い運動などでリラックス時間を確保しましょう。
まとめ:顎をゆるめると、首も軽くなる
歯の食いしばりが強いと、首や肩の筋肉は常に緊張した状態になります。そのまま放っておくと、首の痛みだけでなく、頭痛・顎関節症・肩こり・めまいなどへ広がることもあります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、顎と首の両方にアプローチし、全身のバランスを整える施術を行います。「歯を食いしばる癖がある」「首の痛みが取れない」と感じたら、早めのケアが再発防止のカギです。首の痛みを根本から軽くしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。”噛みしめない体”をつくることが、健康な首と笑顔を守る第一歩です。


体を捻ると胸が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

体を捻ると胸が痛くなる方へーー交通事故後にみられる胸の痛みの原因と対処法
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
体を捻ると胸が痛い,,,それ、放置して大丈夫?
日常生活の中で、体を少し捻っただけで「胸の辺りがズキッと痛む」という経験をしたことはありませんか?特に、交通事故後にこのような症状が現れる方は少なくありません。
事故直後は大きなケガが無いように見えても、数日後~数週間経ってから「胸の痛み」や「動作時の違和感」が出るケースが多く、放置すると慢性化することもあります。この記事では、整骨院の視点から、交通事故後に体を捻ると胸が痛くなる原因と、その改善方法を詳しく解説します。
交通事故後の胸の痛みーーなぜ起きるのか?

交通事故では、シートベルトや衝撃によって体が一瞬で大きく前後・左右に振られます。この際、胸の前面・肋骨周囲・胸椎(背中側)には大きな負担がかかり、次のような損傷や緊張が起こることがあります。
①肋間筋の損傷・炎症
肋骨と肋骨の間にある筋肉が「肋間筋」です。呼吸や体幹の動きに深く関与しており、捻る動作や深呼吸で痛みを感じやすくなります。事故でシートベルトが強く胸を圧迫したり、衝撃で体幹が捻じられるとこの筋肉が損傷し、痛みの原因となります。
②胸椎の可動性低下
背骨の胸の部分(胸椎)は、体幹をねじる動きの中心です。交通事故の衝撃により、胸椎周囲の筋肉が防御反応として固まると、関節の動きが悪くなり、無理に体をねじった時に鋭い痛みが出ることがあります。
③肋骨の微細なひびや軟部組織損傷
目にみえる骨折がなくても、肋骨に「骨膜炎」や「微細なひび」が入っている場合があります。特にシートベルトが強く食い込んだ場合は要注意です。
実は多い「交通事故後の胸部痛」
日本国内では、交通事故による負傷者数は毎年30万人を超えています。その中でも胸部の痛みを訴える人は意外と多いのです。
・統計①:警察庁の交通事故統計によると、令和5年の交通事故負傷者のうち、体幹部(胸・腹部)に損傷を受けた人は全体の約15%を占めています。(リンク)
・統計②:日本整形外科学会の調査では、交通事故後に胸部・肋骨周辺の痛みを訴える人の約60%が筋・軟部組織損傷によるものとされています。(リンク)
・統計③:自賠責保険損害調査会の報告では、交通事故後3カ月以上続く胸部痛を訴える被害者が全体の約18%にのぼることが示されています。(リンク)
これらの数字からも、胸の痛みは決して珍しい症状ではなく、筋肉や骨の損傷が見逃されやすい部位であることがわかります。
整骨院でのアプローチーー胸の痛みを和らげる治療とは

交通事故後の胸の痛みは、単なる「筋肉痛」や「打撲」として処理されがちですが、実際には胸椎や肋骨周囲の機能障害を伴うことが多いです。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、以下のようなステップで丁寧に改善を目指します。
①評価(問診・触診・動作分析)
まず、どの動きで痛みが出るかを確認します。「体を右に捻じると痛い」「深呼吸で胸の奥が痛む」など、痛みの出るパターンを特定し、肋間筋・胸椎・肩甲骨周囲など、関連部位を細かく触診します。
②手技療法(筋肉と関節の調整)
筋緊張が強い場合は、肋間筋や胸椎周囲の筋肉を優しく緩める手技を行います。胸郭の可動性を取り戻すように、肩甲骨や背中の動きを丁寧に調整することもポイントです。
③姿勢・呼吸の改善
胸郭の動きが悪いと呼吸が浅くなり、回復が遅れます。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、呼吸と姿勢の連動を意識したリハビリやストレッチも指導しています。特に「肩をすくめない呼吸」「胸を開くストレッチ」は胸の痛み改善に効果的です。
自宅でできるセルフケア
軽度の痛みの場合、整骨院での治療とあわせて次のセルフケアも有効です。
・胸を開くストレッチ(両手を後ろで組んで軽く胸を張る)
・深呼吸トレーニング(3秒吸って、5秒で吐く)
・体幹ねじり運動(痛みのない範囲で左右に回旋)
ただし、「動かすと痛みが強くなる」「呼吸が浅くて苦しい」などの症状がある場合は、自己判断せず早めに整骨院や医療機関を受診してください。
まとめ:交通事故後の胸の痛みは、早期ケアが回復のカギ
交通事故後に体をねじると胸が痛いという症状は、筋肉や関節、肋骨など複数の要因が関わる複雑な痛みです。一見軽症に思えても、放っておくと慢性化して姿勢や呼吸のクセまで変えてしまうこともあります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉・関節・呼吸の3つを整えることで、再発しにくい体づくりを目指せます。「時間が経てば治るだろう」と思わず、少しでも痛みや違和感を感じたら、早めに相談してみてください。
あなたの胸の痛みが1日も早く改善され、安心して日常生活に戻れるよう、私たち整骨院が全力でサポートいたします。