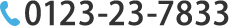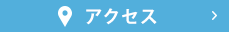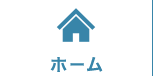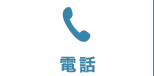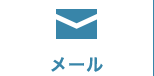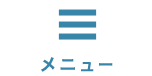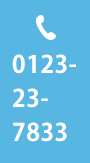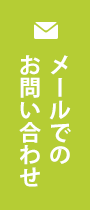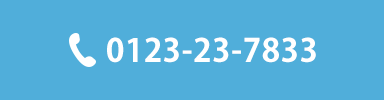体を捻ると胸が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

体を捻ると胸が痛くなる方へーー交通事故後にみられる胸の痛みの原因と対処法
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
体を捻ると胸が痛い,,,それ、放置して大丈夫?
日常生活の中で、体を少し捻っただけで「胸の辺りがズキッと痛む」という経験をしたことはありませんか?特に、交通事故後にこのような症状が現れる方は少なくありません。
事故直後は大きなケガが無いように見えても、数日後~数週間経ってから「胸の痛み」や「動作時の違和感」が出るケースが多く、放置すると慢性化することもあります。この記事では、整骨院の視点から、交通事故後に体を捻ると胸が痛くなる原因と、その改善方法を詳しく解説します。
交通事故後の胸の痛みーーなぜ起きるのか?

交通事故では、シートベルトや衝撃によって体が一瞬で大きく前後・左右に振られます。この際、胸の前面・肋骨周囲・胸椎(背中側)には大きな負担がかかり、次のような損傷や緊張が起こることがあります。
①肋間筋の損傷・炎症
肋骨と肋骨の間にある筋肉が「肋間筋」です。呼吸や体幹の動きに深く関与しており、捻る動作や深呼吸で痛みを感じやすくなります。事故でシートベルトが強く胸を圧迫したり、衝撃で体幹が捻じられるとこの筋肉が損傷し、痛みの原因となります。
②胸椎の可動性低下
背骨の胸の部分(胸椎)は、体幹をねじる動きの中心です。交通事故の衝撃により、胸椎周囲の筋肉が防御反応として固まると、関節の動きが悪くなり、無理に体をねじった時に鋭い痛みが出ることがあります。
③肋骨の微細なひびや軟部組織損傷
目にみえる骨折がなくても、肋骨に「骨膜炎」や「微細なひび」が入っている場合があります。特にシートベルトが強く食い込んだ場合は要注意です。
実は多い「交通事故後の胸部痛」
日本国内では、交通事故による負傷者数は毎年30万人を超えています。その中でも胸部の痛みを訴える人は意外と多いのです。
・統計①:警察庁の交通事故統計によると、令和5年の交通事故負傷者のうち、体幹部(胸・腹部)に損傷を受けた人は全体の約15%を占めています。(リンク)
・統計②:日本整形外科学会の調査では、交通事故後に胸部・肋骨周辺の痛みを訴える人の約60%が筋・軟部組織損傷によるものとされています。(リンク)
・統計③:自賠責保険損害調査会の報告では、交通事故後3カ月以上続く胸部痛を訴える被害者が全体の約18%にのぼることが示されています。(リンク)
これらの数字からも、胸の痛みは決して珍しい症状ではなく、筋肉や骨の損傷が見逃されやすい部位であることがわかります。
整骨院でのアプローチーー胸の痛みを和らげる治療とは

交通事故後の胸の痛みは、単なる「筋肉痛」や「打撲」として処理されがちですが、実際には胸椎や肋骨周囲の機能障害を伴うことが多いです。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、以下のようなステップで丁寧に改善を目指します。
①評価(問診・触診・動作分析)
まず、どの動きで痛みが出るかを確認します。「体を右に捻じると痛い」「深呼吸で胸の奥が痛む」など、痛みの出るパターンを特定し、肋間筋・胸椎・肩甲骨周囲など、関連部位を細かく触診します。
②手技療法(筋肉と関節の調整)
筋緊張が強い場合は、肋間筋や胸椎周囲の筋肉を優しく緩める手技を行います。胸郭の可動性を取り戻すように、肩甲骨や背中の動きを丁寧に調整することもポイントです。
③姿勢・呼吸の改善
胸郭の動きが悪いと呼吸が浅くなり、回復が遅れます。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、呼吸と姿勢の連動を意識したリハビリやストレッチも指導しています。特に「肩をすくめない呼吸」「胸を開くストレッチ」は胸の痛み改善に効果的です。
自宅でできるセルフケア
軽度の痛みの場合、整骨院での治療とあわせて次のセルフケアも有効です。
・胸を開くストレッチ(両手を後ろで組んで軽く胸を張る)
・深呼吸トレーニング(3秒吸って、5秒で吐く)
・体幹ねじり運動(痛みのない範囲で左右に回旋)
ただし、「動かすと痛みが強くなる」「呼吸が浅くて苦しい」などの症状がある場合は、自己判断せず早めに整骨院や医療機関を受診してください。
まとめ:交通事故後の胸の痛みは、早期ケアが回復のカギ
交通事故後に体をねじると胸が痛いという症状は、筋肉や関節、肋骨など複数の要因が関わる複雑な痛みです。一見軽症に思えても、放っておくと慢性化して姿勢や呼吸のクセまで変えてしまうこともあります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉・関節・呼吸の3つを整えることで、再発しにくい体づくりを目指せます。「時間が経てば治るだろう」と思わず、少しでも痛みや違和感を感じたら、早めに相談してみてください。
あなたの胸の痛みが1日も早く改善され、安心して日常生活に戻れるよう、私たち整骨院が全力でサポートいたします。


座ってると背中痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

座っていると背中が痛くなる人へ~整骨院が教える原因と対処法~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
仕事中や車の運転、食事の時間など、「座っている時間」は現代人の生活の多くを占めています。ところが、その座るという動作が続くことで「背中が痛い」「背もたれにもたれるとピリッとする」「姿勢を変えないと落ち着かない」といった悩みを感じている方が少なくありません。今回の記事では、座っていると背中が痛くなる原因と、整骨院での対処法、日常でできるケアについて解説します。
背中・腰痛の実態を知る

背中や腰の痛みは、世界的に見ても非常に多い症状の一つです。世界保健機関(WHO)の報告によると、2020年時点で約6億1,900万人が腰痛を経験しており、2050年には8億4,300万人に増加すると推定されています。(リンク)
また、日本の研究では、慢性痛を抱える人のうち58.6%が「背中下部(腰部)」に痛みを感じているという結果が出ています。(リンク)
さらに、成人を対象にした国際的な調査では、20~59歳の約19.6%が慢性的な腰痛を持つと報告されており、もはや「腰・背中の痛み」は誰にでも起こりうる身近な問題です。(リンク)
座っていると背中が痛くなる主な原因

デスクワークやスマホ操作で背中が丸くなると、背骨を支える筋肉(脊柱起立筋・菱形筋・僧帽筋など)に過剰な負担がかかります。特に頭が前に出た「ストレートネック姿勢」は、首から背中まで連鎖的に張りを生みやすくなります。
同じ姿勢を長時間続けると、筋肉が収縮しっぱなしになり、血流が悪化します。筋肉内の酸素不足が「だるさ」や「痛み」の原因になります。特に肩甲骨まわりの動きが減ると、背中の凝りが強く出やすくなります。
椅子の高さ、背もたれの角度、モニター位置が合っていないと、一部分だけに負担が集中します。たとえば、机が高すぎると肩が上がり、結果的に背中上部に張りが出ることもあります。
腹筋や背筋などの「姿勢を保つ筋肉(コア)」が弱いと、正しい姿勢を維持できず、背中の表層筋が頑張り過ぎて痛みを起こします。特に多裂筋や腹横筋の機能低下は、長時間座位の不快感と深く関係しています。
精神的ストレスは筋肉の緊張を高め、血流を悪化させるため、同じ姿勢でも痛みを感じやすくなります。深呼吸やリラックスできる環境づくりも重要です。
整骨院で行う主な施術と効果

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、背中の痛みを単に「揉む」ではなく、原因を特定しながら全身のバランスを整えます。
〇筋肉・筋膜の調整
硬くなった筋肉を手技で緩め、血流を促進します。特に肩甲骨周囲や腰背部を柔らかくすることで、痛みの原因を根本から軽減します。
〇背骨・骨盤のアライメント調整
背骨や骨盤の歪みがあると、座っている時に左右どちらかへ傾くなどの癖が出やすくなります。それによって、使いずらくなっている・支えにくくなっている筋肉には、刺激を入れて動かし、バランスよく自分でコントロールできる体にしていきます。
〇体幹・姿勢指導
腹筋・背筋のバランスを整える運動指導を行い、正しい姿勢を保つ筋肉を再教育します。再発予防のためには、痛みが取れた後の「姿勢維持力アップ」が不可欠です。
〇生活環境のアドバイス
椅子や机の高さ、モニターの位置、クッションの選び方などを具体的にアドバイスし、背中にかかる負担を減らすサポートを行います。
自宅でできるセルフケア

整骨院での施術と並行して、自宅でも以下のような習慣を取り入れることで改善が早まります。
・1時間に1回は立ち上がる
5分程度歩くだけでも背中の筋肉が緩みます。
・肩甲骨ストレッチ
両肘を背中の後ろで寄せるようにして、胸を開くストレッチを1日数回。
・体幹トレーニング
プランクや骨盤の前後運動で腹筋と背筋をバランスよく使う。
・正しい座り方を意識
骨盤を立て、坐骨で座る。背もたれには軽く背中を預ける。
・深呼吸を取り入れる
胸郭を広げるように深呼吸をすると、背中の筋肉の緊張がほぐれます。
放置するとどうなる?

「座っていると背中が痛い」という状態を放置すると、背中だけでなく、肩こり・腰痛・頭痛・手の痺れなど、他の部位にも影響が出ることがあります。特に、背骨の動きが制限されると、呼吸の浅さや集中力の低下にもつながります。
まとめ~背中の痛みは体のサイン~
座っている時間が長い現代社会では、背中の痛みは「仕方がないもの」ではなく、「改善できるもの」です。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、筋肉・関節・姿勢・生活習慣をトータルで見直し、根本的な原因にアプローチします。「座っていると背中が痛い」と感じたら、無理をせず一度ご相談ください。正しいケアと日常の工夫で、快適な背中を取り戻すことができます。


腰痛をどう対処する 千歳青葉鍼灸整骨院

腰が痛い時、動いた方が良い?それとも安静が良い?
~整骨院が教える、腰痛のタイプ別の見分け方~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
腰が痛くなった時、多くの方が迷うのが「動いた方がいいのか」「安静にした方がいいのか」という判断です。実は、この答えは腰痛のタイプや症状の出方によって異なります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの原因をしっかり見極めたうえで、安静か運動かを判断することがとても大切になります。
今回は、そんな”動くべき腰痛”と”安静を優先すべき腰痛”の見分け方をわかりやすく解説します。
腰痛の現状と統計からみる「動くことの大切さ」

厚生労働省の報告によると、日本人の約83%が一生に一度は腰痛を経験するとされています。(労働者健康安全機構リサーチ)
さらに、1ヵ月以内に腰痛を感じた人の割合は35.6%にものぼり、職場や家庭生活に支障をきたしている人も多いとされています。(アーケリス統計データ)
また、慢性痛(3か月以上続く痛み)として腰痛を訴える人は全体の約23%に達しており(労働者健康安全機構リサーチ)、腰痛が「国民病」と呼ばれるのも納得です。
このように腰痛は非常に多い症状ですが、実は8割以上が「非特異的腰痛」といって、明確な原因が特定できないタイプです。
このタイプでは、長く安静にしすぎるよりも、適度に体を動かすほうが回復が早いことが、近年の研究で明らかになっています。
動いた方が良い腰痛とは?

動かした方が良い腰痛の多くは、筋肉や関節のこわばり・姿勢の崩れなどが原因で起こる「非特異的腰痛」です。この場合、筋肉を休ませすぎると血流が悪化し、かえって痛みやこわばりが強くなることもあります。
・発熱やしびれなど、明確な神経症状がない
・動かすと少し痛いが、軽く動かしていると痛みが軽くなる
・長く座り過ぎたりたちっぱなしにした後に痛みが出る
・朝よりも夕方にかけて重だるくなる
このような腰痛は、「安静にしすぎないこと」が大切です。たとえば、軽いストレッチやウォーキング、腰を反らさない程度の股関節周りの運動を行うことで、筋肉の柔軟性が戻り、血流も改善します。
厚生労働省の「腰痛対策ガイドライン」でも、非特異的腰痛では活動性を維持することが推奨されています。また、ベッド上での安静を続けた場合よりも、日常生活の範囲で動いていた人の方が回復が早く、再発もしにくいことが多いと報告されています。
つまり、筋肉性や姿勢性の腰痛では、「痛くない範囲で体を動かす」ことが治療の第一歩になるのです。
安静にした方がいい腰痛とは?
一方で、安静が必要な腰痛もあります。それは、神経や骨、内臓に関係している腰痛です。こうしたタイプを見逃して無理に動くと、かえって症状が悪化するおそれがあります。
・下肢に強い痺れや放散痛(坐骨神経痛など)がある
・足に力が入りにくい、つまずきやすい
・排尿・排便に異常がある
・熱がある、夜中に異常がある
・がん・感染症の既往がある
・痛みが強くて姿勢を変えるのもつらい
これらの症状がある場合は、椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・圧迫骨折・内臓疾患などの可能性があり、安静を優先するか、まずは医療機関で精査が必要です。
特に、下肢のしびれや排尿障害を伴う場合は、緊急性が高いケースもあるため要注意です。
整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、まず腰痛のタイプを見極めるためのカウンセリングと検査を行います。筋肉性か、関節性か、神経性かを評価し、そのうえで「動かすべき腰痛」か「安静を優先すべき腰痛」かを判断します。
・温熱療法や電気治療で血流を改善
・筋膜リリースや手技で筋緊張を緩める
・姿勢・骨盤のバランスを整える
・ストレッチや骨盤周囲の可動域改善
・体幹筋(腹横筋・多裂筋)のトレーニング
・ピラティスなどによる姿勢安定エクササイズ
このように、症状に合わせて段階的に体を動かしていくことで、再発しにくい体づくりを目指します。また、痛みが落ち着いた後も「正しい動かし方」を身につけることが、腰痛を繰り返さないためのポイントです。
まとめ
腰痛と一口に言っても、「動かすべき腰痛」と「安静にすべき腰痛」は全く別物です。明確な神経症状や強い痛みがある場合は無理をせず安静を保つことが大切ですが、そうでない場合、じっとしすぎることが痛みを長引かせる原因にもなります。
痛みが出た時は、
1.「しびれ」「力が入らない」「熱がある」などの危険サインがないか確認する
2.症状が軽ければ、痛くない範囲で少しずつ体を動かす
3.判断が難しい場合は、整骨院や専門医でチェックしてもらう
この3つを意識してみて下さい。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたの腰痛のタイプを見極めながら、治療と運動のバランスを考えたサポートを行っています。「安静が良いのか、動いた方が良いのかわからない」ときは、是非一度ご相談ください。


走る時の背中・腰痛 千歳青葉鍼灸整骨院

走ると背中や腰が痛くなるランナーへ:原因と整骨院での改善法
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
ランニングは心肺機能の向上やストレス解消、体力維持に効果的な素晴らしい運動です。しかし、走っていると「背中や腰が痛くなる」という悩みを抱えるランナーは少なくありません。トレーニングを続けたいのに痛みが出てしまうーーそんな時は、単なる疲労ではなく、体のバランスや使い方に問題がある可能性があります。
今回の記事では、ランニング時の「背中や腰の痛み」の原因や、整骨院で行う改善アプローチ、セルフケアの方法をわかりやすく解説します。
ランナーに多い背中・腰の痛みの実態

ランニングによる腰痛・背部痛は、特に長距離ランナーに多く見られる症状です。ある調査では、ランナーの約30~40%が腰や背中に痛みを感じた経験があると報告されています。(リンク)
さらに、ランニング障害の中で腰背部痛は「膝」「足首」に次いで第3位に位置するとされており、単なる筋肉痛ではなく、繰り返される衝撃やフォームの問題が関係していることがわかります。(リンク)
また、長時間座る仕事をしているランナーでは、腰痛リスクが約2倍という研究報告もあり、日常生活の姿勢がランニング中の痛みに影響していることが示されています。(リンク)
背中・腰が痛くなる主な原因

走ると背中や腰が痛くなる原因はいくつかありますが、整骨院でよくみられる代表的な要因を紹介します。
①骨盤・体幹のバランス不良
ランニングは左右交互に足を動かすため、骨盤の安定性が非常に重要です。骨盤が前傾または後傾しすぎていると、背骨の動きが制限され、腰椎や胸椎に負担が集中します。特に、デスクワークなどで猫背姿勢が続いていると、骨盤が後傾し、背中や腰の筋肉が硬くなりやすくなります。
②体幹の筋力不足
腹筋群(特に腹横筋や多裂筋)が弱いと、走行中に骨盤が安定せず、背骨に捻れが生じます。結果として、腰部の筋肉(腰方形筋や脊柱起立筋など)が過剰に働き、痛みを感じやすくなります。
③呼吸と姿勢の乱れ
ランニング中に呼吸が浅くなり、肩や背中の筋肉が常に緊張していると、胸椎や肋骨の可動性が低下します。呼吸が浅い状態では、体幹の安定性も下がり、結果的に腰への負担も増します。
④シューズやフォームの問題
クッション性の低下したシューズや、ヒールストライク(かかと接地)の強い走り方も衝撃を増やし、腰背部へダメージを与えます。着地時の衝撃吸収ができていないと、筋肉だけで支えることになり、痛みが慢性化するケースもあります。
整骨院での治療・改善アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの根本的な原因を見極め、以下のような施術を組み合わせて改善を図ります。
①骨盤・脊柱のバランス調整
手技やエクササイズなどによって骨盤や背骨の歪みを整え、体幹の安定性を取り戻します。これにより、ランニングフォームがスムーズになり、再発予防にもつながります。
②筋肉の緊張を緩める
特に硬くなりやすいのは、腰方形筋、脊柱起立筋、広背筋です。手技療法やストレッチで筋肉の柔軟性を回復させ、血流を促進することで痛みを軽減します。
③呼吸と姿勢の再教育
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、胸郭の動きを引き出す「呼吸リハビリ」や、骨盤を中心とした姿勢指導も行います。「走る前の呼吸トレーニング」で体幹を安定させることにより、背中や腰への負担を減らすことができます。
④自宅でできるストレッチ・エクササイズ指導
整骨院での施術に加えて、自宅で簡単にできる体幹トレーニングやストレッチを取り入れると、改善スピードが上がります。
自分でできるセルフケア方法
〇腰方形筋ストレッチ
椅子に座って片手を頭の上に伸ばし、体をゆっくり反対側に倒します。腰の横や背中の筋肉がじんわり伸びるのを感じましょう。
〇胸郭ストレッチ
両手を胸の前で組み、背中を丸めながら大きく息を吸う。この動きを5回繰り返すことで、呼吸と姿勢が整います。
〇骨盤の安定トレーニング
仰向けで膝を立て、軽くお腹を引き込んだまま骨盤を小さく前後に動かします。体幹を意識して「腰を反らさない」ように行うのがポイントです。
まとめ:痛みを我慢せず、体の使い方を見直そう
走っていると背中や腰が痛くなるのは「頑張り過ぎ」ではなく「使い方のずれ」が原因であることが多いです。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの根本を探り、あなたの体の特徴に合わせた治療と運動指導を行います。
ランニングを長く続けるためには、「痛みを我慢せず、早めにケアする」ことが大切です。背中や腰の違和感を感じたら、是非一度ご相談ください。


咳で肩が痛くなる 千歳青葉鍼灸整骨院

咳やくしゃみで肩まわりが痛い,,,その原因と整骨院での対処法
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「風邪をひいて咳をしたら肩がズキッと痛む」「くしゃみをした瞬間、背中がピキッとした」「呼吸するだけで肩が重だるい」ーー。このような症状を感じたことはありませんか?
実は、咳やくしゃみで肩や背中に痛みが出るのは珍しい事ではなく、筋肉や関節に負担がかかっているサインです。特に、季節の変わり目や冷え込みが強くなる時期には、体の緊張や筋肉の硬さが増し、痛みが出やすくなります。
今回は、咳やくしゃみで肩まわりが痛くなる原因と、整骨院で行う治療・予防方法について詳しくお伝えします。
肩や背中の痛みは意外と多い
咳やくしゃみで起きる肩まわりの痛みは、一時的な筋肉のけいれんや炎症が関係していることが多いですが、実はこうした「筋骨格系の痛み」はとても身近なものです。
いくつかの統計を見てみましょう。
1.肩の痛みを感じたことがある人の割合は全体の約20%前後。
肩の有病率はおおよそ18~26%、年間発症率は0.9~2.5%と報告されています。(リンク)
2.仕事や家事などで肩の不調を感じた人は約3人に1人。
約2万人の調査で、1年以内に肩の痛みを経験した人は35.5%でした。(リンク)
3.胸の痛みのうち、筋肉や肋骨など”筋骨格性”が原因のものは約16%。
呼吸や姿勢、動作に関連して起こる痛みも多いことがわかります。(リンク)
このように、肩や背中の痛みは誰にでも起こりうる症状で、咳やくしゃみといった日常の小さな動作が引き金になることも少なくありません。
咳やくしゃみで痛みが出る理由

咳やくしゃみは、一瞬で強い圧力を胸郭(胸の骨格)や背中にかける動作です。その際、肩甲骨や肋骨を動かす筋肉、胸の前の筋肉(大胸筋や小胸筋)、背中の僧帽筋や広背筋などが大きく動きます。
この動作で痛みが出る主な原因はつぎのようなものです。
咳やくしゃみの瞬間、胸郭が強く引き伸ばされ、肩や背中の筋肉に急な張力が加わります。筋肉が硬かったり疲労していると、この一瞬の負荷で炎症や筋膜の引きつれを起こすことがあります。
肩や背中の筋膜が硬く動きづらくなっていると、呼吸動作のたびに摩擦が生じ、痛みを感じやすくなります。筋膜リリースなどで滑りを回復させることが重要です。
胸周りの関節(胸椎・肋骨)が硬くなると、咳やくしゃみの力が一部に集中します。結果として肩甲骨や背中の筋肉が過緊張を起こし、痛みに繋がります。
猫背や巻き肩、ストレートネックの姿勢が続くと、肩や胸の筋肉は常に引っ張られています。その状態でくしゃみをすれば、筋肉がさらに過度に引き伸ばされ、痛みが起こりやすくなります。
これから寒くなる季節は、筋肉が冷えて硬くなりやすい時期。血流が悪くなることで筋肉が弾力を失い、わずかな衝撃でも痛みを感じやすくなります。
整骨院での治療アプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、まず痛みが出ている箇所を正確に特定し、「どの筋肉が原因か」、「どんな動きで痛みが出るか」を丁寧に評価します。
〇手技療法・筋膜リリース
筋肉の緊張を緩め、肩甲骨や肋骨の動きをスムーズにすることで、咳やくしゃみの衝撃を分散できる体に整えます。
〇温熱療法
冷えた筋肉を温めて血流を促進。痛みの回復を早めるとともに、今後の再発予防にも効果的です。
〇関節可動域改善
胸椎や肋骨、肩甲骨の可動性を高め、呼吸時の動きが滑らかになるように手技やエクササイズを入れて調整していきます。
〇姿勢改善・呼吸指導
猫背や巻き肩を整え、正しい呼吸の仕方を習得することで、再発を防ぎやすくなります。特に横隔膜をしっかり動かす呼吸法は、肩や首への負担を軽減します。
セルフケアと予防のポイント

自宅でも次のようなケアを意識することで、痛みの再発を防ぎやすくなります。
・胸を開くストレッチ:両手を後ろで組み、肩甲骨を寄せるようにして胸をひろげる
・肩甲骨の運動:背伸びをするように肩を上げ下げし、肩甲骨の動きを感じる
・温めケア:就寝前に肩や背中を温め、血行を良くする
・呼吸トレーニング:スマホやデスク作業の姿勢をこまめに見直す
また、咳やくしゃみのときは体を少し前に倒して腹部を支えるようにし、肩や背中に直接衝撃が伝わらないようにするといいでしょう。
整骨院からのメッセージ
咳やくしゃみで肩や背中に痛みが出るのは、「体のどこかが硬くなり、動きのバランスが崩れている」サインです。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの根本を探りながら、筋肉の柔軟性を回復させ、関節の動きを整えていくことで、再発しにくい体へ導くことができます。
「風邪をひくたびに肩が痛くなる」「季節の変わり目に体がこわばる」という方は、是非一度ご相談ください。痛みを我慢せず、呼吸が楽にできる身体作りを一緒に目指しましょう。


体が硬い人には! 千歳青葉鍼灸整骨院

体が硬い人ほど、整骨院で「動ける体」をつくろう!
~治療+ピラティスで柔軟性を取り戻す~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「昔から体が硬くて、前屈しても手が床につかない」「ストレッチをしても全然伸びない」「肩や腰がすぐに張ってしまう」
そんな悩みを持つ人は多く、実は年齢に関係なく増えています。体が硬いというのは単に「柔らかくない」だけではなく、筋肉や関節、筋膜が動きにくくなり、姿勢や痛みにまで影響する状態です。
今回は、整骨院での治療とピラティス運動を組み合わせて、体の硬さを改善していく方法についてお話しします。
体が硬いと起こる問題とは?

柔軟性の低下は、日常生活の中でさまざまな不調を引き起こします。
まず、筋肉や関節の動きが悪くなると、動作中に”代償動作”が起きやすくなります。たとえば、股関節が硬いと、前屈の時に腰を過剰に曲げてしまい、結果として腰痛が出やすくなります。
また、可動性の低下は筋や腱の負担を増やし、スポーツでは肉離れや捻挫などのリスクを高めます。日常でも、つまずきや転倒、肩こり、慢性腰痛の原因となることもあります。
柔軟性と健康の関係については、次のような報告もあります。
・柔軟性が高い人ほど、長期的に健康リスクが低い傾向があるとの研究があります。(リンク)
・医療系学生を対象とした調査では、ハムストリングスの硬さを持つ人が38%に上るとの報告もあり、若い世代でも柔軟性不足が多いことが分かっています。(リンク)
・柔軟性トレーニングを行っている人は、日常的な痛みや疲労感が少ない傾向にあるという調査結果も報告されています。(リンク)
こうした統計からも、「硬いカラダをそのままにする」ことは健康にも悪影響を及ぼすと考えられます。
整骨院でのアプローチ:治療と運動の両立

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、体の硬さを改善するためにまず「動きを制限している原因」を探ります。単にストレッチをしても伸びにくい場合は、筋肉や関節の深層部で癒着や硬さが生じていることが多いからです。
①手技療法(治療)
・関節モビライゼーション(関節をゆっくり動かす手技)
・筋膜リリースやトリガーポイント療法
・血流促進を目的とした手技
これらの施術で筋・関節・筋膜の動きを整えることで、ストレッチや運動の効果が出やすい状態をつくります。
②運動療法(ピラティス)
次のステップで取り入れるのがピラティスです。ピラティスは、呼吸を意識しながら体幹を安定させ、関節の動きを滑らかにするエクササイズ。低負荷で安全に行えるため、体が硬い方にも非常に向いています。
・ピラティスは柔軟性と筋持久力を改善するという研究結果があります。(リンク)
・ダンサーを対象にした研究でも、ピラティスによって筋力と柔軟性が両方改善したと報告されています。(リンク)
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、施術で可動域を広げた後にピラティスで「動ける体」をつくることで、再び硬く戻らないようにサポートします。
ピラティスで変わる体の感覚
ピラティスを取り入れると、最初の数回で「体の動かしやすさ」や「姿勢の安定感」が変わったと感じる方が多くいます。これは、ただ筋肉を伸ばしているのではなく、”使えていなかった筋肉”を目覚めさせているからです。
たとえば、
・股関節の動きが悪い人は、お尻(大殿筋・中殿筋)をうまく使えずに腰を反りやすい
・胸が硬い人は、呼吸が浅くなり、肩や首に力が入りやすい
ピラティスでは、こうした「使えていない部分」を呼吸と一緒に動かし、体の連動性を取り戻していきます。結果として、筋肉が伸びやすくなり、ストレッチの効果も持続しやすくなるのです。
整骨院での進め方(例)
1.評価とカウンセリング
どの動きで硬さが出るのか、姿勢や関節可動域をチェック。
2.施術で下地をつくる
筋膜・関節・神経周囲の癒着を緩め、可動性を取り戻す。
3.ピラティスで体幹を安定化
呼吸を使いながら、動きの中で柔軟性を高める。
4.自宅ストレッチ・セルフケア指導
簡単に続けられる体操や姿勢の工夫をアドバイス。
5.定期チェック
硬さが戻らないよう、数週間ごとに動作を確認。
硬いカラダは「変わる」
「体が硬いのは生まれつき」と諦めてしまう人もいますが、実際は”動かしていない時間の積み重ね”によるものがほとんどです。整骨院で治療を受け、ピラティスのような正しい運動を続けることで、筋肉と関節は必ず反応してくれます。
可動域が広がれば、姿勢も変わり、疲れにくく、ケガのしにくい体になります。今からでも遅くありません。体の硬さを改善し、「動ける快適な体」を一緒に目指していきましょう。


荷物作業で肘痛い 千歳青葉鍼灸整骨院
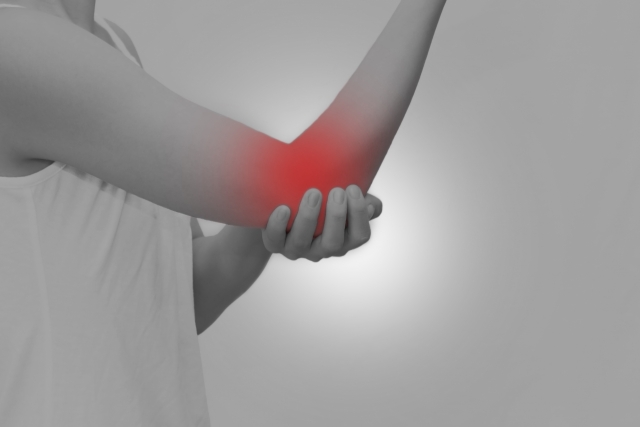
荷物の上げ下ろし作業で肘を痛めてしまった方へ
~繰り返し動作による肘の負担と整骨院でできるケア~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
仕事で荷物を持ち上げたり、運んだりを繰り返しているうちに「肘の外側がズキッと痛い」「荷物を持った時に力が入らない」と感じたことはありませんか?それは単なる疲れではなく、肘の腱(けん)に負担がかかっているサインかもしれません。
肘は「曲げる」「伸ばす」だけでなく、手首や肩と連動して細かい動きを支えています。日常ではあまり意識されない部分ですが、重い荷物の上げ下ろしを繰り返す仕事では、肘へのストレスが積み重なりやすいのです。
今回は、そんな「荷物作業で肘を痛めた方」に向けて、原因・治療・予防のポイントをわかりやすく解説します。
肘を痛める人は意外と多い!~統計でみる肘のトラブル~

肘の腱や筋肉を痛める症状は、スポーツ選手だけでなく、日常的に手を使う仕事の人にも多く発生しています。
1.職業労働者の肘障害の発症率
研究によると、仕事で腕をよく使う人の年間発症率は、男性で約1.0%、女性で0.9%と報告されています。繰り返し動作や重作業が発症リスクを高めることがわかっています。(リンク)
2.反復作業との関係性
肘の外側が痛くなる「外側上顆炎(いわゆるテニス肘)」は、手首や前腕を繰り返し使う作業者に多く、職業性の要因が大きいと報告されています。(リンク)
3.内側の肘痛(ゴルフ肘)も増加傾向
組立作業などで同じ動作を続ける作業者のうち、約3.2%が肘の内側に痛みを抱えていたという報告もあります。(リンク)
つまり、肘の痛みは誰にでも起こりうる職業病のひとつ。特に荷物の上げ下ろしなどで「腕を伸ばした状態で重いものを扱う」動作を繰り返すと、腱や筋肉の微小な損傷が蓄積し、痛みが慢性化してしまうこともあります。
なぜ荷物作業で肘を痛めるのか?

肘の痛みの多くは、肘の外側(または内側)にある腱の炎症や変性が関係しています。この腱は、前腕の筋肉と骨をつないでおり、手首や指を動かすたびに引っ張られます。重い荷物を持ち上げるとき、手首を反らす(背屈)動作が多くなり、非所の外側に強い張力がかかるのです。
さらに、以下のような要因も痛みを悪化させます。
・肘を伸ばしたまま荷物を持つクセ
・手首を過度に使う作業姿勢
・前腕や肩の筋肉が硬く、動きが悪い
・作業中の疲労回復が追い付いていない
・力の使い方に偏りがある(片腕に頼るなど)
最初は「違和感」や「重だるさ」程度でも、放置していると腱に細かい断裂が生じ、慢性的な炎症へと進行することがあります。
整骨院でのアプローチ

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、まず痛みの原因をしっかり評価することから始めます。
①評価・検査
・痛みの出る動作(持ち上げ・下ろす・握るなど)を確認
・肘・前腕・手首・肩の動きや筋肉の緊張をチェック
・腱の炎症や硬さを触診で確認
痛みがどの筋肉・動作からきているのかを見極めることで、無理のない治療プランを立てます。
②炎症期のケア
・アイシング(冷却)で炎症を抑える
・電気療法・超音波治療で深部の回復を促す
・テーピングで腱の負担を軽減する
痛みが強い時期は、無理に動かすより「肘を休ませる」ことが最優先です。
③回復期の施術
・前腕や上腕の筋肉を手技療法で緩める
・肩や背中の動きも整え、肘への負担を分散する
肘の痛みは、実は肩や手首の動きの悪さから来ていることも多く、関連部位を含めた施術が大切です。
自宅や職場でできるセルフケア
整骨院での施術に加えて、自宅でも次のケアを行うことで回復が早まります。
1.軽いストレッチ
痛みのない範囲で前腕を伸ばすストレッチを行いましょう。
2.アイシング(10~15分)
作業後は冷やして炎症を防ぎます。
3.サポーターの使用
肘周囲の圧をコントロールし、腱への負担を軽減。
4.休息を取る勇気
「少しくらい大丈夫」と無理をすると、かえって治りが遅くなります。
再発予防ポイント

・荷物を持つときは両腕で体に近づけるように持つ
・手首だけで持ち上げず、全身で支える意識を持つ
・作業間にストレッチや軽い体操を取り入れる
・睡眠や栄養をしっかり摂り、筋肉の回復を促す
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、これらの姿勢指導や身体の使い方の工夫なども行っています。
まとめ
荷物の上げ下ろしを繰り返すことで起こる肘の痛みは、単なる筋肉痛ではなく「腱障害」であることが多いです。放っておくと慢性化し、仕事や日常動作にも影響が出てしまいます。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの軽減から再発予防までをトータルにサポートします。「痛いけど、仕事だから仕方ない」と我慢せず、早めにご相談ください。適切な施術とセルフケアで、痛みのない快適な毎日を取り戻しましょう。


この時期の肩こり 千歳青葉鍼灸整骨院

寒くとなると肩から首が痛くなる女性へ
~冷えが引き起こす不調と整骨院でのケア~
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
朝晩の空気が冷たくなり、いよいよ秋から冬へと季節が移り替わるこの時期。「肩が重い」「首が凝る」「肩甲骨のあたりが冷えて痛い」と感じていませんか?
寒さを感じると体が自然に縮こまり、血流が悪くなることで、筋肉がこわばりやすくなります。特に女性は、冷えやホルモンバランスの影響で筋肉が硬くなりやすく、寒い時期になると「肩や首の痛み」が強く出やすい傾向があります。
今回は、寒さで肩~首に痛みが出る理由と、整骨院でできる対策・セルフケアについてお伝えします。
寒さで痛みが出る理由
①筋肉が縮むことで血流が悪くなる
寒いと体は熱を逃がさないように筋肉を収縮させます。この状態が続くと血流が低下し、老廃物が溜まりやすくなります。その結果、肩や首の筋肉がこわばり、痛みや重だるさを感じやすくなります。
特に「僧帽筋」や「肩甲挙筋」といった首・肩を支える筋肉は、寒さの影響を強く受けやすい部位です。
②神経の過敏化
寒冷刺激が続くと、皮膚や筋膜の神経が敏感になり、痛みを感じやすくなることがあります。慢性的に肩こりを持っている人は、すでに筋肉内の神経が過敏になっており、寒さによって痛みが増幅しやすい傾向にあります。
③姿勢の影響
寒いと体が前かがみになり、自然と肩がすくみます。この姿勢が続くことで、首~肩~背中の筋肉が常に緊張状態になり、血行不良や神経圧迫を引き起こします。デスクワーク中やスマホ操作の際に「肩が丸まっている」と感じたら、要注意です。
女性は男性に比べて筋肉量が少なく、体を温める代謝が低めです。そのため、寒さによる血行不良の影響を受けやすくなります。また、ホルモンバランスの変化も血流や自律神経に関係し、冷えやすさ・こりやすさに影響します。
実際に、世界的な研究でも女性は男性より首や肩の痛みを感じやすいことが示されています。
・スペインの調査では、女性が慢性頸部痛を訴える割合が有意に高いと報告されています。(リンク)
・世界規模のデータでも、首の痛みの有病率は女性が高い傾向にあります。
・学生を対象とした調査でも、女性学生のほうが首や肩の痛みを訴える割合が高いとされています。(リンク)
つまり、「女性だからこそ起きやすい冷えと痛み」が存在するのです。
整骨院での施術アプローチ

寒さによる痛みは、筋肉や関節、血流、姿勢など複数の要因が重なって起こります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、その人の状態に合わせて次のような施術を行います。
①評価(チェック)
・痛みの出る動き・姿勢を確認
・肩・首、背中の筋緊張を触診
・可動域検査で、動かしにくい関節を確認
根本原因を見極めて、どこに施術を集中させるべきか判断します。
②血流改善と筋肉緩和
・温熱療法(ホットパック・温シップ)で筋肉を温め、血行を促進
・手技療法(筋膜リリース・ストレッチ)でこわばった筋肉を緩める
・電気療法で痛みの伝達を和らげ、回復を促す
冷えによって固まった筋肉をしっかりほぐし、循環を整えることで痛みを軽減します。
③姿勢と可動性の改善
・首や肩甲骨の動きをスムーズにするストレッチ
・胸を開く姿勢改善の指導
・肩甲骨周囲の筋肉(僧帽筋・菱形筋・肩甲下筋など)を柔らかくする施術
正しい姿勢に戻すことで、再発を防ぎやすくなります。
④筋力・安定性トレーニング
・首を支える深層筋(頸部屈筋)の強化
・肩甲骨を安定させる中・下部僧帽筋や菱形筋のトレーニング
・姿勢を支える体幹筋(腹横筋・多裂筋など)のエクササイズ
筋肉のバランスを整えると、寒さによる負担にも耐えられるようになります。
自宅でできるセルフケア
整骨院でのケアと併せて、日常で意識できるポイントも大切です。
〇温める
・肩や首をカイロ・湯たんぽで温める
・入浴時は首までしっかりお湯につかる
・ストール・ネックウォーマーで冷気を防ぐ
〇ストレッチ
・朝起きたときや夜寝る前に、首の前後左右ストレッチ
・肩をゆっくり回す「肩甲骨ほぐし」
・1時間に1回は姿勢を変える
〇姿勢を意識
・スマホを目線の高さに
・デスクワークでは背筋を伸ばし、肩をすくめない
・枕の高さを調整し、首に負担をかけない
小さな意識の積み重ねが、冬の痛み予防につながります。
寒さと痛みに関するデータ

寒冷環境での痛みに関する研究も多く報告されています。
・屋外の寒さにさらされる作業者では、首・肩の痛みの発症率が高いという報告があります。(リンク)
・寒冷曝露が筋骨格系の痛みリスクを上げる可能性を示すレビューも発表されています。(リンク)
天候変化(寒暖差)が痛みを誘発することも報告されています。(リンク)
これらの研究からも、「寒さ」が肩や首の不調を悪化させる要因であることがわかります。
まとめ:寒さに負けない体づくりを
寒くなる季節は、筋肉が縮み、血流が悪くなりやすいため、肩~首の痛みが出やすくなります。特に女性は冷えやホルモンバランスの影響で、痛みが長引きやすい傾向があります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、
・血流改善
・筋肉の緊張緩和
・姿勢・可動域の調整
・筋力バランスの修正
を通して、根本から改善を目指します。
「最近、寒くなって首や肩が辛い」「寝違えたような痛みが続く」
そんな時は、早めにご相談ください。冷えに負けない体を整え、今年の冬を快適に過ごしましょう。


サッカーでの膝痛 千歳青葉鍼灸整骨院

膝の痛みが良くならないサッカー少年へ
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
~なぜ痛みが残るのか?整骨院でできる事~
「練習後に膝が痛む」「休んでも違和感が消えない」「動き出しや方向転換で膝がズキッとくる」ーーサッカーを続けていると、膝の痛みや違和感を抱える選手は決して少なくありません。
特に、痛みが「なかなか良くならない」ケースでは、単なるオーバーユース(使い過ぎ)以上に、体の使い方やバランスの不整、筋力アンバランス、膝関節そのものの状態など複数要因が絡んでいることがあります。
このブログでは、サッカー選手における膝痛の背景と、整骨院での対処・セルフケア・予防法を整理してお伝えします。
膝痛はサッカー少年によくある問題:統計でみる実態

まず、サッカー・若年選手における膝・下肢のケガ傾向を示す統計をいくつか見ておきましょう。
・青年・少年サッカー選手のケガ発生率(男女まとめ)では、年間5.70/1,000時間(男性)/6.77/1,000時間(女性)という報告があります。下肢(膝・足部)は最も傷害が多い部位の1つとされます。
・若年サッカー選手を対象とした学術研究では、外側・内側の脚部傷害の約29.3%が膝関節の部位であるというデータもあります。(リンク)
・パテラ(膝蓋)腱炎(いわゆる”ジャンパー膝”)は、サッカー選手でも発生率が認められ、若年のエリートサッカー選手では13.4%の発症率が報告されています。
これらのデータから、サッカーをプレーする若い選手にとって、膝の痛み・腱障害・関節のトラブルは比較的遭遇しやすい問題といえます。
なぜ膝の痛みが残るのか?ー背後にあるメカニズム・原因

痛みがなかなか良くならない膝痛には、以下のような要因が関係していることが多いです。
①オーバーユース(使い過ぎ)・疲労蓄積
サッカーでは、シュート、ジャンプ、ストップ&ターン、ダッシュ・ストップなど膝に繰り返し強い負荷がかかります。十分な休息や回復期間が取れていないと、膝周囲の腱・軟部組織に微細損傷が蓄積し、炎症・疼痛が続きやすくなります。
②筋力アンバランス・支持筋の弱さ
膝を支えるためには、大腿四頭筋、ハムストリングス、内側・外側広筋、腸脛靭帯、股関節の筋肉(大殿筋・中殿筋など)が協調して働く必要があります。
例えば、膝を内側に引き寄せやすい筋力バランス(内転筋過剰や外転筋弱さ)があると、膝に不自然な力がかかり、痛みが改善しにくくなります。
③可動域制限・柔軟性低下
・股関節の可動性制限:股関節が硬くなると、膝が代償的に働かされる動きが増え、負荷が集中しやすくなります。
・足関節可動性制限:足首の動き(背屈・底屈)が制限されていると、着地や推進動作時に膝に偏った力がかかることがあります。
・大腿前面や腸腰筋・ハムストリングス・内転筋の硬さ:これらが硬いと、膝を曲げた時の負荷分散がうまくいかず、痛みが出やすくなります。
④動作パターン・フォームのクセ
・キックや切り返し動作での「軸足の立て方」が悪い
・膝の使い方が不適切(膝が内側に入る、ねじれ動作が大きいなど)
・加速・減速・方向転換時の体重移動のずれ
こうした癖が繰り返されることで、膝に局所的ストレスが蓄積され、痛みが残りやすくなります。
⑤過去の膝障害・成長期因子
過去にオスグッド(成長期膝疾患)を患った事がある選手は、膝関節や付着部の柔軟性・構造に影響が残っていることがあります。ある研究では、オスグッド病既往のある選手では膝関節機能スコアが健常者に比べて劣る傾向があるという報告もあります。(リンク)
また、ACL損傷や半月板損傷などが起こると、膝関節そのものの構造が損なわれ、それ以降の膝痛が慢性化しやすくなります。サッカー選手におけるACL損傷率も練習よりも高いという報告があります。
整骨院でできる対応・サポート
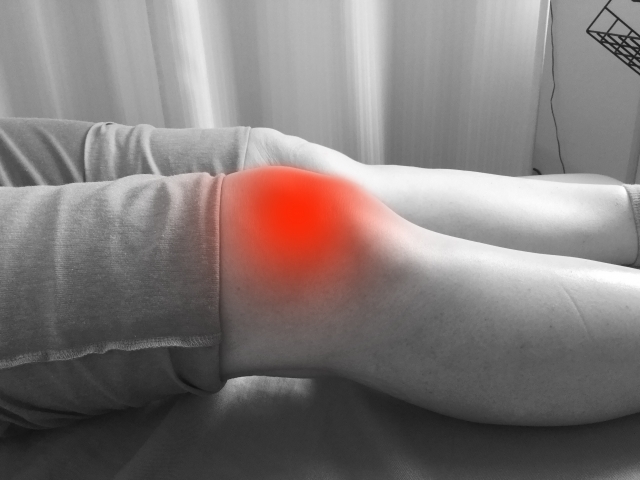
膝の痛みを改善し、再発を防ぐために、千歳市の青葉鍼灸整骨院でできるアプローチは次のような段階で構成されます。
・痛みの性質・発生動作(切り返し・ジャンプ・ストップ時など)を詳しく聞き取る
・視診・触診:腫れ・圧痛部位・筋硬結・可動域制限を確認
・可動域測定:膝・股関節・足関節の可動域チェック
・筋力検査:膝支持筋・股関節筋など
・動作解析:キック・切り返し・着地動作を動画等でチェック
・過去病歴確認(オスグッド、ACL既往など)
・必要に応じて整形外科紹介・画像検査(MRI・レントゲン)
この段階で、「なぜ改善しないか」の本質を把握することがポイントです。
・炎症・腫れ・熱感がある場合はアイシング・冷却療法
・電気療法・超音波療法など軟部組織の修復をサポート
・軟部組織(筋膜・腱・膝包など)への手技療法
・テーピングや関節支持テープで膝関節を補助
この時期に無理をすると悪化するだけなので、痛みを抑えることを優先します。
・大腿前面・後面・内転筋・腸腰筋・ふくらはぎのストレッチ
・股関節可動性改善
・足関節可動性改善(特に背屈可動性)
・筋膜リリース・トリガーポイント療法
可動性が改善すれば、膝にかかる歪みが減り、痛み改善への土台ができます。
・大殿筋・中殿筋・外転筋強化
・内転筋・ハムストリングス・大腿四頭筋のバランス強化
・体幹安定性トレーニング(腹横筋・多裂筋など)
・片足スクワット・ステップダウン等で膝の軸ぶれ改善
・バランストレーニング・不安定面訓練
この段階で、「動かせる体」から「制御できる体」へと進めていきます。
・切り返し・加速・減速・キック動作のフォーム改善
・膝が内側に入らない使い方、膝軸意識のトレーニング
・動作を鏡・動画でフィードバック
・練習中に注意すべき動作パターンの指導
正しい動作パターンが身に付けば、痛みの再発を抑えることが可能です。
・練習量・強度の段階的増加
・ウォームアップ・クールダウン導入
・定期チェック(可動域・筋力・動作)
・自宅でのセルフケア指導(ストレッチ・トレーニング維持)
注意すべきサイン・病的膝障害を疑う時
以下のような症状がある場合は整骨院対応だけでなく、整形外科での画像診断や専門医の診察が必要です。
・膝が膨れる・腫れて熱感が強い
・ロッキング(膝が動かない)やクリック音・引っかかり感がある
・強い安静時痛・夜間痛
・半月板損傷・靭帯損傷の既往や不安定感がある
・長期間(数か月)痛みが改善しない
まとめ:諦めずに根本から改善を目指そう
膝の痛みが長引くサッカー少年には、使い過ぎだけでなく、関節可動性・筋バランス・動作パターン・過去歴といった複数の要因が絡んでいることが多いです。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みを抑えるだけでなく、体の使い方そのものを見直し、膝に負担をかけない動きを身につけるまでを支えることができます。
「また痛むかもしれない」とビクビクしながらプレーするのではなく、正しいケア・動き方を身につけて安心して練習・試合に臨める体を一緒に作っていきましょう。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。


サッカーで股関節痛 千歳青葉鍼灸整骨院

サッカーで股関節が痛い人へ 動きのクセとケアの重要性
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
サッカー選手にとって「股関節の痛み」は、非常に多いトラブルの1つです。
「ボールを蹴る瞬間に痛い」「走り出す時に股関節の奥がズキッとする」「プレー後に違和感が残る」ーーそんな悩みを抱える選手は、年齢やレベルに関係なく増えています。
特に最近は、学生や社会人サッカー選手でも慢性的に股関節の痛みを感じている人が多く、単なる筋肉痛と思って放置すると、長期離脱につながるケースも少なくありません。
サッカーと股関節の関係
サッカーは「走る」「蹴る」「方向転換する」という、股関節を中心とした動作が非常に多いスポーツです。股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ大きな関節で、全身のバランスを取る”軸”のような存在です。
特にサッカー動作では、
・ボールを蹴る時の股関節の屈曲・伸展・内旋・外旋
・スプリント(ダッシュ)での伸展・内転筋の強い働き
・急な方向転換での内外旋コントロール
といった動きが、常に繰り返されています。
この複雑な動作の積み重ねが、”筋肉や関節へのオーバーユース(使い過ぎ)”を引き起こし、痛みや炎症に繋がります。
股関節の痛みを引き起こす代表的な原因

①腸腰筋や大腿直筋の過緊張
ボールを蹴る動作では腸腰筋が過剰に使われやすく、緊張が続くことで股関節前面に痛みが出やすくなります。
②内転筋の硬さ・柔軟性の低下
キック動作やサイドステップ時に、内転筋群(内もも)の柔軟性が低下すると、股関節の可動が制限されて痛みが生じます。
③体幹・骨盤の安定性の低下
サッカーでは片足での動作が多く、骨盤の安定が保てないと股関節に負担が集中します。特に腹横筋や中殿筋が弱い選手は注意が必要です。
④フォームの乱れ(蹴り足・軸足の使い方)
無意識のうちに軸足の股関節が内側に入り込んだり、蹴り足が外旋しすぎたりすることで、股関節へのストレスが増大します。
サッカー選手に多い股関節障害の例
・グローインペイン症候群(鼠径部痛症候群)
内転筋や腸腰筋、腹直筋付着部などが慢性的に炎症を起こす状態。サッカー選手に特に多く、長引きやすいのが特徴です。
・FAI(大腿骨寛骨臼インピンジメント)
骨の形の問題で股関節がスムーズに動かず、骨同士がぶつかって痛みを起こします。
・滑液包炎や腱炎
股関節周囲の滑液包や腱が炎症を起こし、動かすたびに違和感や熱感が出ることがあります。
痛みを感じたらやるべきこと
1.まずは安静とアイシング
痛みが強いときは無理をせず、早期にアイシングで炎症を抑えましょう。
2.整骨院での評価・施術を受ける
原因が筋肉か、関節か、フォームかによって対処法は異なります。整骨院では、動作分析や筋バランスのチェックを通して根本原因を探ります。
3.柔軟性と安定性の両方を改善
単にストレッチするだけでなく、骨盤を安定させる体幹トレーニング(特に中殿筋・腹横筋の強化)も欠かせません。
4.キックフォームの見直し
フォーム指導を受けることで、再発を防ぐことができます。特に軸足の向きや骨盤の回旋の使い方を整えることが重要です。
股関節の痛みを防ぐセルフケア
・腸腰筋ストレッチ
仰向けで片膝を抱え、反対の足を伸ばすストレッチで前面の硬さを解消。
・中殿筋エクササイズ
横向きで足を持ち上げるサイドレッグリフトで骨盤の安定を強化。
・内転筋のほぐし
ボールやフォームローラーを使って、内ももをゆっくり圧迫・ほぐします。
・ウォーミングアップとクールダウンの徹底
筋肉の温度や弾力を保ち、ケガを予防します。
サッカー選手の股関節痛に関するデータ

サッカーと股関節障害は、国内外の調査でも強い関連が報告されています。
・「スポーツ庁:スポーツ外傷・障害調査(2023)」
→サッカー選手の約32%が下肢関節(特に股関節・膝)に痛みを経験(リンク)
・「日本整形外科学会:グローインペイン症候群ガイドライン(2022)」
→男子サッカー選手の約15~20%が鼠径部痛を経験(リンク)
・「国立スポーツ科学センター(JISS)研究報告」
→サッカーにおける股関節可動域の低下が再発率を約1.8倍に上げると報告(リンク)
まとめ
サッカーによる股関節の痛みは、「単なる使い過ぎ」だけでなく、体の使い方やフォームのクセから生じているケースが多く見られます。特に、腸腰筋・内転筋・中殿筋のバランスが崩れていると、蹴る・走る・止まる動作で負担が偏り、痛みが慢性化します。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、
・動作評価による原因の特定
・筋バランスの調整施術
・自宅でできるセルフケア指導
を通して、再発しない体づくりをサポートします。
「少しの痛みだから大丈夫」と我慢せず、早めのケアが、長くサッカーを楽しむための第一歩です。もし気になる症状や困っている事などありましたら、お気軽にご相談ください。