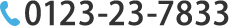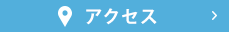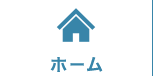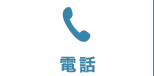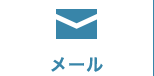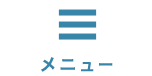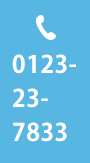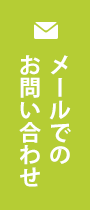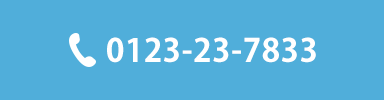首の横が張る 千歳市青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
はじめに:その”張る”は「首の横が張る」?
仕事中や家事の合間、ふと「首の横が張る」と感じる瞬間はありませんか?スマホやパソコンを見続けた後、”首の横が張る”と痛みや違和感が広がるのは、現代人にとってとても身近な不調です。
今回の記事では、「首の横が張る」状態の原因や背景、セルフケア、千歳市の青葉鍼灸整骨院でのアプローチについて、わかりやすくお伝えしていきます。
①「首の横が張る」はどれくらい多い?統計で確認
1.首の痛みの生涯有病率は60~80%に上ると言われ、1年以内の発症率もおおよそ10~21%と報告されています。つまり、「首の横が張る」こともこの一部として頻繁に起こるわけです。(生涯60~80%、1年10~21%で首の痛み発症)
2.世界中で年間30~50%の人が首の痛みを経験しているというデータもあり、”首の横が張る”も含む首まわりの違和感はごく普通の経験と言えます。(年間30~50%の人が首の痛みを経験)
3.一般成人の平均首の痛み有病率は23.1%で、大学生では48~78%とさらに高いのが特徴です。長時間のスマホや姿勢の影響を受けやすい若年層では、”首の横が張る”も頻出症状です。(大学生の首痛発症率48~78%)
②なぜ「首の横が張る」のか?その原因とメカニズム

・姿勢の歪み・頭部前傾姿勢
スマホ首や前傾姿勢が続くと、首の側面の筋肉に長時間負荷がかかり、「首の横が張る」と感じやすくなります。
・筋力バランスの崩れ
肩・背中・体幹の筋力が弱いと、首でバランスを取りがちになり、結果として”首の横が張る”ことになるんです。
・深部筋の硬縮・筋膜の緊張
コリのしこりが筋膜に伝わり、「首の横が張る」違和感として訴えることもあります。ストレートネックなど構造的な影響も伴うことがあります。
・血行不良
冷えや緊張により、筋肉の血流が低下すると、酸欠状態になり、「首の横が張る」症状が強まります。
・ストレス・心理的負担
精神的な負荷も筋硬直を引き起こし、首の側面が張る原因となります。
③実際に「首の横が張る」ときの日常症状例
・長時間のスマホ操作で急に”首の横が張る”感じが広がる
・パソコン作業後、右または左側だけ”首の横が張る”ような違和感を覚える
・運転中に振り向くと、「首の横が張る」感覚とともに腕や肩まで重くなる
・肩や肩甲骨にも張りを感じるほど、”首の横が張る”のが全身に広がる感じ
・朝起きたときに、「首の横が張る」のが強く、首を回すと痛みを伴う
④セルフケアでできること:簡単なのに効果的!
左右にゆっくり首を傾け、”首の横が張る”が少し和らぐ範囲で静かにキープ。1日数回が効果的。
ホットタオルやカイロで首側面を温めると、筋が緩んで”首の横が張る”が軽減されやすいです。
前傾姿勢が続いたら、胸を張って肩甲骨を寄せ、頭を軽く引き戻すように意識。これだけで「首の横が張る」予防になります。
特に仕事中は、1時間ごとに簡単なストレッチで、「首の横が張る」の未然防止に。
入浴中に優しく首を回すことで、「首の横が張る」だけでなく、全身の血流とリラックス効果も同時に得られます。
⑤千歳市青葉鍼灸整骨院でのケア:根本から「首の横が張る」を改善

・手技療法
首側面や肩の筋膜を緩めるマッサージや筋膜リリースで、「首の横が張る」状態を奥からほぐします。
・関節モビリゼーション
頸椎や肩関節の可動域を整える施術で、”首の横が張る”への刺激を和らげます。
・姿勢分析と改善指導
日常習慣や姿勢のクセを見極め、「首の横が張る」原因を解消する指導を行います。
・セルフケア指導
自宅でできるストレッチや運動、首・肩のほぐし方をわかりやすくお伝えします。
・環境提案
枕の高さやデスク環境の見直しなどで、そもそも”首の横が張る”姿勢にならない環境づくりをサポートします。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
⑥まとめ:放置厳禁、「首の横が張る」は専門ケアで快適に改善
1.首の不調は多くの人が経験し、1年以内の発症率も高い
2.「首の横が張る」は現代人の姿勢習慣と深い関連があり、放置すると慢性化の恐れも
3.千歳市の青葉鍼灸整骨院では、その場ケアだけでなく、予防・姿勢改善まで包括的アプローチができる
「首の横が張る」は見過ごしがちですが、ケアと改善で快適な日常を取り戻せます。”首の横が張る”つらい感覚、一緒に軽くしていきましょう。何か気になる症状などあってお困りでしたらお気軽にご相談ください。


首を動かすと肩痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
「首を動かすと肩が痛い」あなたへ‐痛みの仕組みと整骨院でのケア
日常で「首を動かすと肩が痛い」と感じることがありませんか?特に朝起きたときや長時間のデスクワークの後、首を動かすたびに肩にズキッとした痛みが走る,,,。そんな不快な症状に悩む方へ、今回は「首を動かすと肩が痛い」原因・要因・セルフケア・そして千歳市の青葉鍼灸整骨院でのサポートまで、しっかりお伝えしていきます。
①「首を動かすと肩が痛い」はどれくらい多い?
・手工業や手作業が多い職業では、過去12カ月の間に頸か肩または両方に痛みを感じた割合が66.6%にのぼります。(肩の痛み72.1%、首の痛み68.3%)(手工業者における首・肩の痛みの12カ月有病率)
・オフィスワーカーの調査では、視覚ディスプレイ作業を1日1時間以上行う人のうち、首の痛みが55%、肩の痛みも50.7%にのぼりました。(オフィスワーカーにおける首の痛み・肩の痛み)
・世界全体でも、年間30~50%の人が首の痛みを経験しているという報告もあります。(一般人口の首の年間発症率と一点有病率)
これらのデータから、「首を動かすと肩が痛い」という症状は非常に頻繁に発生していることがわかります。
②なぜ「首を動かすと肩が痛い」のか?考えうる原因
首を動かすと、肩回りの筋肉(僧帽筋上部・肩甲下筋・肩甲挙筋など)が引っ張られて、筋膜連動で「首を動かすと肩が痛い」と感じることがあります。
頸椎や肩甲上腕関節(肩甲骨と上腕骨で構成される関節)の関節包・関節周辺組織に炎症がある場合、首を動かすたびに肩にも刺激が伝わり、「首を動かすと肩が痛い」症状が現れやすくなります。
首の神経(特にC4~C6)が圧迫・炎症を起こすことで、「首を動かすと肩が痛い」のほか、腕や指にしびれを伴うケースもあります。
長時間の前傾姿勢やスマホ首(ストレートネック)は、首や肩の筋肉に大きな負担を与え、「首を動かすと肩が痛い」感覚を引き起こします。慢性的な疲労として蓄積しやすいため、注意が必要です。
③「首を動かすと肩が痛い」人が感じる具体的な症状

よくある痛みの場面は以下の通りです。
・首を左右にひねると、肩にズキッと痛みが走る
・後ろを振り向くと「首を動かすと肩が痛い」と感じる
・肩を回すと同時に首にも痛みが出る
・寝返りや上を向く動作で「首を動かすと肩が痛い」と目覚める
・同じ姿勢(デスクワークやスマホ操作)を長く続けると、「首を動かすと肩が痛い」が強くなる
④千歳市の青葉鍼灸整骨院が提案するケア方法
手技療法で首・肩の張りを緩和し、「首を動かすと肩が痛い」状態から筋肉を解放します。
関節の動きを整え、首を動かすこと自体が肩に伝える不快な刺激を減らします。
片寄った負担のかけ方にならない楽な姿勢・動作の習得を促し、痛みの再発を防ぎます。特に「首を動かすと肩が痛い」の原因となる姿勢を修正していきます。
首と肩のストレッチ、姿勢保持のための簡単エクササイズなどをお伝えし、日常でも「首を動かすと肩が痛い」が再発しないように支援します。
枕の高さ、デスク環境、画面位置の見直しで、「首を動かすと肩が痛い」状況を減らします。
青葉鍼灸整骨院での治療の流れ

①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
⑤まとめ:早期ケアで快適な動きを取り戻す
・「首を動かすと肩が痛い」は非常にポピュラーな症状で、多くの方が経験しています。
・原因は筋・関節・神経・姿勢などさまざまで、千歳市の青葉鍼灸整骨院ではこれらを総合的に治療ができます。
・早めの対応が痛みの長期化を防ぎ、快適な生活をサポートします。
「首を動かすと肩が痛い」と感じたら、1人で悩まずにお気軽にご相談ください。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、あなたに合ったケアで、快適な動きを取り戻すお手伝いをいたします。


寝違えで首回らない 千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
はじめに
朝、目が覚めた瞬間に「あれ,,,首が回らない」と感じる経験はありませんか?まさにそれが、俗にいう「寝違え」です。日常的によくある症状の1つですが、突然「首が回らない」と感じる辛さは本当に厄介です。今回の記事では、その「首が回らない」状態の原因と対策、そして整骨院がどのように支えられるのかを、詳しくお伝えしていきます。
寝違えとは?
医学的には「急性疼痛性頸部拘縮」や「結合織炎」と表現されることもある寝違えは、睡眠中に首や肩に過度な負担がかかる姿勢をとったことがきっかけで、「首が回らない」衝撃的な痛みを引き起こす症状です。特に、寝起きに激しく「首が回らない」と感じることが多く、日常動作にも影響が出るケースもあります。
実際の経験頻度
2007年に実施された意識調査では、「寝違えを経験したことがある」方が大多数という結果が示されています。つまり「首が回らない」状態に遭遇する人は非常に多いのです。

主なメカニズムと誘発要因
1.就寝中の悪い姿勢
高すぎる枕、うつぶせ寝、寝返りが少ない、同一姿勢の維持などで、筋肉や関節への負担が増え、「首が回らない」状態を誘発します。
2.筋肉の柔軟性不足や血流不良
睡眠中の長時間の筋緊張や血行低下により、筋肉にしこりやこわばりが生じ、「首が回らない」という症状へとつながります。
3.椎間関節や神経の急性炎症・損傷
頸椎の椎間関節や関節包、筋肉に微小な損傷や炎症が発生し、動かすと「首が回らない」痛みが突出する場合があります。
4.複数要因の重なり
姿勢の問題、環境要因(冷えなど)、身体の硬さなどが重なることで、症状が発生しやすくなる傾向があります。

「寝違え」と直接表現された統計は少ないですが、「首の痛み」の一般的な頻度や負担を示すデータは参考になります。
1.世界人口の約4.9%が首の痛みを経験
世界で約3億3,000万人が首の痛みを経験しており、その半分が1年以内に症状が改善する一方、10%は慢性化します。
2.一次診療での首の痛みの年間発症率は約10.4~21.3%
首の痛みは一次診療のよくある症状であり、発症率は10~20%と高めです。(→https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2020/0801/p150.html)
3.長時間座り続けることによる首の痛みのリスク上昇
1日に6時間以上座りっぱなしでいると、首の痛みのリスクが大幅に高まり、特に「首が回らない」を伴う症状への影響が指摘されています。(ニュース記事参照‐工具内表示)
安静ではなく、適度な動きが回復を早める
・無理に動かすより、ゆっくりと痛みの出ない範囲で軽く首を動かすことで血流改善を促します。
・温めることで筋肉が緩み、「首が回らない」強い痛みを和らげる効果があります。
姿勢や睡眠環境の見直し
・枕の高さを見直し、首のカーブにフィットした適切な高さを選びましょう。(ストレートネックなどが原因を助長することもあります)
・寝返りが打ちにくいマットレスや寝具は避け、全身が自然に動きやすい環境を整えることが重要です。
⑤千歳市の青葉鍼灸整骨院でできる「首が回らない」

1.手技による筋肉の緊張をとる
僧帽筋や肩甲挙筋など、首から背中周辺の筋肉を丁寧に緩めていき、「首が回らない」状態からの回復をサポートします。
2.関節モビリゼーションや関節可動域の改善
痛みが引かない場合は、椎間関節の動きを改善し、「首が回らない」という制限を解除していきます。
3.姿勢と動作習慣の調整指導
日常や睡眠中の体勢を正しいものへ導くアドバイスを行い、「首が回らない」再発を防ぎます。
4.セルフストレッチと予防プログラム
自宅で簡単にできるストレッチや予防運動をお伝えし、ご自身でもケアが継続できるように支援します。
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
1.寝違えによる「首が回らない」は非常に一般的で、多くの人が経験しています。
2.頸部痛は年間10~20%の発症率があり、長時間座り続けるなど生活習慣も影響します。
3.千歳市の青葉鍼灸整骨院では、痛みの緩和だけでなく、姿勢や環境対策を含めた根本改善を目指せます。
「首が回らない」と感じたら、1人で悩まずにご相談下さい。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、優しく丁寧なケアで快適な朝の動きを取り戻すお手伝いをいたします。


交通事故で首が痛い 千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
交通事故に巻き込まれてしまい、「首が痛い」と感じたことはありませんか?事故直後は何ともなくても、数時間後や翌日に、急に「首が痛い」と感じる方も珍しくありません。今回の記事では、交通事故後の首の痛みの原因やその背景、そして整骨院でできるケアや回復の道筋をわかりやすくお伝えしていきます。ひとりで悩まず、一緒に改善していきましょう。

交通事故に伴うむち打ち症(ワーハンド)の頻度
・自動車事故後のむち打ち(whiplash injuries)は、関与した人の最大83%に発生するとされています。(むちうち発生率)つまり、事故に遭うと、「首が痛い」と感じる可能性がめっちゃ高いということなんです。
・また、米国では毎年約87万人の交通事故関連の頸椎(首)の怪我が医療機関で扱われているというデータもあるため、交通事故後の「首が痛い」訴えは決して少なくありません。
続く「首の痛み」の長期的な割合
・事故後1年経っても、その後も首の痛みが継続する可能性は50%にのぼるという報告があります。(交通事故後の慢性首痛、1年持続する割合)つまり、「首が痛い」が慢性化するリスクも高いため、早期対処が重要です。

1)むちうちによる軟部組織の損傷
交通事故では、首が急激に前後へ振られる「ムチウチ」の動きにより、筋肉・靭帯・関節包・椎間板にストレスがかかります。これにより、「首が痛い」と感じる原因となります。
2)関節・椎間関節の障害
むちうちでは、特に上位頸椎の椎間関節(ファセット関節)が痛みの発生源になることが多く、「首が痛い」が関節由来である場合もあるんですよね。
3)神経や血管に由来する症状(まれなケース)
強い衝撃により、まれに椎骨動脈や内頚動脈にダメージが生じ、「首が痛い」とともに頭痛・めまい・しびれなどが現れることもあるんです。重大な症状がある場合は、速やかな医療機関受診が必須です。
1.事故直後より”遅れて”痛みが出ることが多い
痛みが事故直後に出ない場合でも、数時間後~翌日以降に「首が痛い」と感じるケースが多いです。
2.鈍痛・運動制限・頭痛などの複合的症状
「首が痛い」だけでなく、動かしづらさや頭痛、肩甲骨周辺の不調などを伴うことが多いです。
3.慢性化のリスク
5年後にも40.7%のむち打ち症患者が首の痛みを抱えているという報告があり、早期ケアが不可欠です。(交通事故後5年経っても首の痛みを訴える割合)

1.初期対応と緊張緩和
・軽く動かすこと、ときには温熱療法により、筋肉の緊張を鎮め、「首が痛い」症状の悪化を防ぎます。
・完全な安静ではなく、安全な範囲での柔らかな動きを早期に促すことが、回復を早めます。
2.手技と関節調整
・筋肉や関節の動きを改善し、「首が痛い」を緩和するための手技療法やモビリゼーションを行います。
・慢性化を防止するため、関節の可動域改善や緊張緩和に取り組みます。
3.姿勢や動作の見直し
・日常での動き、姿勢、寝方などの習慣を整えることで、「首が痛い」症状が再発しづらい身体へ導いていきます。
4.リハビリとセルフケア指導
・首や上半身の柔軟性を高める運動・ストレッチを指導し、自宅でも続けられるケアをお伝えします。
5.状態に応じた連携または診断依頼
・強い痛みや神経症状が疑われる場合は、整形外科や専門医への紹介も対応可能で、安全な回復を支えます。
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
1.交通事故後に「首が痛い」のは非常に多い症状(最大83%)
2.事故後1年でも50%が痛みを継続しており、慢性化予防が重要です。
3.千歳市の青葉鍼灸整骨院では、状態に応じて早期に動かすこと・姿勢改善・手技療法・セルフケア指導を通じて、皆さんの「首が痛い」を早期にケアします。
事故後の「首が痛い」は、決して1人で抱えるものではありません。適切なケアと支えで回復への道筋は開かれます。気になる症状、あてはまる症状などありましたらお気軽にご相談ください。


首が痛い悩みがある 千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
はじめに
重い荷物を持ち運ぶ、かがむ作業を続ける、長時間の同一姿勢など、重労働に従事する人々の多くが抱える悩みの1つに”首が痛い”という状態があります。単なる疲労では片づけられず、作業効率や生活にも影響するこの”首が痛い”問題に対し、整骨院ではどのようなアプローチが可能か、今回は詳しく解説していきます。
世界および国内の一般的な首の痛みの状況
・世界的には、2010年には約3億3,000万人が首の痛みに悩み(世界の約4.9%)があるとされています。
・年間を通じて、多くの働く世代で”首が痛い”と感じることは珍しくなく、高齢化や身体的負荷の増加が背景にあります。
重労働者・ブルーカラーに特有のリスク
・工場や建設、物流などのブルーカラー(肉体労働者や技術者を指す)労働者の年間”首が痛い”報告率は約48%と、半数近くにのぼります。(ブルーカラー労働者の年間「首が痛い」報告率)
・欧米の大規模調査では、長時間労働や重い作業、反復作業は”首が痛い”リスクの重要な要因と強く関連していることが示されています。(米国における重労働・長時間労働と「首が痛い」の関連)
業種別・時間別の傾向
・米国のデータでは、インストール・メンテナンス・修理などの職種は、建築・エンジニア系と比較して”首が痛い”リスクが高いと報告されています。
・また、週46~59時間働く人は”首が痛い”リスクが約1.2倍、週60時間以上は、1.35倍に上ることも示されています。
これらの統計データから、重労働に伴う身体ストレスと”首が痛い”症状の頻度・重症度の関連性が明らかです。

1)姿勢の問題と負荷の集中
重いものを運ぶ、かがむ、前傾姿勢を続ける作業では、首にきわめて大きな負荷がかかります。”首が痛い”と感じるのは、下記のような要因が組み合わさっているためです。
・前傾姿勢や不自然な体勢→首へのストレスが増加し、筋肉や関節に負担
・反復作業や持続的な同一姿勢→筋疲労が蓄積され、”首が痛い”状態が慢性化しやすい
・重い工具や材料の扱い→頭部や頸部の安定が乱れ、”首が痛い”と感じる頻度が高まる
2)物理的および心理的ストレス
・高い作業負荷だけでなく、人員不足や長時間勤務などの心理的ストレスも”首が痛い”症状に影響します。(身体的・心理的ストレスが「首が痛い」原因に影響する可能性)
・ストレスによって筋緊張が強まり、”首が痛い”と感じる状況が頻発する場合もあります。
以下は、整骨院に来院される重労働者がよく訴える症状です。
・作業後、首が凝り固まり、”首が痛い”と感じる
・物を持ち上げたり、運んだりするときに首にピリッとした痛みが出る
・朝起きたときに”首が痛い”と感じることがある
・同じ姿勢を続けた後、”首が痛い”だけでなく、肩から背中にも広がる痛みが出る

1)姿勢と動作の調整
・作業姿勢の見直し:前傾やかたよった姿勢を避け、首と体幹を一体として動かす姿勢を意識する
・動作の工夫:「持ち上げる」「運ぶ」ときに、膝腰主体で体幹を使うフォームの指導
2)筋肉・関節の調整
・手技療法(関節モビリゼーションなど)や物理療法(温熱治療器や高周波など)で、筋肉の柔軟性を回復させ、”首が痛い”症状の緩和を目指す
・ストレッチやセルフケア指導:首や肩、背中の筋肉を自宅でもケアできるようにサポート
3)姿勢保持筋の強化
・首から下背部の筋肉に刺激を入れるエクササイズ:頭を支えるための深層筋を中心に、安定性強化をゆっくり進める
・体幹の安定向上:重労働に耐えうる体幹を整えることで、”首が痛い”リスクを軽減させる
4)職場環境・作業内容の工夫提案
・作業休止・頻度の見直し:同一姿勢や重負荷作業を短時間ごとに区切るリズム作業の導入
・用具の工夫:長い道具の使用、持ち手の変更、台上作業の導入など、首の角度に配慮する工夫
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
1.統計:重労働者の約48%が年間に”首が痛い”を経験
2.要因:長時間労働や重作業、身体的・心理的ストレスの複合で、”首が痛い”状態に陥りやすい
3.対策:姿勢・動作の改善、筋肉・関節のケア、職場工夫、セルフケア導入で”首が痛い”リスクを低減できる
重労働の現場で働く皆さんが、”首が痛い”と感じても放っておかず、早めに治療やケアをすることで、作業効率や日常生活の快適さも大きく変わります。気になる症状、あてはまる症状などありましたらお気軽にご相談ください。


首が凝る症状 千歳市青葉鍼灸整骨院

はじめに
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
スマホやパソコンの長時間使用、学校や部活動での姿勢や疲れから、若い人でも「首が凝る」悩みを抱えることが増えています。実際に、「首が凝る」と感じたことがある、という人は少なくありません。今回は「首が凝る」状態の背景や原因、対策についてわかりやすくご紹介していきます。
世界的な傾向
若い世代でも、首の不調はきわめて一般的です。例えば、「neck pain (首の痛み)」についての調査では、若年層での12カ月間の発症率が42~67%にのぼるとされ、つまり約半数近くの若者が1年の間に何らかの首の不調を経験していると推測できます。(若年の首痛の年間有病率に関する調査)
青年期~若年成人の負担
さらに、世界的なデータから、10~24歳の年齢層では、1990年から2019年にかけて「neck pain (首の痛み)」の患者数が約1,159万件から1,288万件へ増加。特に20~24歳の層では10~14歳の約3倍の有病率となっており、まさに若い世代における「首が凝る」状態が深刻であることが分かります。(10~24歳の世代における首の痛みの世界的推移)
学業・オンライン学習との関係
大学生を対象にした研究では、オンライン学習を3か月続けたうち74,2%が首に軽度~中度の不調を感じており、その多くが最近起こった症状として「首が凝る」と表現できる状態でした。オンライン授業の長時間化が「首が凝る」原因の1つとして注目されています。(オンライン学習による学生の首の痛みの現状)

スマホ姿勢が招く「ストレートネック」
スマホやノートパソコンを長時間使うことで、頭が前方に下がる「前傾姿勢(forward head posture)になりやすく、これが首への負担を大幅に増加させます。姿勢によっては首に物理的なストレスが何倍にもなることも。若い世代では特にその傾向が強まっています。
丸まった肩と連動する姿勢の悪さ
丸まった肩(rounded shoulder posture)は、上位胸椎の動きを制限し、首の筋肉を過緊張に導きます。この姿勢が続くことで、首が凝る状態が慢性化しやすくなります。
ストレスや心理的負担も影響
精神的なストレス、睡眠不足、孤立感などがあると、筋肉がこわばり、「首が凝る」感覚が強くなる傾向もあります。若い世代にとって生活環境の変化が大きく影響するため注意が必要です。(BioMed Central)
千歳市の青葉鍼灸整骨院でもおススメしている、若い人ができるセルフケア習慣を以下にまとめます。
1.姿勢を意識する習慣を取り入れる
・スマホを見る時は、目線を少し上げて、頭が前に出ないように意識する
・姿勢が崩れてきたら、背筋を伸ばして肩を軽く後ろへ引くストレッチを定期的に
2.”首が凝る”と感じたらこまめに動かす
・長時間同じ姿勢を続けないように、約1時間ごとに軽く首や肩を回す
・ゆっくりとしたストレッチや深呼吸を行うことで、筋肉の緊張がやわらぎます
3.胸を開く背中のストレッチ
・壁に背中をつけ、肩甲骨を意識しながら胸を開くように立つことで、姿勢改善にも効果的
・壁の前に立ち、前腕を壁につけて背中をのけぞるように腕に体重をあずけて背中を伸ばす
・丸まった肩を矯正し、「首が凝る」予防になります
4.ストレス管理も忘れずに
・十分な睡眠、休息をとること。好きな音楽や軽い運動でリラックスする時間を持ちましょう。

もし「首が凝る」状態が続いて辛くなったら、整骨院に相談するのも1つの方法です。
・手技療法や物理療法(温熱治療器や高周波など)で硬くなった首・肩回りの筋肉を緩めたり伸ばす
・姿勢分析と調整で「首が凝る」根本原因を見つけ、楽に正しい姿勢がとりやすい状態をエクササイズなどを取り入れて作る
・セルフストレッチの指導で、自宅でも簡単にケアできる方法をお伝えします
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
1.若者でも「首が凝る」症状が決して珍しくなく、1年に半数以上が経験している可能性がある
2.スマホ姿勢や丸まった肩、心理的ストレスなどが複合して「首が凝る」原因となる
3.整骨院では姿勢改善や筋肉ケアをベースに、持続的な改善を目指すサポートができる
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、患者さんと適切なコミュニケーションを取り、身体の状態がどうなっているのか、だからこういうところに痛みが出ていて、こういう治療をしたら、こういう身体になるというところまで、お話をさせていただいております。
ご自身の原因がわからない不調・痛みや今回の記事にあてはまる症状など悩んでることがあったら、是非ご相談ください。


首が動かしづらい方へ千歳青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
日常生活の中で「首が動かしづらい」と感じる瞬間はありませんか?朝起きた時に首を回そうとしても引っかかるような違和感がある、長時間のデスクワーク後に後ろを振り向けない、車の運転中に安全確認で振り返るのが辛い,,,。このように「首が動かしづらい」という感覚は、多くの人に共通する身近な不調の1つです。
整骨院には、このような症状で悩まれて来院される方が少なくありません。今回は、「首が動かしづらい」と感じる原因や日常生活への影響、そして統計データを交えながら整骨院でのサポートについて詳しくお伝えしていきます。

「首が動かしづらい」とは、単に首の痛みだけでなく、左右や上下にスムーズに動かせない、動かすとつっぱり感や制限を感じる状態を指します。例えば車のバック時に振り向けない、うがいする時に上を向くのがつらいといった日常の不便さとして現れます。
この「首が動かしづらい」状態は、単なる一時的な凝りや寝違えのような症状にとどまらず、姿勢や筋肉、関節の機能低下などが背景にあることも多いんですよね。

年間・生涯発症率の高さ
世界的に見ても首の不調は非常に一般的で、年間で30~50%の人が首の痛みや不具合を経験しており、平均では約37,2%と報告されています。また、生涯を通じては22~70%の人が首の痛みを感じたことがあるという統計もあります。(出典:Physio-Pedia – Epidemiology of Neck Pain)
これらの数字は、「首が動かしづらい」と感じることが特別な状態ではなく、誰にでも起こりうる身近な問題であることを示しています。
学生を対象とした調査では、首の可動域に制限がある人の割合が次のように報告されています。屈曲(前に倒す動き)で30.6%、回旋(左右に振り向く動き)で25.2%、側屈(横に傾ける動き)で23.8%、伸展(後ろに倒す動き)で20.4%。この結果は、若年層であっても「首が動かしづらい」状況に直面している人が多いことを示しています。(出典:University of Zenica study)

特に長時間同じ姿勢で働く職業では、首の動きが制限されやすい傾向にあります。タクシー運転手を対象にした研究では、47.5%の人に頸部の可動域制限が確認されました。その内訳は軽度18.3%、中度17.5%、重度2.5%とされ、日常的に「首が動かしづらい」と感じるリスクが高いことがわかります。(出典:LWW-Taxi Drivers’ Cervical ROM Restriction)
「首が動かしづらい」状態が続くと、日常のあらゆる場面で不便さが生じます。
・車の運転時に後方確認が難しい
・デスクワークで長時間座っていると首や肩が固まってしまう
・スポーツや運転中に視野が制限され、パフォーマンスが下がる
・高齢者では振り返る動作が難しく、転倒リスクが高まる
首は頭部を支え、全身のバランスに関わる重要な部分です。そのため「首が動かしづらい」と感じることは、単なる不快感にとどまらず、生活の質(QOL)を下げてしまう要因にもなるんですよね。
姿勢の乱れ
長時間スマホやパソコンを操作することで頭が前に出た姿勢(ストレートネック)が習慣化し、首に大きな負担がかかります。これが「首が動かしづらい」と感じる大きな原因の1つです。
年齢や性別
統計的に女性や中高年層は首の不調を抱えやすいことが報告されています。加齢に伴う筋力低下や柔軟性の低下も「首が動かしづらい」症状を引き起こします。
職業による影響
運転業務、デスクワーク、細かい作業を長時間続ける職種の方は、首まわりの筋肉が硬くなりやすく、可動域が狭くなってしまいます。タクシー運転手のデータが示すように、「首が動かしづらい」状態は職業病的に現れることもあります。
慢性化のリスク
一度首の不調を経験した人の約30%が慢性化し、37%は12カ月以上症状が続くとされています。早期に対処しなければ「首が動かしづらい」状態が長引く危険性があります。

千歳市の青葉鍼灸整骨院では、「首が動かしづらい」症状に対して以下のようなサポートを行います。
・手技療法や物理療法(温熱治療器や高周波など)
硬くなった筋肉を緩めたり伸ばすことで、関節の動きを改善していきます。
・姿勢改善指導
日常生活での姿勢や身体の使い方をチェックして、負担がかかりやすい原因などを確認してその方に必要なエクササイズを取り入れて、再発を防いでいきます。
・運動療法・ストレッチ指導
可動域を広げるためのセルフケアやストレッチを提案し、自宅でも「首が動かしづらい」状態を改善できるようサポートしていきます。
・高齢者向けバランストレーニング
首の可動域だけでなく全身の安定性を高め、転倒予防につなげます。
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
「首が動かしづらい」と感じることは、多くの人に共通する悩みであり、統計的にも非常に一般的であることが示されています。姿勢の乱れや職業的負担、加齢などさまざまな要因が絡み合い、日常生活の質を低下させる可能性があります。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、手技や運動療法、姿勢改善のサポートを通じて、この「首が動かしづらい」症状を改善へと導くことが可能です。1人で悩まず、専門家に相談することで安心して日常生活を送れるようになります。


上を向くと首痛い 千歳市青葉鍼灸整骨院

千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
日常生活の中で、「上を向くと首が痛い」と感じることはありませんか?
例えば、洗濯物を干す時、天井の電球を交換する時、空を見上げた時,,,そんな場面で首がズキッと痛むと、とても不便ですよね。
「首が痛い」という症状は誰にでも起こりうる身近なものですが、放置すると慢性化し、肩こりや頭痛、手の痺れなどにもつながる可能性があります。
実際に、日本では成人の41%以上が筋骨格系の痛みを抱えており、その中でも首や肩の痛みが最も多く20%以上にのぼるという調査結果があります。(→日本における首・肩の痛みの実態)
さらに世界に目を向けると、2020年には約2億人が首の痛みに悩んでいたとされ、2050年には高齢化と人口増加の影響で2、7億人に増加する見通しです。(→世界の首の痛み患者数と将来予測)
つまり「首が痛い」というのは珍しい症状ではなく、多くの人にとってとても身近な問題なのです。
ということで、今回は、整骨院の治療家視点から「上を向くと首が痛い人」に向けて、原因・セルフケア・整骨院でできる治療法をわかりやすく解説していきます。

「首が痛い」と一言で言っても原因はさまざまです。特に”上を向く”動作で痛みが出る場合には、次のような理由が考えられます。
首の筋肉の緊張によるもの
長時間のスマホやパソコン作業によって、首の後ろの筋肉が硬くなります。その状態で上を向くと、縮んでる筋肉がさらに引っ張られ、「首が痛い」と感じやすくなります。
首の関節の動きが悪くなっている
首の骨(頸椎)は7つの椎骨でできています。加齢や姿勢不良により関節の動きがスムーズでなくなると、上を向いた時に関節にストレスが集中し、首が痛いと感じます。
椎間板や神経のトラブル
変形性頚椎症や椎間板のすり減りなどがあると、神経を圧迫して痛みや痺れが出ることもあります。「単なる凝り」と思っていたら実は神経が関係していた、というケースもあるんですよね。
姿勢の崩れ(ストレートネックなど)
最近増えているのが「ストレートネック」。スマホ首とも呼ばれ、本来の首のカーブが失われる状態です。ストレートネックの方は、上を向く動作が苦手で、首が痛いと訴えることがとても多いんですよね。
「首が痛いけど我慢できるから」と放置するのは危険です。
・首が痛い→首を動かさなくなる
・動かさない→筋肉がさらに硬くなる
・硬くなる→血流が悪化して痛みが増す
・結果→首が痛い状態が慢性化
さらに進行すると、肩こりや頭痛、腕の痺れ、吐き気など、日常生活に支障をきたすこともあるんです。
実際に、人生で一度は首の痛みを経験したことがある人は、67%以上にのぼると報告されています。(→首の痛みを経験したことがある人の割合)

「上を向くと首が痛い」時にできる、自宅でのセルフケアをご紹介します。
姿勢の見直し
スマホは顔を下げ過ぎず、画面を目の高さに近づけてみるようにしましょう。デスクワークでは、椅子やモニターの高さを調整すると首の負担を軽減できます。
温めて血流を改善
首が痛い時は、蒸しタオルや入浴で温めましょう。血流が良くなり、筋肉の緊張がやわらぎます。
軽いストレッチ
強いストレッチは逆効果です!下を向いたり、左右に軽く倒すなど、痛みのない範囲で優しく動かしましょう。※首に器質的疾患を持っている方は、ストレッチする方向によって症状を悪化させてしまうことがあるので、要注意です。(ご相談ください。)
適度な運動
ウォーキングや肩甲骨の体操など、首以外の大きな筋肉を動かすと血流が良くなり、姿勢もおこしやすくなります。結果的に首の痛みがやわらいでいくこともあります。

セルフケアをしても首が痛い場合や、日常生活に支障がでている場合は整骨院にご相談ください。千歳市の青葉鍼灸整骨院では以下のような対応が可能です。
・筋肉や関節の状態をチェック(身体で何が起こっていて、首が痛いのか説明していきます。)
・筋緊張をやわらげる手技療法や物理療法
・姿勢改善のための運動指導
・首や肩に負担をかけない生活アドバイス
千歳市の青葉鍼灸整骨院の治療は、「首が痛い」を一時的にやわらげるだけでなく、再発しにくい体作りを目指していきます。
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。

次のような症状を伴う場合は、整骨院だけでなく病院での検査が必要です。
・首の痛みに加えて腕や手の痺れがある
・力が入りにくい、物をよく落とす
・首の動きに伴ってめまいや吐き気が出る
これは、神経症状の可能性があるため、早めの整形外科受診をおすすめします。

「上を向くと首が痛い」という症状は、筋肉の凝りから関節・神経のトラブルまで幅広い原因があります。放置すれば悪化し、肩こり・頭痛・しびれへと広がる可能性もあります。
・姿勢を整える
・温めて血流を改善する
・軽いストレッチを行う
・必要なら整骨院で治療を受ける
これらを意識することで、首が痛い症状は改善していきます。
もし今、「首が痛い」と感じているなら、無理せず早めにご相談ください。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、首の健康と快適な日常生活をサポートいたします。


区画症候群とは 千歳市青葉鍼灸整骨院
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
今回は、区画(コンパートメント)症候群について詳しく解説していきたいと思います。

コンパートメント症候群とは、四肢(手や足)の骨や筋膜、骨間膜で囲まれた「区画(コンパートメント)」内で、組織にかかる圧力が高まることで、筋肉や神経の血行が悪くなる状態を指します。その結果、筋肉が収縮・弛緩しづらくなる機能不全や、筋肉の細胞が死んで壊死状態になることがあり、筋肉や神経が損傷する可能性があります。
・外傷:骨折、重度の打撲や挫滅損傷(皮膚、筋肉、神経、血管などの組織が内部から複雑に破壊される損傷)、脱臼などによる出血や腫れ
・血管損傷:血管の損傷とその後の再灌流傷害(血流が一時的に止まった後に再び血流が戻った際、組織や細胞に損傷が生じる傷害)
・慢性的な疲労:激しい運動による筋肉の腫れ(特に下腿)
原因を知ればなりやすい人はなんとなく想像がつくと思いますが、特徴を4つ具体的に挙げていきます。
①外傷を負った人
骨折、打撲、脱臼などの外傷によって、筋肉組織内に腫れや出血が生じ、区画内の圧力が高まります。特に、下腿や前腕(肘から手首にかけて)は筋肉が多く存在するため、コンパートメント症候群が発症しやすい部位なんですよね。
②激しい運動を行う人
ランニングやジャンプなど、筋肉に強い負荷がかかる激しい運動を頻繁に行う人も、コンパートメント症候群になりやすいです。原因でお伝えした通り、慢性的な疲労により、特に下腿に発症しやすく、急激な運動量の増加や、普段使わない筋肉を急に使い始めた場合にも起こることがあります。
③特定の治療を受けている人
ギプスや包帯による固定がきつすぎる場合も、血流が悪くなり、コンパートメント症候群を発症させる可能性があります。特に、骨折などの治療中にギプスを巻かれた場合は、圧迫の調整に注意が必要ですね。
余談ですが、よくドラッグストアに売っている着圧タイツやソックスをみかけますが、あのタイツを一時期履いていたことがあって、そのときは、足の浮腫みや血行不良を目的に使用していましたが、なぜか腹痛が起こり、それ以来履かなくなってしまいました(笑)
着圧タイツは、心臓や血圧に疾患のある方や、サイズ・圧力の調節が不適切だったり、朝から晩、寝る時に着用し続けるなどで血流が悪くなってしまいます。しっかり使用説明書を読んでから使うようにしましょう!(笑)
④交通事故に遭った人
交通事故による強い衝撃は、筋肉や筋膜を損傷し、内出血や腫れを引き起こすことでコンパートメント症候群を発症させる可能性があります。脛骨骨幹部骨折では、コンパートメント症候群を合併することがあります。

コンパートメント症候群の最も初期で特徴的な症状は、損傷の程度に見合わない強い痛みです。特に、関係する筋肉を動かしたり伸ばしたりすると痛みが悪化します。その他、以下のような症状がみられます。
・激しい痛み:見た目以上の局所に強い痛み
・腫れ:影響を受けた部位の急激な腫れや変形(稀に水疱がみられる)
・感覚障害:皮膚のチクチク感、熱感、筋肉の麻痺
・圧痛:強い圧迫感

コンパートメント症候群は、早期の診断と治療がとても重要です。治療が遅くなると、筋肉や神経が壊死して、永続的な機能障害や場合によっては、切断しなきゃいけないケースもあります。
急性と慢性で治療の内容が異なります。
急性の場合
まず患部を圧迫している物を取り除き、場合によっては鎮痛剤や筋弛緩剤などの薬を使うことがあります。疲労が原因で起こった場合、千歳市の青葉鍼灸整骨院では、とにかく圧迫してる筋肉を温熱治療器などを使って血流量をあげていきます。1つのアイテムとして、高濃度酸素マッサージオイルを患部にすりこむことで筋肉に素早く浸透し、疲労物質の乳酸を分解してくれる効果を発揮します。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、メンテナンスに来られる患者さんにもこのマッサージオイルを使用しています。気になった方はこちらもご覧ください。(O2クラフトオイル)
早期に手術をしなければいけない重度の場合は、皮膚と筋膜を切開して区画内の圧力を下げる手術を行うことがあります。
慢性の場合
慢性の場合、疲労が原因で起こっているケースが多いです。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、問題のある筋肉の血流改善を行いながら、どうしてそこに負担をかけてしまうのか、身体の動きをチェックしていきます。なるべく、負担が少ない状態で運動ができるように、家でできるようなセルフケアをお伝えすることもあります。
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
いかがでしたでしょうか。
この疾患は、放置するととんでもないことにもなりうるケースということがご理解いただけたのではないでしょうか。
千歳市の青葉鍼灸整骨院では、治療を受けなくてもご相談だけでもその方に最適な情報をお伝えしています。例えば、「こういう症状があるんですよね。」とご相談いただいたら、「その場合が、こういうことが起こっている可能性があるので、病院に行ってみて下さい。」や「それでしたら、うちで治療を受けた方が早く改善していきますよ」なのか、または「その場合は、2,3日様子を見てみて、痛みが落ち着くようだったらそのままでも問題ないし、痛みが引かないようであれば、来てください」などと、その方に必要なことを伝えています。なぜなら、痛みの原因が筋肉などの軟部組織だったとしたら、病院に行っても積極的な患部の治療ってやってくれない事が多いと思います。痛み止めの薬や湿布をもらい、飲んでみたけど全然効かないなんてことありませんか?そういう状態だったら、病院じゃなくて整骨院で治療を受けた方が無駄な時間が省けて、早く回復すると思いませんか?
どこの痛みでも、その人が今まで経験してきた痛みの程度や腫れてる具合などで、やばいか大したことないかなどを判断されると思います。でも、自分で勝手に判断して、何か月も放置していても症状が変わらないなんてことがあったら、自然治癒する程度ではなかった、ということになりますよね。手遅れになればなるほど、治療の選択肢が限られてきて、最悪手術しか良くなる方法がないと言われてしまったら、面倒ですし生活環境、仕事環境にも大きく影響してしまいますよね。そうならないように、目安としては、怪我して2,3日様子を見て、痛みが引いてくるようでしたらそのままでも良くなっていくと思いますが、痛みが引かない、腫れがひかないなどがあった時は、一度千歳市の青葉鍼灸整骨院にご相談頂ければと思います。もし、気になる症状・よくわからない症状などがあってお困りな時も、お気軽にご相談ください!


有痛性外脛骨腫 千歳市青葉鍼灸整骨院
千歳市の日常やスポーツでのケガ、交通事故後のムチウチなどを施術する整骨院。
青葉鍼灸整骨院の五十嵐です。
今回は、スポーツをする小学生になりやすい有痛性外脛骨腫について詳しく解説していきたいと思います。

有痛性外脛骨腫は、足の舟状骨の横にある「外脛骨」という余分な骨に痛みが生じる病態を指します。この外脛骨は、全人口の15~20%にみられるもので、痛みが無ければ問題はありませんが、痛みが出ると有痛性外脛骨腫と診断されます。特に、成長期のスポーツ活動が盛んな10~15歳に多く見られますが、成人になってから痛みを発症することもあります。
・捻挫や怪我
捻挫をきっかけに症状が出ることが多く、足関節が不安定になり外脛骨に負担がかかることで痛みが生じます。
・筋疲労(オーバーユース)
過度な運動による下腿(ふくらはぎやすねの周り)の筋肉の疲労が、後脛骨筋腱(足首の内側にある、底屈・背屈動作に関わる筋肉)を強く引っ張り、痛みを引き起こすことがあります。なぜなら、後脛骨筋腱の付着部が舟状骨と楔状骨なので、後脛骨筋が疲労してピンピンに張ると、外脛骨も圧迫を受けるというメカニズムなんです。
・靴による圧迫
偏平足で足幅が増加したり、外脛骨が突出している場合に、靴が当たって圧迫されることで痛みが生じます。
・偏平足や足の着き方
土踏まずのアーチが低下した偏平足や、かかとが内側に倒れるように(土踏まずのアーチを潰すような)足の接地の仕方が原因で、外脛骨に負担がかかりやすくなるんですよね。

・足の内側、特に舟状骨の内側の下の部位に痛みが生じます。
・痛みのある部分には、腫れ・熱感・赤みがみられることがあります。
・押すと痛む(圧痛)のが特徴です。
・歩行時、運動時、つま先立ち、靴を履いた時に痛みを感じやすいです。なので、痛みが強いと歩くのもびっこをひくような歩き方になってしまうのです。
・痛みが強い場合は、安静時や夜間にも痛みを感じることがあります。

有痛性外脛骨腫かどうか判断するのに、見た目にも特徴があります。足の内側に骨の盛り上がりがあり、その部分に自発痛(何もしていないのに、じっとしていても感じる痛み)や圧痛があることでも判断できます。
そして、画像診断では、レントゲンで舟状骨の内側に外脛骨が存在することを確認できて、外脛骨の形状も把握できます。
治療は、基本的に痛みがでなければ外脛骨があっても問題はないので、保存療法が中心となります。千歳市の青葉鍼灸整骨院では、外脛骨の負担を減らすために足関節の底屈・背屈動作をしやすくなるように下腿の筋肉や外脛骨周りの軟部組織を伸ばしたり緩めたりしていきます。あとは、外脛骨の炎症が早く治まるように微弱電流をあてることがあります。痛みが強い場合は、2,3日運動を休ませて回復を待ちます。痛みが引いてきたら、痛みの再発予防として、インソールを入れてもらったり、足の着き方を修正していくこともあります。
保存療法で症状が改善されない場合や、繰り返す場合は、手術療法が検討されますが、ほとんどが保存療法で症状が改善されます。ちなみに、手術をするとなると、痛みの原因となっている外脛骨を取る方法や、外脛骨と舟状骨を1つの骨につなげる方法などがあるようです。
①カウンセリング
ヒアリングをさせていただき、今どんなお悩みをお持ちなのかを確認します。
②アセスメント
身体の状況(姿勢、痛みの原因)を確認しながら、現在の状況を把握していきます。
③施術
痛みの原因となる筋肉、関節などに温熱治療器、高周波などを使ってアプローチします。
④エクササイズ
必要に応じてストレッチ、ピラティスなどを行い柔軟性を出していきストレスを改善します。
⑤プランニング
①~④を行った後に今後のプランを一緒に決めていきます。
いかがでしたでしょうか。
足関節は、自分の体重を支える大事な部位であり、負担も大きいのでなんぼ健康な人でも、わずかな炎症は起こりやすいものです。
どこの痛みでも、その人が今まで経験してきた痛みの程度や腫れてる具合などで、やばいか大したことないかなどを判断されると思います。でも、自分で勝手に判断して、何か月も放置していても症状が変わらないなんてことがあったら、自然治癒する程度ではなかった、ということになりますよね。手遅れになればなるほど、治療の選択肢が限られてきて、最悪手術しか良くなる方法がないと言われてしまったら、面倒ですし生活環境、仕事環境にも大きく影響してしまいますよね。そうならないように、目安としては、怪我して2,3日様子を見て、痛みが引いてくるようでしたらそのままでも良くなっていくと思いますが、痛みが引かない、腫れがひかないなどがあった時は、一度近くの整形外科で受診してもらった方が良いと思います。もし、気になる症状・よくわからない症状などがあってお困りな時は、お気軽にご相談ください!